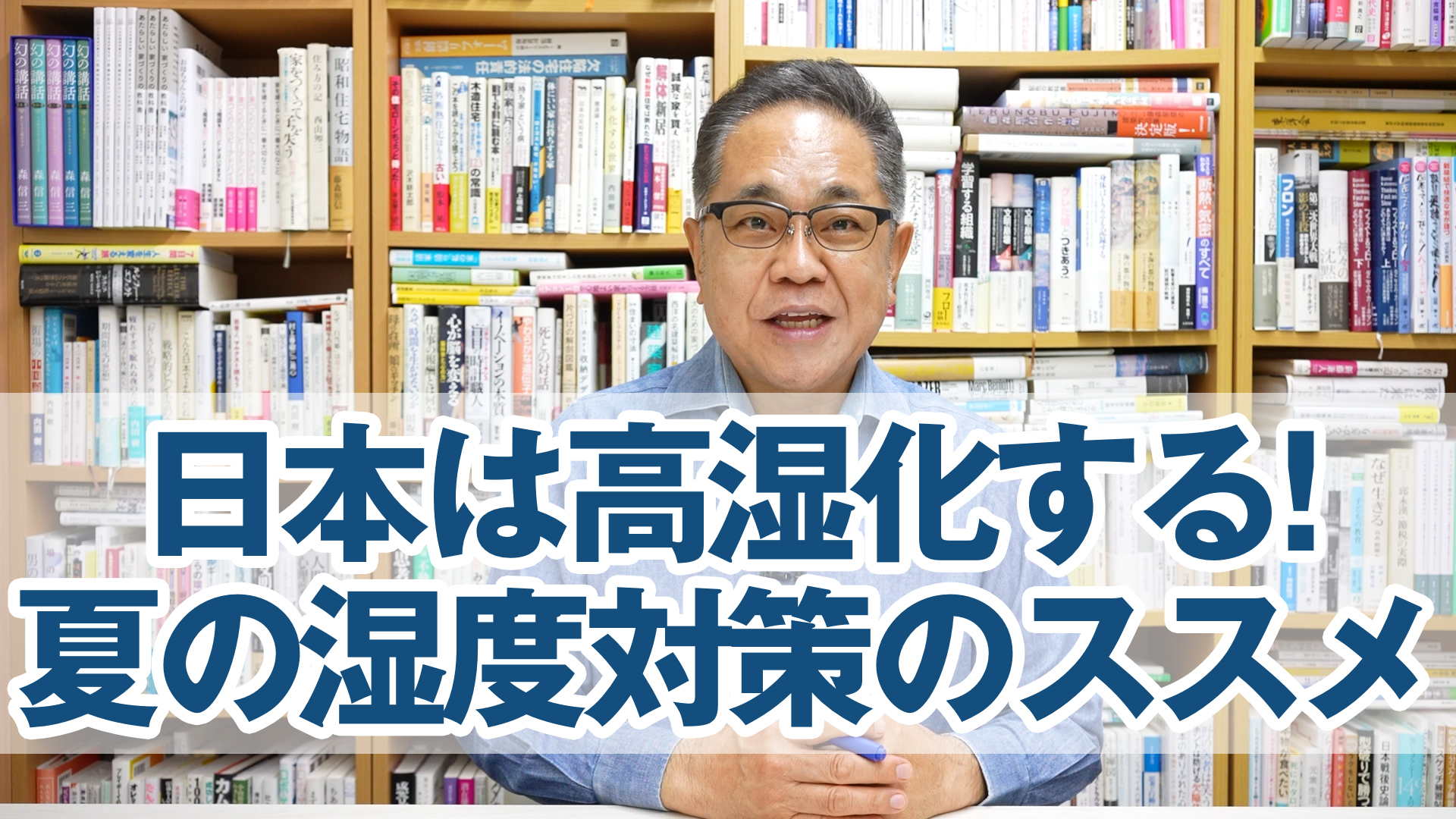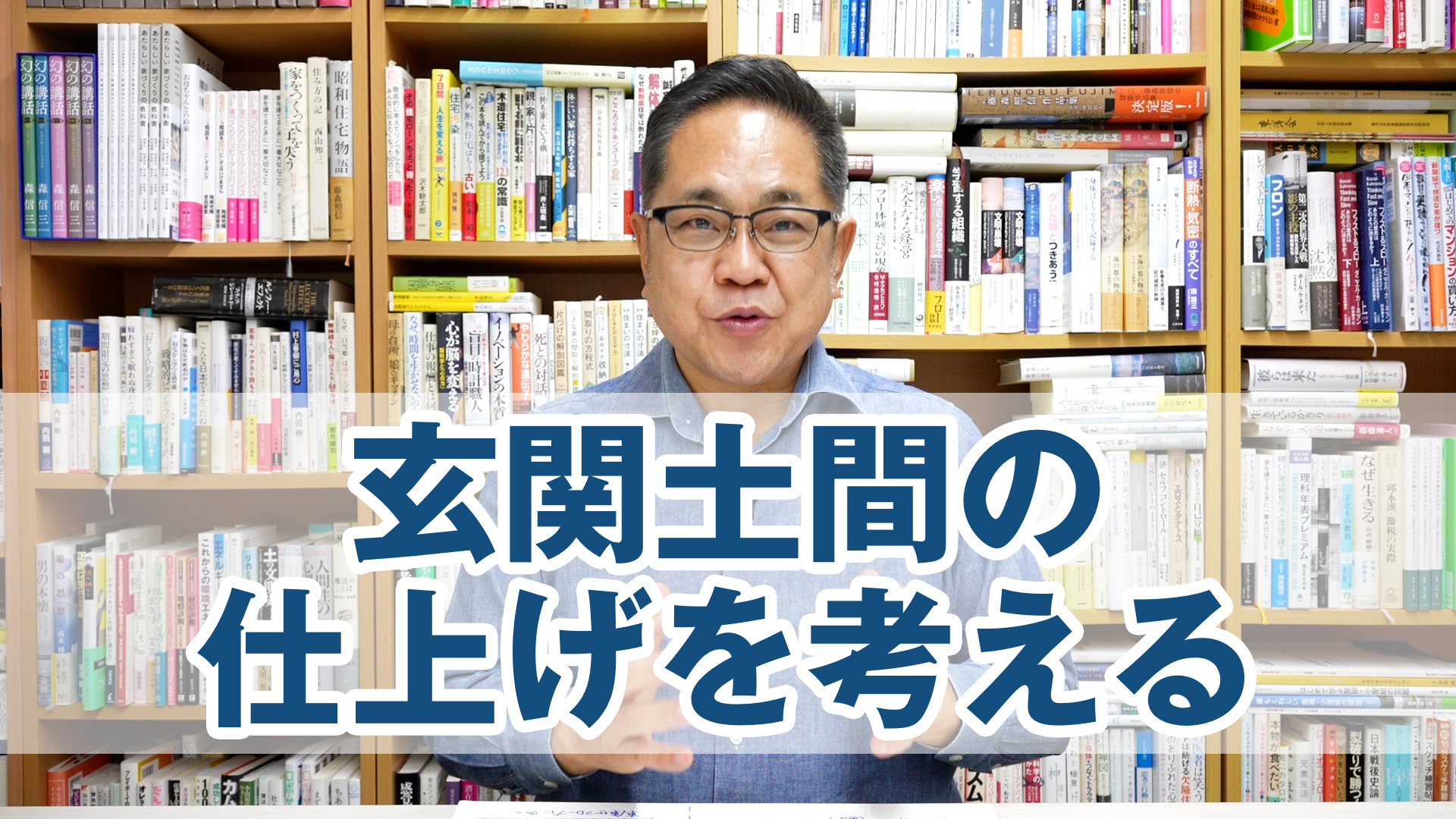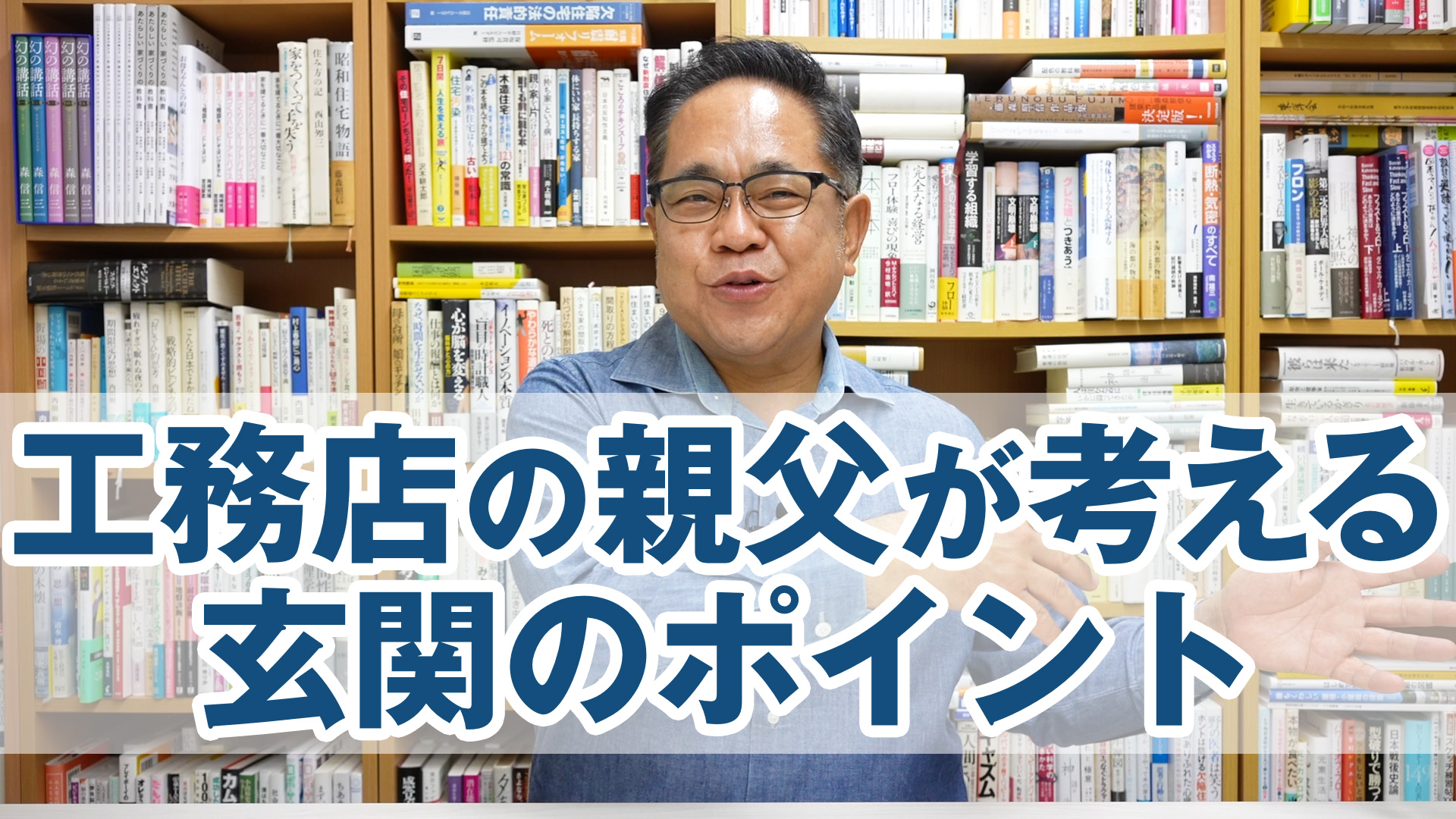かっこいいデザインの家の意外にコワイ注意点
▼雨漏りしやすい5つの場所とその対策
https://www.m-athome.co.jp/movie/amamori_basho_taisaku
今日は「最近流行っているカッコいい家が、実は意外と怖いんですよ」というお話をしてみたいと思います。もちろん、「カッコいい家を建てるな」と言いたいわけじゃありません。そうではなくて、「建てるなら、ちょっとここに注意してほしいですよ」というお話なんです。これまでも似たようなテーマを何度かお話してきましたが、特に最近感じるのは、やっぱりこの異常気象の影響ですね。平たく言えば、日本の夏がとても暑く、湿気が多く、しかも期間が長くなったということ。そうした今の気候環境で考えると、「デザイン重視の家」の怖さというのは、ますます顕著になってきたんじゃないかなと感じています。
では、具体的に何を僕が危惧しているのか。そのあたりを、いつものように板書を見てもらいながらお話していきたいと思います。まず、「カッコいいデザインの家」と一口に言っても、いろんなパターンがありますよね。たとえば、ベーシックな屋根があって、ちゃんと庇(ひさし)が出ているような家。こういう家は、通気や防水の仕組みが明確で、あまりばらつきがありません。でも、最近増えているのは、もう少し個性的なタイプ。たとえば「軒ゼロの屋根」って聞いたことありますか? 軒が全く出ていないデザインの家ですね。見た目はすごくシャープで、若い方には特に人気があります。
それから、キューブ状の箱のような家。あるいはその箱の一部をへこませたり、バルコニーを組み込んだようなデザイン。僕も以前の動画で、「立体的に見せると家はカッコよくなる」という話をしたことがありますが、まさにそういったタイプです。そして、もう一つ人気なのがビルトインガレージ。車好きの方には憧れですよね。「ガレージ付きの家が夢です!」という方も多いです。それに加えて、予算の関係で広い土地が難しくても、2階の面積を確保したいということで「オーバーハングタイプ」の家もよく見かけます。これは2階が1階より張り出しているタイプで、その下を駐車場やデッキスペースにして、ちょっとした中間領域をつくるような家です。最近は平屋の人気も強いので、「ほぼ平屋+少しだけ2階」という家も増えましたね。
こうした家々、見た目はすごく洗練されていてカッコいいんですが、意外な落とし穴があるんです。それが「家の耐久性を維持するための通気と換気」。壁の通気と、その出口である換気、そして屋根換気。この2つが本当に大切なんです。でも、デザインが複雑になるほど、これがうまくいかなくなるケースが増えるんですね。
たとえば、ベーシックな屋根の家なら、壁の中の通気層を上に上がっていった空気が、軒の裏(軒天)や小屋裏を通って、棟(むね)から自然に抜けていきます。太陽の熱で屋根が温まると、暖かい空気は自然に上に抜けようとしますから、吸気と排気がうまく循環するんです。でも軒ゼロの家になると、軒の部分がないために、通気の経路を確保するのがとても難しい。うまく計画しておかないと、空気が逃げ場を失ってしまうんですね。僕たちも実際に「軒ゼロでやってくれ」と言われることがありますが、完全な軒ゼロは現実的に無理なんです。見た目は軒ゼロに見えても、実際にはほんの少しだけ出して、その中で通気を確保しています。
現場で軒ゼロの家を見ると、僕もついじっと見ちゃうんですよ。「どんな納まりになってるんやろ?」って。職人さんに「ここ、どうやって収めてるんですか?」と聞いたりもします。やっぱり気になるんです。それくらい難しいんですね。
同じように、インナーバルコニーの家も怖いんです。バルコニーの床の下が1階の居室になっているタイプ。これは雨漏りが起きやすい構造です。だから止水と防水が非常に重要。でも実は、止水・防水と通気・換気って、トレードオフの関係にあるんです。隙間をなくして水を防ごうとすると、空気が抜けない。逆に空気を通そうとすると、水が入りやすくなる。だから、このバランスを取るのが本当に難しい。建築の世界ではこれを「雨じまい」と言いますが、このわずかな部分に職人の知恵が凝縮されるんです。
たとえばキューブ住宅の屋根。実はあれ、見た目はフラットな箱でも、上に上がると大きなバルコニーのように凹んでいるんです。そこには必ず「パラペット」と呼ばれる立ち上がりの壁があります。その下が屋根になっている。ここでも通気の出口をどう確保するかがポイントで、雨漏りを防ぎながら空気も抜けるような特殊な部品(焼き物部材など)を使って処理します。これをケチると、本当に怖いです。
さらに、屋根と壁の取り合い部分。ここは屋根の熱気が集中するので、換気を確保しないと、内部に熱がこもってしまいます。でも、やっぱりここも雨仕舞いとのせめぎ合い。水を防ごうとすると隙間がなくなり、空気が逃げられない。逆に空気を通そうとすれば、水の侵入リスクが上がる。この二律背反をどう解決するかは、職人の腕と設計の配慮次第なんです。
最近特に増えているのが「夏型結露」という現象です。夏に結露が起きるというもの。たとえば、屋根の下が居室になっていて、外は猛暑、室内はエアコンで冷やしている場合、断熱や通気が十分でないと、壁の内部で湿気が結露してしまうんです。「雨も降ってないのに雨漏り?」と思ったら、実は結露だったというケースが本当にあります。これも、通気や換気の設計がうまくいっていないと起こりやすいんです。
ビルトインガレージやオーバーハングの家も同じ。通気層が複雑になり、熱や湿気がこもりやすい。さらに断熱ラインがずれていたりすると、そこから劣化が始まってしまう。だからこそ、こういうデザインの家を建てる時は、しっかりした技術と考え方を持つ会社さんにお願いすることが大事です。
ただ、残念ながら分譲住宅などでは、不動産会社が地元の工務店に発注して「この予算で建てて」となると、細かい部材を省いてしまうこともあります。「雨漏りしてないから大丈夫でしょ」と。でも、それでは本当の意味での耐久性は担保できません。だから、もしデザイン重視で家を建てるなら、ぜひ「この部分の通気や換気はどうなっていますか?」と設計段階で確認してください。現場が始まってからでも、監督さんに「ここ、どう抜けるようになってますか?」と聞いてみるのもいいと思います。決して意地悪ではありません。むしろ、そういう質問ができるお客さんがいることで、現場も品質意識が高まります。
僕はいつも思うんです。家づくりというのは、施主さんと工務店が協力してつくる“協業作業”なんです。プロに任せきりではなく、一緒に考えていく。それが結果的に、より満足度の高い家づくりにつながると思います。
最近は若い方だけでなく、シニアの方でもデザイン性を重視する方が増えています。だからこそ、見た目の良さだけでなく、「その裏側にある仕組み」にも関心を持ってもらえたらと思います。そうすることで、安心して長く住める“本当にいい家”になるはずです。