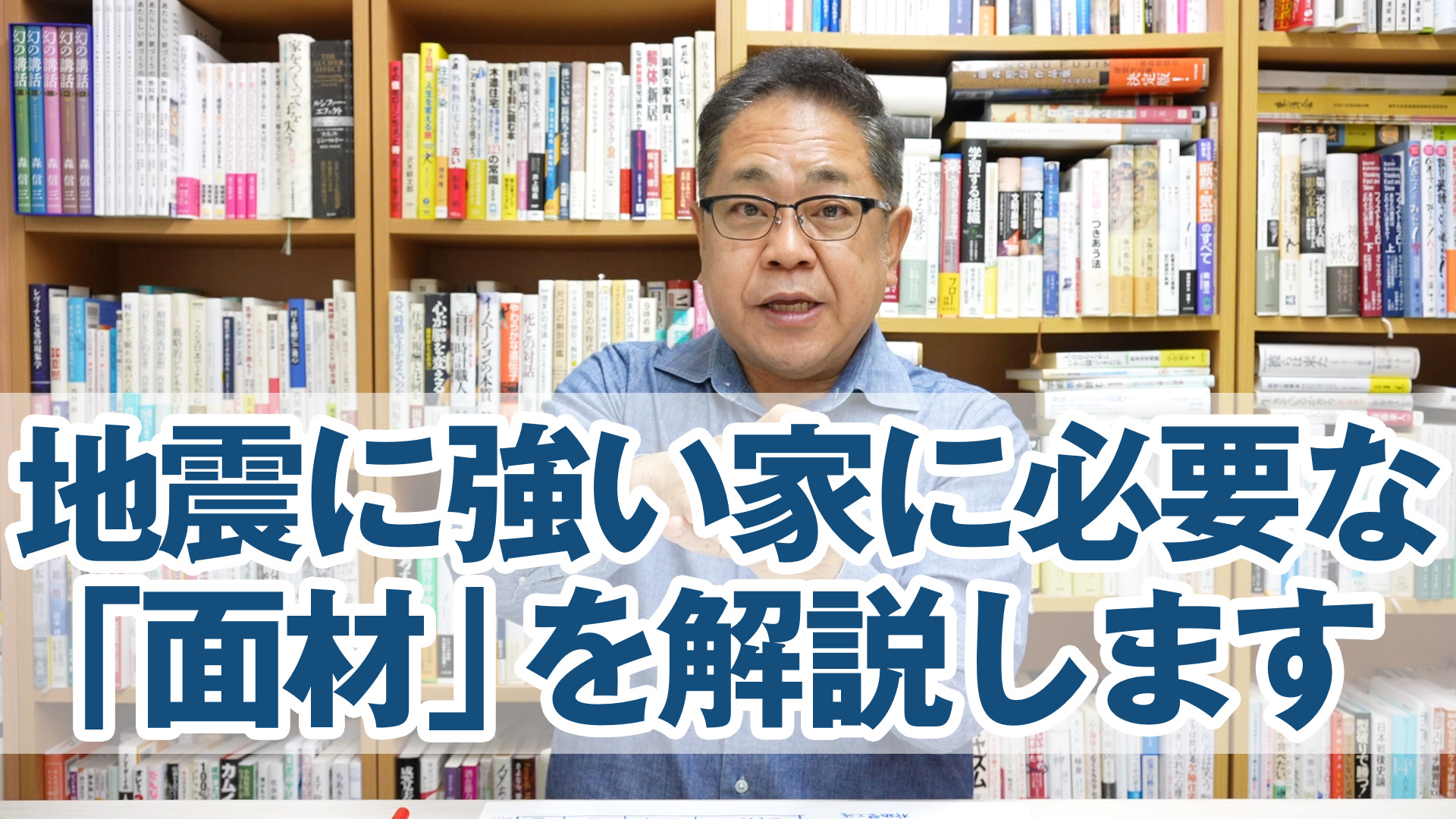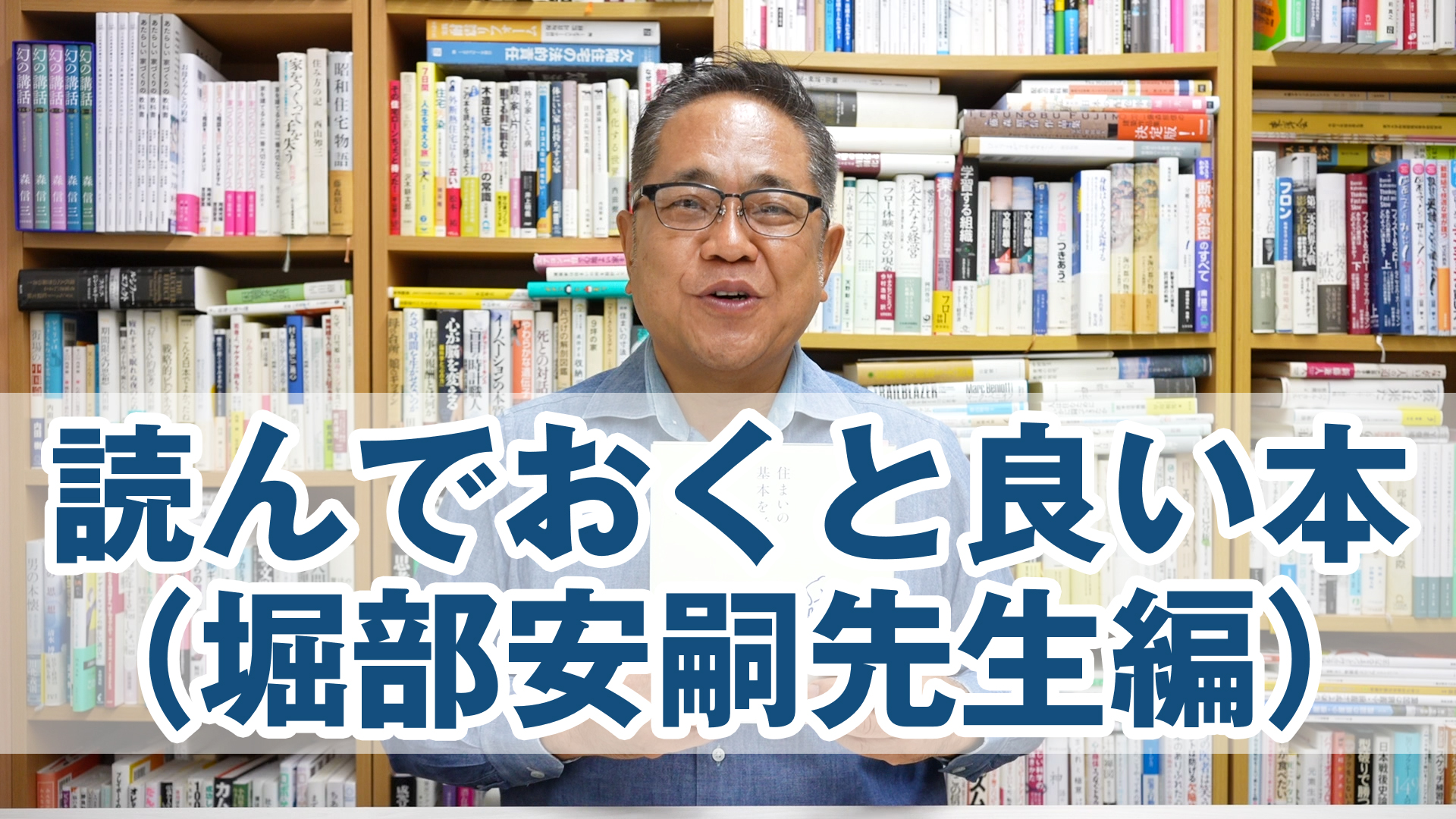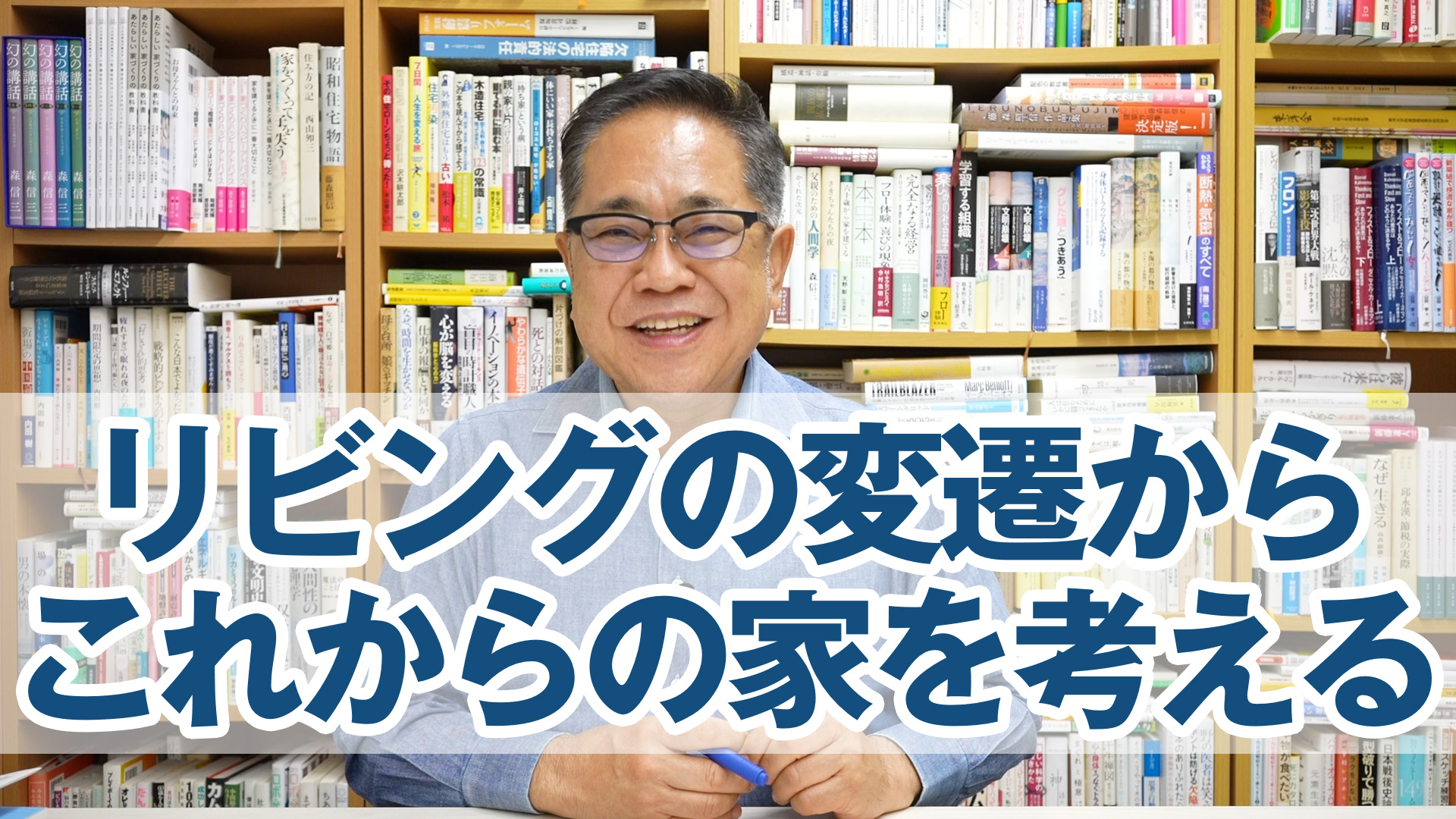リプロダクションコストについて考える
みなさんこんにちは、モリシタ・アット・ホームの山下です。前回はモデルハウスを建てるにあたって、まず最初に「土地を読み解く」ということについてお話させていただいたんですが、今日はその次のステップとして、私たちが何を考えるのかということを進めていきたいと思います。
▼新モデルハウス完成までの道のり「土地を読み解く」
https://www.m-athome.co.jp/movie/model_michinori_tochi
次に取り組むのは、実は「家のコンセプト」、つまり大きなテーマを決める作業なんです。その中で、今私がすごく気になっているテーマのひとつに「リプロダクションコスト」という言葉があります。あまり聞き慣れない方も多いと思いますので、今日はこのリプロダクションコストについてのお話と、それをモデルハウスづくりにどう活かしていくのかという点に触れていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。
まず「リプロダクション」という言葉自体に馴染みがない方も多いと思いますので、その意味からお話しますね。リプロダクションには「再生」とか「生殖」「再現」といった意味があります。いろいろな使われ方をするんですが、今日お伝えしたいのは「家のリプロダクションコスト」についてです。ここに書いたように「家を再生させるための費用」と定義しています。この再生とはどういうことかといいますと、家というのは家族の成長や暮らし方に合わせて役割が変わっていくんです。例えばお子さんが小さい時期、思春期、就職して独立していく時期など、家族のライフステージに応じて住まいの使い方は大きく変わりますよね。夫婦二人の生活の中でも同じように転機は訪れるもので、私は最低でも二度は「再生」のタイミングがあると思っています。
まず一つ目が「子育てが終了した時」です。実際に住宅相談の場でも「子どもが育って夫婦二人になったけど、今の家は広すぎて持て余している」「使っていない部屋があってもったいない」といった声をよくいただきます。その結果「減築できないか」とか「もっとコンパクトな家に建て替えたい」という相談につながるんです。さらに、使っていない部屋でも維持管理は必要で、家はなぜか使わない空間から傷んでいくことが多いですし、雨漏りのような問題も放っておけません。つまり使わなくてもお金はかかるんです。これもリプロダクションコストの一つだと思っています。
二つ目が「住めなくなった時」です。これは家が古くなって住めないという意味ではなく、例えば夫婦どちらかが亡くなったり入院したりして、一人で住むことが難しくなった時のことです。その時に「この家をどうしていけばいいのか」と悩む方は本当に多いんです。実際に弊社代表の森下が「家じまい」「空き家」などの問題に取り組んでいて、相談に来られる方のお話を聞く機会が私も多いのですが、皆さんまず口にされるのは「処分するのにお金がかかる」ということ。相続があっても、古い家では子どもが住みにくくて大規模リフォームが必要になったり、立地がよければ売却も可能ですが、そうでない場合は本当に悩まれるんです。さらに最近増えているのが「そもそも相続する人がいない」というケース。子どもがいない方も多いですし、兄弟や甥姪に託すのも現実的ではないと考える方も多いです。こうしたことが、まさにリプロダクションコストなんです。だからここを真剣に考えておかないと、せっかく家を建てても、最後に大きな悩みを抱えてしまうんじゃないかなと、最近つくづく感じています。
これまでは「家のトータルコストを安くしましょう」とお伝えしてきました。トータルコストといえば一般的には「イニシャルコスト」と「ランニングコスト」を合わせたものですよね。多くの会社さんもその二つを前提にしています。でも私はそこに「リプロダクションコスト」も加えて考えるべきだと思っています。つまり、建てる時のお金、住んでいる間のお金、そして最後にかかるお金。この三つを合わせて本当の意味でのトータルコストなんじゃないかなと。ですから、これからはこの三つを意識して、なるべく抑えられる家づくりを皆さんにお伝えしていきたいと思っています。
ではどうやって抑えるのか。そこで私がモデルハウスのコンセプトに必ず盛り込みたいと思っているのが「小さく作る」という考え方です。特別なことではありませんが、実際に設計しようとすると意外と難しいテーマなんです。狭い・窮屈と感じさせないことが大切ですから、夫婦二人で暮らしても広々と感じられ、さらに子育てにも対応できる家を目指したいと考えています。そうすることで、子育てが終わった後も大きなリフォームや住み替えを考えなくてもいい住まいになります。
小さく作ると、イニシャルコストの本体工事費や付帯工事費、外構費、諸費用も抑えられますし、ランニングコストの光熱費や修繕費、さらには固定資産税や保険料といった支出も少なくできます。つまり「小さく作る」ことでイニシャルとランニング、両方をしっかり抑えられるんです。
じゃあ夫婦二人でちょうどいい大きさってどれくらいなのか。私も休日に妻と一日の行動を振り返ってみると、生活のほとんどがリビングと水回りの往復で、意外と広さはいらないんじゃないかと感じました。でも感覚だけで決めるのもよくないので調べてみると、「住生活基本計画」による住宅面積の水準というものが国交省から出ていました。そこには最低限の居住面積と、豊かな生活を想定した誘導居住面積という基準があります。私たちが参考にしたいのは後者で、戸建て住宅を想定した「一般型」では、二人世帯で75平米、四人家族で125平米という基準です。これを坪に換算すると、二人で約22.7坪、四人で37.8坪ということになります。
実際にお客様に希望を伺うと、四人家族の方は「40坪くらい欲しい」と言われることが多いですが、子育てを終えた方に聞くと「20〜23坪くらいの平屋で十分」とおっしゃるんです。皆さん感覚的にちょうどいい広さを理解されているんだなと感じました。ですので、私たちがこれから建てるモデルハウスは「小さく作る」をコンセプトに、具体的には22坪前後を目安にしたいと思っています。夫婦二人にはちょうどよく、子どもが二人いても快適に暮らせる設計を目指します。
もちろん、モデルハウスなので「小さく作る」だけではなく、他にも2〜3のコンセプトを組み合わせて、皆さんに楽しんでいただける、参考になるような住まいを形にしていきたいと思っています。構想もだいぶ固まってきましたので、これから随時進めていきます。どうぞ楽しみにしていただければと思います。