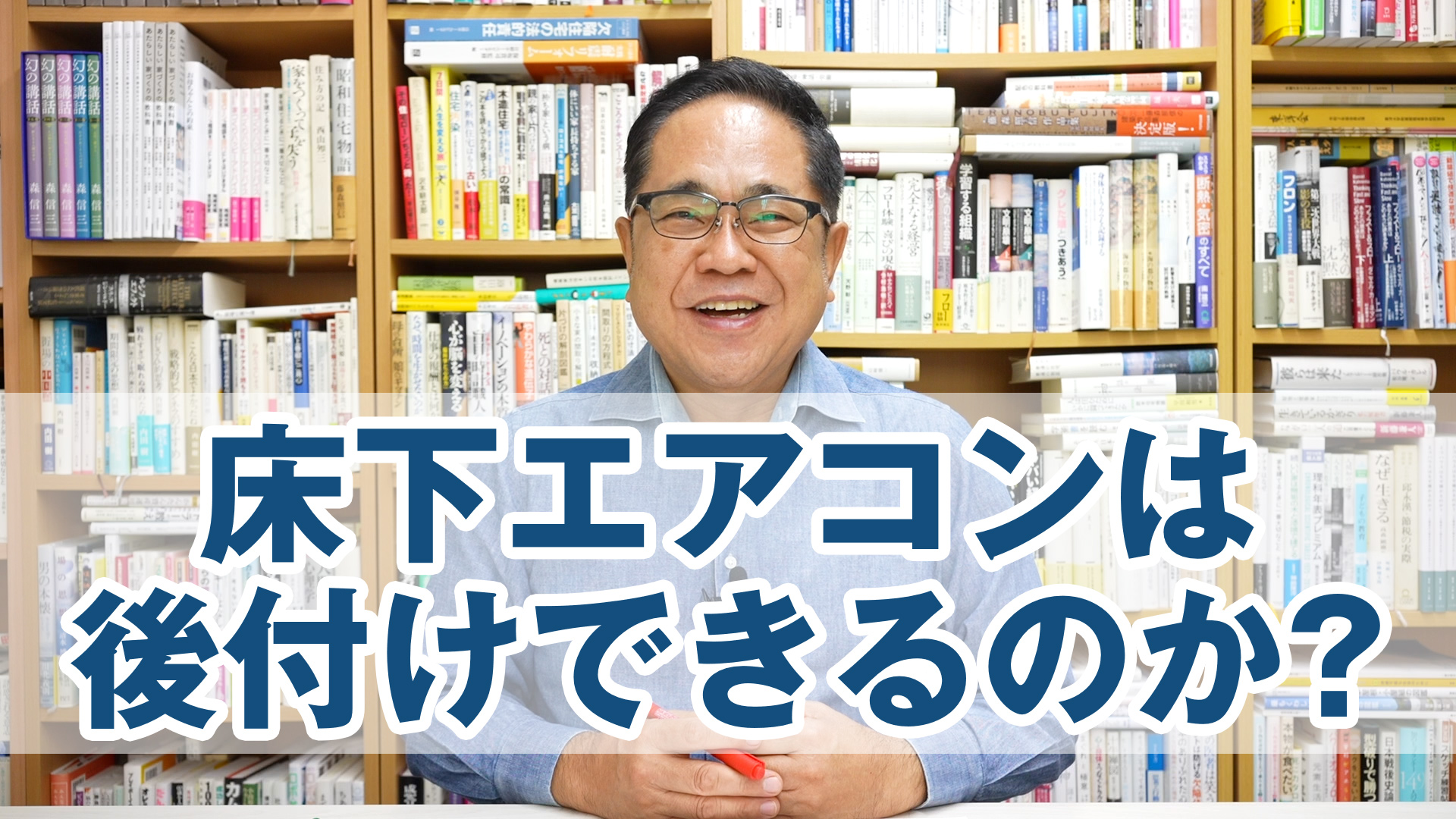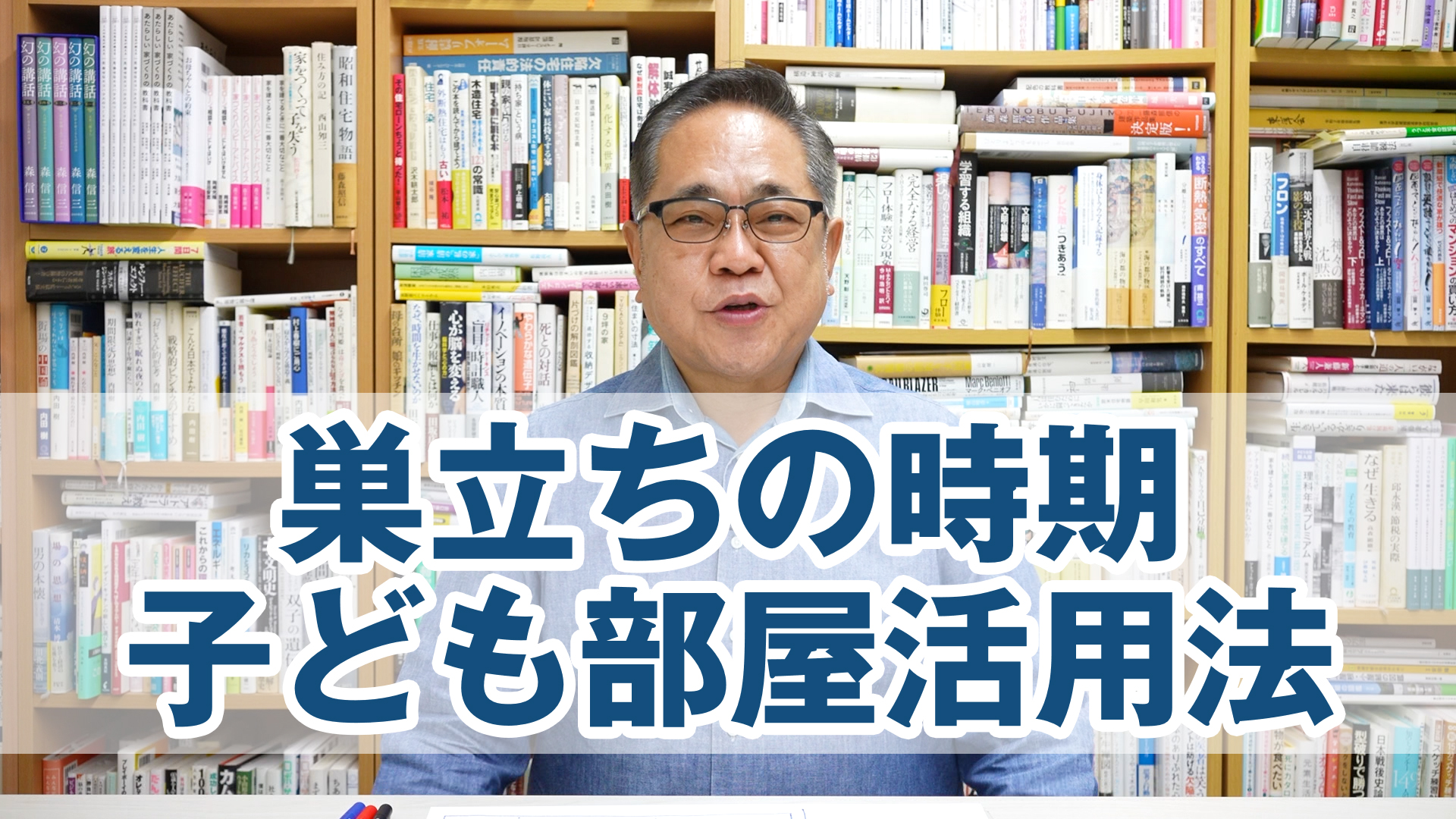高性能化した日本の家が夏に涼しくない理由
本当に暑いですね。こうなってくると、そろそろ冷房をどうするかということにも関心が高まってくると思いますので、今日はそれにちなんだテーマでお話ししたいなと思います。それは、「日本の家って高性能化してきたのに、なぜか夏に涼しくないという問題が全国で起きている」というトピックなんです。この話題について、5月30日発行の新建ハウジングという、僕たちプロが読む業界紙で、大鳥建設の森浩介さんがとても上手く記事を書かれてまして、これはぜひみなさんにも知っておいていただきたいなと思いましたので、今日はその内容を僕なりに解説していきたいと思います。
それではいつものように、僕の板書を見ていただきながら聞いてもらえたら嬉しいんですけど、日本では2025年4月から新築住宅に断熱性能の義務化が始まります。義務化というのは、新築なら断熱等級4以上に絶対しておかなアカン、ということですね。これは賃貸住宅も例外じゃなく、普通の賃貸にも義務化されることになりました。これは本当に画期的で、すごくいいことやと思います。今まではあまり厳しい制約がなかったんですが、ここ最近は高気密・高断熱住宅が一般的になってきた反面、新たな問題も出てきたんです。
それは何かと言うと、この高気密・高断熱の家って、昭和っぽい言い方かもしれませんけど、よく「魔法瓶のような家」と表現されてきましたよね。実際、魔法瓶のように家の中の温度が保たれるという点では本当に優れているんです。ただ、魔法瓶に例えるなら、夏は中に冷たい水を入れないと意味がないし、冬は温かいお湯を入れないといけません。つまり、家も同じで、その季節ごとに合った熱を作って取り入れることが大事なんです。家は単なる器じゃなくて、そこに人が暮らすわけですから、ただ高性能な家ができればいいという話でもないんですよね。ですので、夏はエアコンでしっかり冷房することがすごく大事になってきます。
また、別の動画でもお話ししましたが、昔の人は「風通しのいい家がいい」とよく言いますよね。確かに昔の日本なら風通しが良ければそれで快適だったんですけど、今の日本は高温多湿ですから、風通しを良くしても結局は暑くて湿気た風が入ってくるだけなんです。だから全然涼しくならないんですよね。本当に、風通し神話というのはまだまだ根強くて、うちの母も「風通してるから大丈夫」「扇風機回してるし」と言うんですが、「いやいや、お母ちゃん、冷房つけとかんと熱中症になるで」と、毎年のように言ってます。自分では平気やと思ってても、実際には気づかず倒れる方も多いですから、電気代を惜しむより倒れないでほしいなと、ついお願いしてしまうんです。
そう考えると、これからの日本の暮らし方としては、省エネ性能の高い、いわゆる魔法瓶のような家にすることとあわせて、エアコンでしっかり冷やすということが絶対必要になってくるんです。そして、エアコンについてもAPFという専門用語がありますが、効率の良いAPF値の高いエアコンを使うこと、これが「日本の家を涼しくする基本公式」になってきます。でも、ここからが大事なポイントなんです。「そんなの当たり前やん、森下さん」と思われるかもしれませんが、実は「夏に室温は低くなったけど、なぜか湿度が高いまま」という現象が、今の日本の家でよく起きているんですね。
これはどういうことかというと、高性能な今どきの住宅のエアコンは、家の中の冷えた空気が外に抜けにくくなっているんです。でもエアコンが優秀なほど、設定温度まで達するとピタッと止まるんですね。この「止まる」のは省エネ的にはとても良いんですが、一方で24時間換気はずっと動いているので、外から湿気た空気が入ってきます。ところが、すぐに室温が上がるわけではないので、その間にちょっと困ったことが起きるんです。エアコンがピタッと止まると、冷やすのも除湿も一緒に止まるので、エアコンの中は除湿された水がたまったままになる。これ、俗に「湿気戻り」と言うんですが、止まっている間にエアコン内部の水分がまた部屋の空気に戻ってきてしまうんです。その結果、家の中の湿度はだんだん高くなっていって、「温度は低いけどなんかすっきりしないな」と感じることが増えてきたんです。
うちの妻も「そんなに湿気てる?」とか「これくらいでいいけど」と言うんですけど、僕はもうちょっと除湿したいから低めの温度にするんです。そしたら「寒い!」って怒られて、エアコン切られてしまう、なんてこともよくあります。こんな感じで、夫婦喧嘩の原因になったりもするんですよね。でも、温度を高めに設定すると、水分の飽和量が増えるので湿気を多く含みやすくなり、結果的に悪循環が起きてしまうんです。
大鳥さんも記事でおっしゃってましたけど、APF値の高いエアコンほど、高効率なコンプレッサーをできるだけ休ませようとするので、省エネ性は高いけど、ピタピタ止まることで除湿が追いつかなくなる現象が起きるんですね。実際、名前は出せませんが、高性能で有名な某工務店さんのユーザーさんにお話を伺ったことがあるんです。その方は「床がベタベタするんですけど、どうしたらいいんですかね」と相談されたことがあって、「それって床のフローリングがウレタン仕上げだから?」とか「絨毯を敷いた方がいいんですか?」と悩まれていました。でも、やはり根本的には、こうした現象が起きてしまっているわけです。
実際に、空調までしっかり工務店さんがやってくれていれば良いんですけど、多くの場合はリビングや各部屋に個別でエアコンをつけるパターンが多いですよね。そうすると、各部屋がすぐ冷えるから、またすぐ止まる。除湿が追いつかないまま、換気でどんどん湿気が入ってくる、そんな状況になってしまうんです。僕の親友の小暮社長も「どうやって除湿をし続ける家にするかが大事やで」とよく言っています。みんなUA値やC値にこだわって、「これさえ低ければ完璧」みたいに言う方もいますが、それも一定のラインまではもちろん大切です。でも、それよりもっと大事なのは「どうやって除湿できるか」をしっかり考えることなんじゃないかなと僕は思います。そのことが分かってもらえない時は、ちょっと悲しくなってしまうんですよね。小暮社長、意外に情熱的な男なんです。
ですので、そういったことをぜひ頭に置いて、他の動画でも松尾先生の記事を僕なりに解説していますので、そちらも参考にしていただければ、解決のヒントが見えてくるかなと思います。高性能な家なのに、なぜか夏に涼しくない、ということが自分の家で起きないように、ぜひ空調や家づくりのことを考える時に注意してみてほしいです。