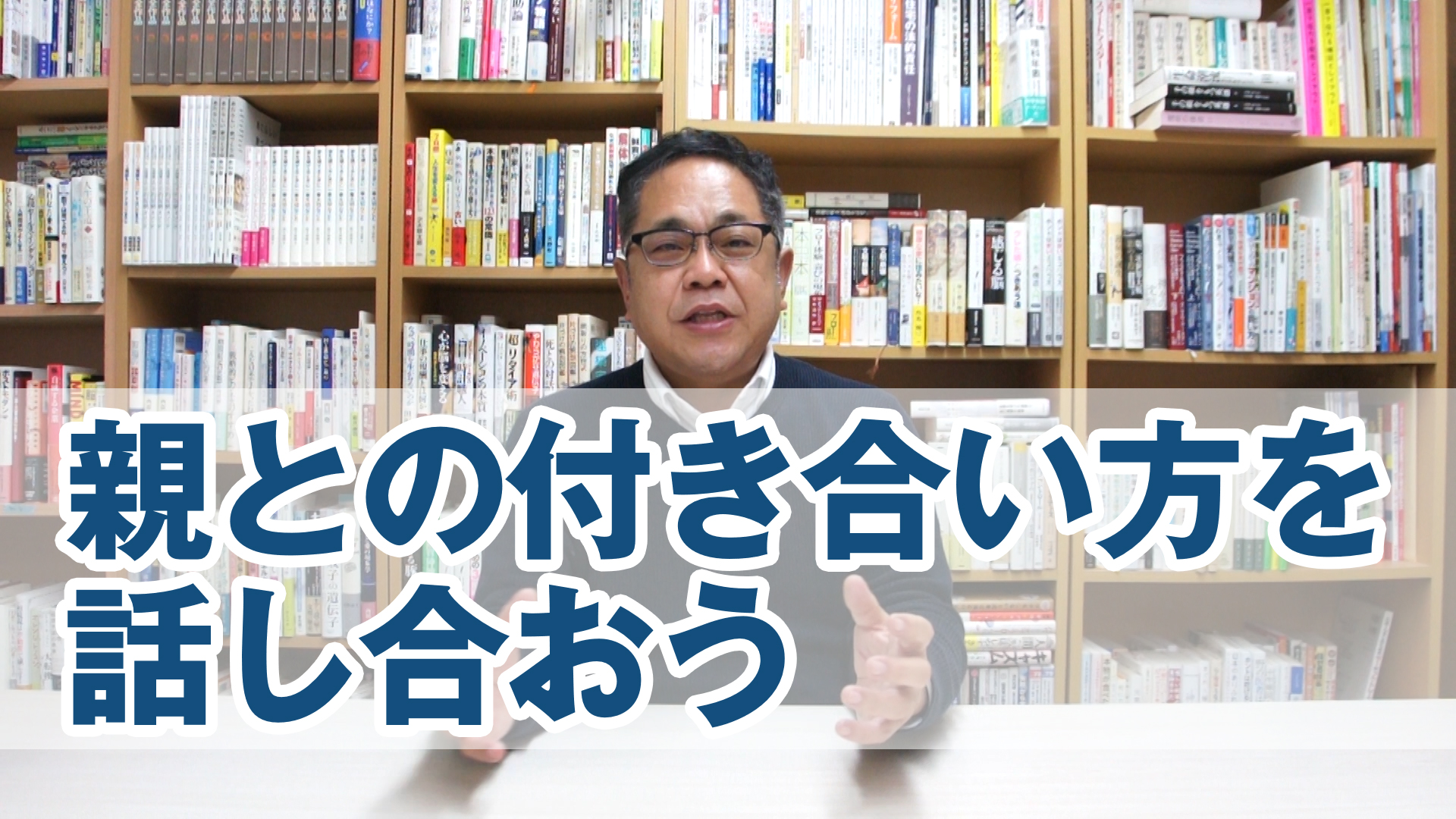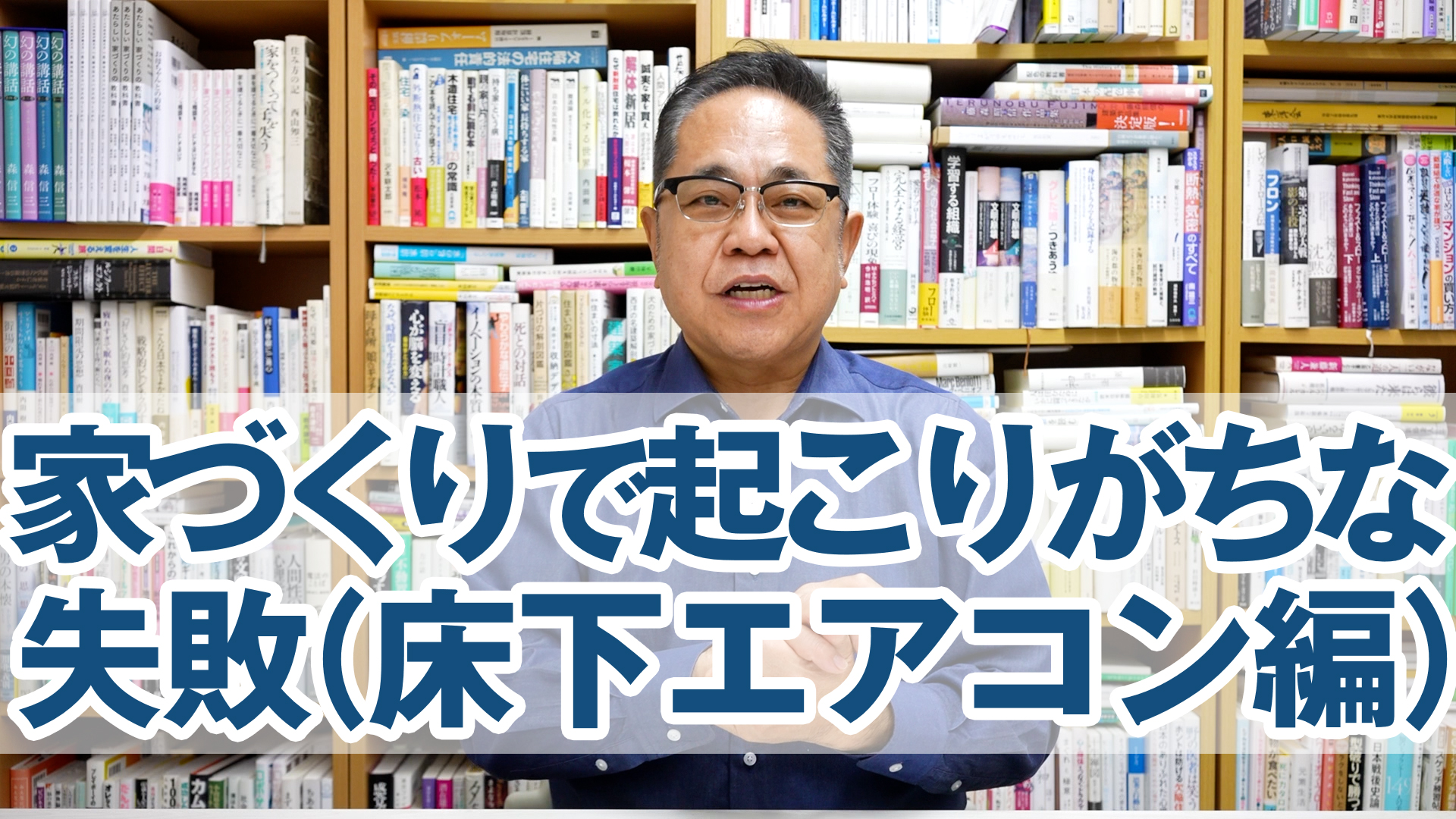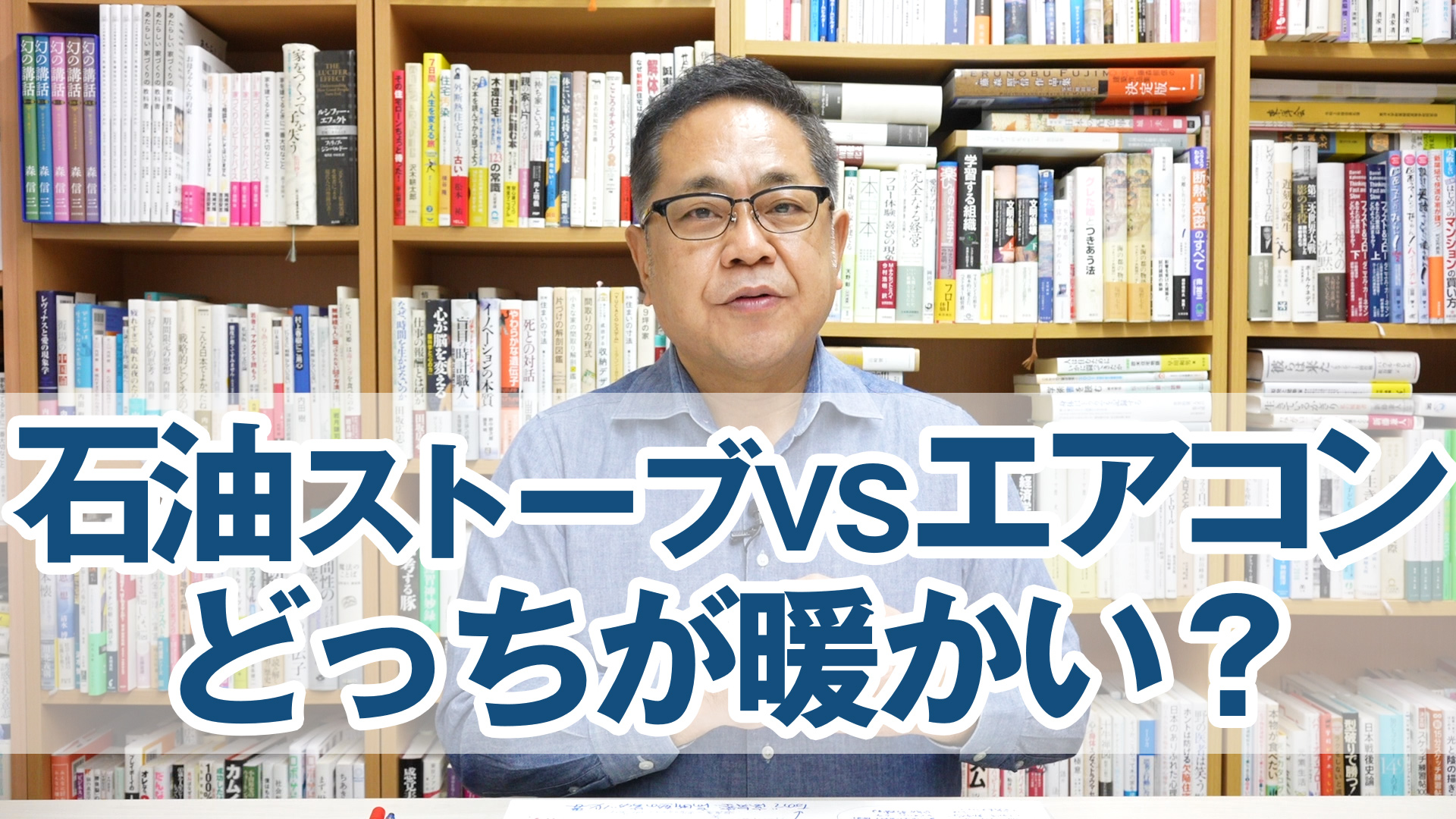今さらながら有線LANの有用性を考える
今日はちょっとした小ネタというか、Wi-Fiとか無線LANという言葉がすごく浸透している今、そのもっと前の“有線LAN”について少しスポットを当ててお話しできたらなと思っています。というのも、お客さんとの打ち合わせの中で「LANケーブルを引いておいた方がよかったですね」とか、住み始めてから「やっぱりLANケーブルを入れといたらよかったです」と言われることが、最近ほんの数人ですけど続いたんです。そういう話を聞くと、皆さんにもあらかじめお伝えしておいた方がいいんちゃうかなと思いまして、今日はそんな小ネタをお話ししようと思います。
今の子どもたちは、もう完全にWi-Fiネイティブですよね。無線でつなぐのが当たり前で、コードをつなぐという経験があまりない世代。せいぜい学校で少しやるくらいでしょうか。僕らの世代はどっちかというと旧タイプで、1995年のWindows95が出た頃からなんです。当時はインターネットが世の中に出始めたばかりで、僕らは子どもの通う学校にボランティアでLANケーブルを引っ張って、インターネット環境を整えてあげよう、なんてことをしていた時代です。まさに“線を引っ張る”のがインターネットの世界だったんですよね。
最近になって、テレワークとかリモートワークで家で仕事をする方が増えました。最初は「Wi-Fiでできるやん」と思っていたけど、実際にシビアなオンライン会議をしているときに、Zoomが止まったり、画面共有のプレゼンがうまく動かへん、なんて経験された方も多いと思います。僕もNetflixやAmazonプライムなど、ネットで映像コンテンツを見るようになってから、ストリーミングが安定しないことがありました。せっかくデジタルリマスターされた綺麗な映像を見たいのに、Wi-Fi環境が不安定で、画面がカクついたりする。あの「うーん…」という感じ、ありますよね。
さらに、僕はやりませんけど、オンラインゲームの世界では通信の品質が命です。何億円もかけて大会に出るような人もいて、アメリカの人とリアルタイムで勝負するようなこともある。そのレベルになると、Wi-Fiでは限界がある。やっぱり有線LANの安定性が圧倒的なんです。無線LANって便利なんですけど、壁や天井、特に鉄筋コンクリートの家だと電波が通りにくいですし、電子レンジやBluetoothなど、目に見えない干渉も多い。だからこそ、有線LANはそういった影響を受けず、安定しているという大きな強みがあります。
あと、Wi-Fiの設定って子どもたちはフワッとやってしまいますけど、うちのばあちゃんには無理です。「どこに線を挿すんじゃ?」って言ってますし、僕もその気持ちはわかります。設定に手こずるより、線を“カチッ”と挿すだけで終わる方が安心です。それに、電波の“ただ乗り”というリスクもありますよね。自分の家のWi-Fiを使おうとしたら、知らないSSIDがいっぱい出てきて、隣近所のWi-Fiが表示される。そういうのを悪意ある人が乗っ取ることも理論上は可能です。その点、有線LANはセキュリティ面でも安心です。
中には「Wi-Fiの電波が飛んでると眠れない」という人もいます。実際、僕の知り合いにもホテルの無線LANが原因で寝られないという方がいました。そういう意味でも、有線LANの方が安心して使えるという人もおられます。もちろん、デメリットもあります。ケーブルを長く引き回すと、その途中で劣化したり、ノイズを拾ったりすることもありますし、ケーブル自体に寿命もあります。うちの会社でも、20年前のケーブルが切れていて交換したことがありました。特に鉄骨の建物では、わずかに振動して当たることで、年月を経て切れることがあるんですね。
それでも有線LANには大きなメリットがあります。だから僕の提案としては、これから新築を建てる方は、リビングや仕事部屋、それから大画面テレビを置く予定の場所など、必要になりそうなところにLANの配線を計画しておくのがおすすめです。最近は子どもが成人しても実家で暮らすケースも多いですし、それぞれの部屋で快適なネット環境を求める時代です。昔は各部屋にテレビ端子を付けましたよね。それと同じ感覚で、LAN端子も設けておくといいと思います。
少し専門的な話になりますが、LANケーブルにも種類があります。いわゆる“カテゴリー”という規格ですね。一般的な順に言うと、カテゴリー5・5E・6・6A・7・7A・8とあって、数字が上がるほど通信速度と伝送帯域が広くなります。昔はカテゴリー5で十分でした。100Mbps出たらすごい時代で、僕らは「もうこれで一生大丈夫やろ」と思ってました。でも今は、家庭用でも光回線が1Gbpsとか10Gbpsの時代です。カテゴリー5だと、その10分の1の速度しか出ない。せっかく速い回線を契約しても、ケーブルでボトルネックになってしまうわけです。
今なら最低でもカテゴリー6、できれば6Aがおすすめです。これなら10Gbpsに対応しますし、当面は困ることはないでしょう。オンラインゲームを本格的にされる方はカテゴリー7を選ぶとより安心です。ちなみにカテゴリー8はデータセンター用なので、一般家庭では不要です。こうやって聞くとマニアックに感じるかもしれませんが、今後AIとか3D映像とか、どんどんデータ量の多い時代になっていくと考えると、家のネットワーク品質は決して軽視できないと思います。
あと、LANケーブルにはノイズ対策の有無もあります。工場の近くや電波の強い場所では、ノイズに強い“シールド付き”タイプを選ぶと安心です。それからケーブル自体にも、極細やフラット、柔らかタイプなどいろんな種類があります。施工性や見た目で選んでもいいですけど、僕が今話しているのは、家の壁の中に埋め込む“配線用”のスタンダードなケーブルのことだと思っておいてください。
ここで注意してほしいのが、電気工事の世界では「強電」と「弱電」に分かれていること。照明やコンセントなど高い電圧を扱うのが強電、電話線やLAN、インターホンなどの低電圧を扱うのが弱電です。一般的な電気屋さんは強電が得意で、弱電には詳しくない場合もあります。ですから、有線LANを建物に仕込むときは、「線だけ通しておいて」ではなく、必ず“CD管”という配線用の管を通してもらってください。
このCD管を入れておけば、あとでケーブルを抜き替えられます。時代が変わっても対応できますからね。一般的な住宅では16mmのCD管を使うことが多いですが、カテゴリー7のような太いケーブルだと通りにくいことがあります。できれば22mm、2本入れたいなら28mmくらいにしておくと安心です。特にオンラインゲームを本格的にやる人は、将来的に品質の差が大きく出るので、最初からその準備をしておくといいと思います。
あと、10m以上の長い距離を引くときは、ケーブルの構造にも注意してください。“単線”と“より線”という2種類があって、単線は硬くて曲げにくいけど、信号が安定して遠くまで届きます。より線は柔らかく施工しやすいけど、長距離にはあまり向きません。10mを超えるなら単線タイプを選ぶといいでしょう。
こんなふうに、有線LANって一見地味な話なんですけど、実はこれからの家づくりにとってすごく大事なんです。これからの時代、AIとかホームオートメーションとか、いろんな家電がインターネット経由でつながっていきます。そうなると、1階・2階、そして3階まで、それぞれ安定した回線がある家って、生活の質が全然違ってくると思うんです。「Wi-Fiがあるから大丈夫やん」ではなく、「より快適で高品質な通信を確保する」という考え方。そんなことを、家づくりの計画の中で少し頭の片隅に置いておいてもらえたら嬉しいです。