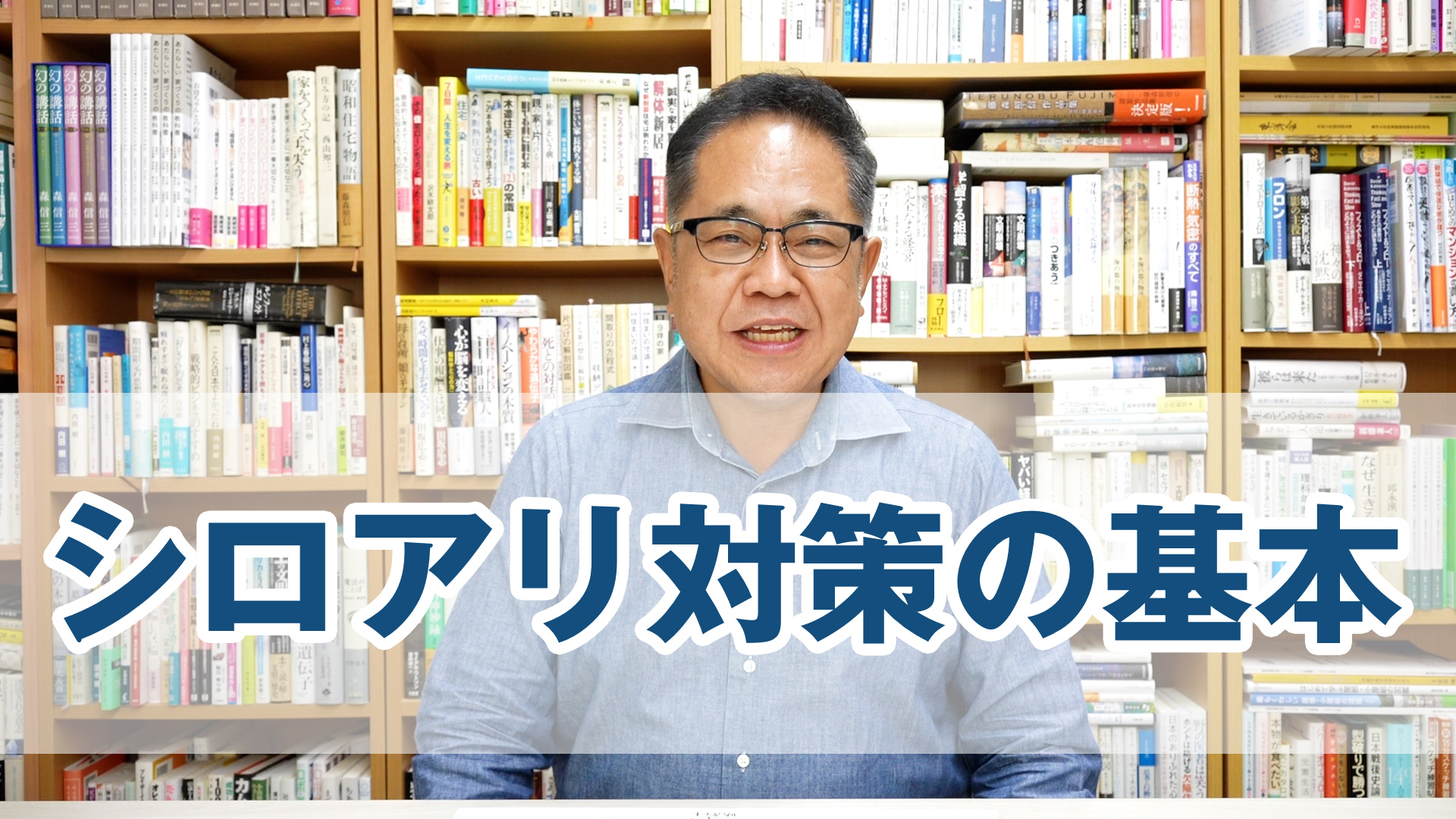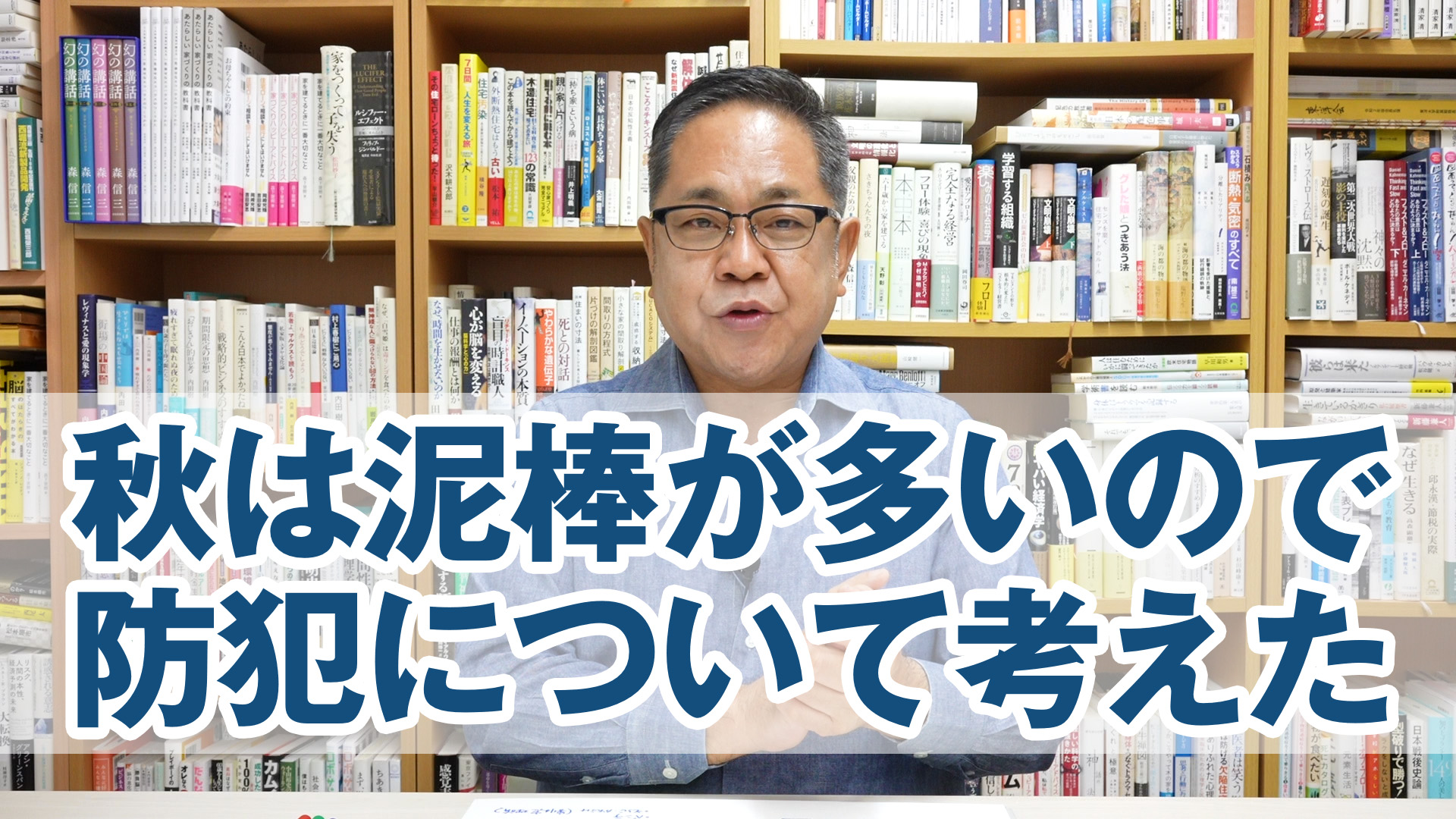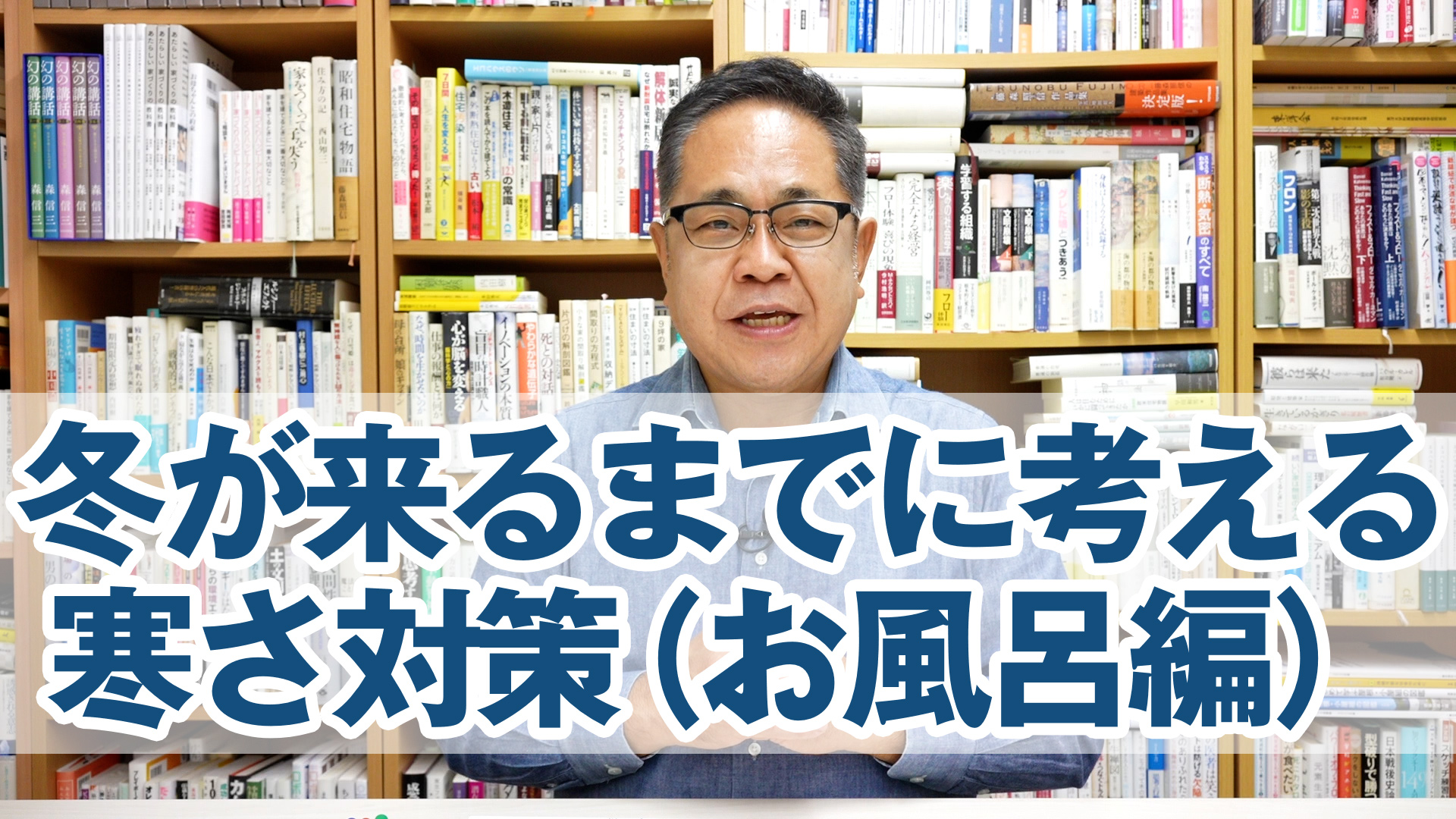夜干し家族にオススメ! 間取りのコツと仕様
今回は洗濯物を夜に干す方、いわゆる夜干しをされるご家族に向けて、間取りをつくる上でのコツや仕様について解説していきたいと思います。みなさんは洗濯って朝にされますか?それとも夜ですか?昼間は外に出られている方が多いと思うので、あまり昼に洗濯するというのは少ないかもしれませんね。では、いつものように僕の板書を見ていただきながら話を聞いていただけたらと思います。昭和から平成の前半ぐらいまでは、世の中はまだまだ朝干しが中心だったと思うんですが、平成の後半から現在にかけては、夜干しがすごく増えてきて、むしろスタンダードになっているんじゃないかなと思うんです。じゃあ一体なぜそうなったのかを考えてみると、合理的な理由がちゃんとあるんです。
1つ目は共働きの家族が増えて、それが標準的になったということ。昭和の頃は亭主が働きに出て奥さんが主婦で家を守る、というのが多かったんですけど、今は男女ともに働いて協力しながら家事もこなしていく時代ですよね。そうすると「いかに家事を楽に、合理的にできるか」という機運が家庭の中で高まってきた。それが夜干しという行動につながった大きな理由なんじゃないかなと思います。そして2つ目は、外干しに対するリスクが高まってきたという社会的背景です。僕の母は昭和のおばあちゃんタイプで「外に干したい、太陽に当てたい、風に晒したい」という人なんですが、今は花粉症が本当に深刻ですよね。家族4人中3人が花粉症、なんていうのも珍しくない。そう考えると花粉が飛ぶ季節は外干しを控えようというご家庭も多いですし、スギやヒノキだけじゃなく、ブタクサやイネ科など年中花粉が飛んでいますから、外干しは厳しい。さらに中国からの黄砂やPM2.5といった細かい汚染物質も飛んできて、外に干しているとむしろ汚れてしまう、なんてことにもなりかねない。加えて共働きの方からは「外に干していると天気が気になってドキドキする。雨が降ったらどうしよう、風が強くなったら大丈夫かな」というストレスを感じるという声もよく聞きます。だから夜干し、つまり室内干しというのが一つのスタンダードになってきたんです。
洗濯という行為は「洗う・干す・取り込む・畳む・しまう」という流れがありますけど、その最初の「洗う」という起点を一日のどのタイミングに持ってくるか、これは共働きで子育て中のご家庭にとっては大きな悩みどころなんです。特に朝は戦争みたいに忙しい。子どもを起こしてご飯を食べさせ、着替えさせて送り出す。それだけでも大変なのに、お母さんは身支度をして、お父さんはパンをくわえながら子どもを保育園に送っていく、ゴミも出して…という具合に、とにかくバタバタしてますよね。だから「朝に洗濯は勘弁してほしい」という気持ちになるわけです。そうなると洗濯にまつわる動作をいかにコンパクトに、合理的にできるか。そのためには動線を短くする工夫が大事になってきます。
では夜干し・室内干しに特化した間取りを考えるとどうなるか。多くの方が希望されるのは「ランドリールーム」という専用の空間です。南側にサンルームのように設ける方もいれば、居室を優先して北や東、西にランドリールームを設ける方もいます。そこには洗濯機や乾燥機を置き、物干しのフックや昇降式の物干し竿を設けたり、乾いた衣類をすぐ収納できるスペースをつくったり。取り込んだ洗濯物を畳んだりアイロンをかけたりできる台を置くのも便利です。こうしたランドリールームは、共働きで忙しいご家庭にとって本当にありがたい空間になるんです。ただし、メリットばかりではありません。まず専用スペースを確保すると床面積が増えるので、リビングやキッチンとの兼ね合いで家が少し大きくなってしまう。そして生活の中心であるリビングから少し離れる場合、洗濯物の乾き具合をちょこちょこ見に行かないといけない。それから多くの人が心配するのは「室内干しはジメジメして生乾きになって臭うのでは?」ということです。
でも実はこれにはきちんと答えがあります。つまり、ただ干すだけではダメなんです。ランドリールームに換気扇や除湿器、サーキュレーターなどを併用することがポイント。例えば6kgの洗濯物を2月や3月といった乾きにくい季節に干した場合でも、換気扇+除湿器を使えば8時間で乾くというデータがあります。これは朝日化成さんの研究所が発表しているもので、多くの実務者が参考にしています。換気扇+ファンだけでも14時間あれば乾くので、夜10時に干せば翌朝には乾いている、もしくは昼までには乾くという計算です。つまり、太陽に当てなければ乾かないというのは一種の先入観かもしれないんです。さらに小型のエアコンを設置すれば、冬は暖房で、夏は除湿でさらに快適に乾かせる。除湿器よりエアコンの方が強力に湿気を取ってくれますから、とてもおすすめです。
ランドリールームの位置については、リビングダイニングに隣接させて、間仕切りや収納を兼ねたスペースに干すという方法もあります。そうすると夜に干して乾いていなかったら、朝に建具を開けてLDKとつなげることで風や空調を活かして効率的に乾かせる。さらにその隣に収納を設けて、乾いたらすぐ片付けられるようにするのも便利です。また、2階ホールや階段上の空間を活用する方法もあります。ホールや吹き抜けに干すと邪魔にならず、空調の風も当たりやすいので乾きやすい。僕の友人の小暮さんは、吹き抜け部分をすのこ状にして物干しスペースにしていて、加湿にもなって一石二鳥だと言っています。さらにお風呂や洗濯スペースを2階に設ければ、干す・片付けるという動線もとてもスムーズですし、各個室に収納をつくれば、それぞれの部屋に片付ける習慣も身につけられる。そうすると家族全員で協力できる家事スタイルが自然にできてくるんじゃないかなと思います。
まとめると、室内干しをする場合は「換気扇や除湿器などの設備をどう置くか」が非常に重要で、それによって使い勝手や快適さが大きく変わります。夜干しをするご家庭は多いですし、ぜひ間取りを考える段階で、このランドリースペースや室内干しの工夫を取り入れていただけたらと思います。