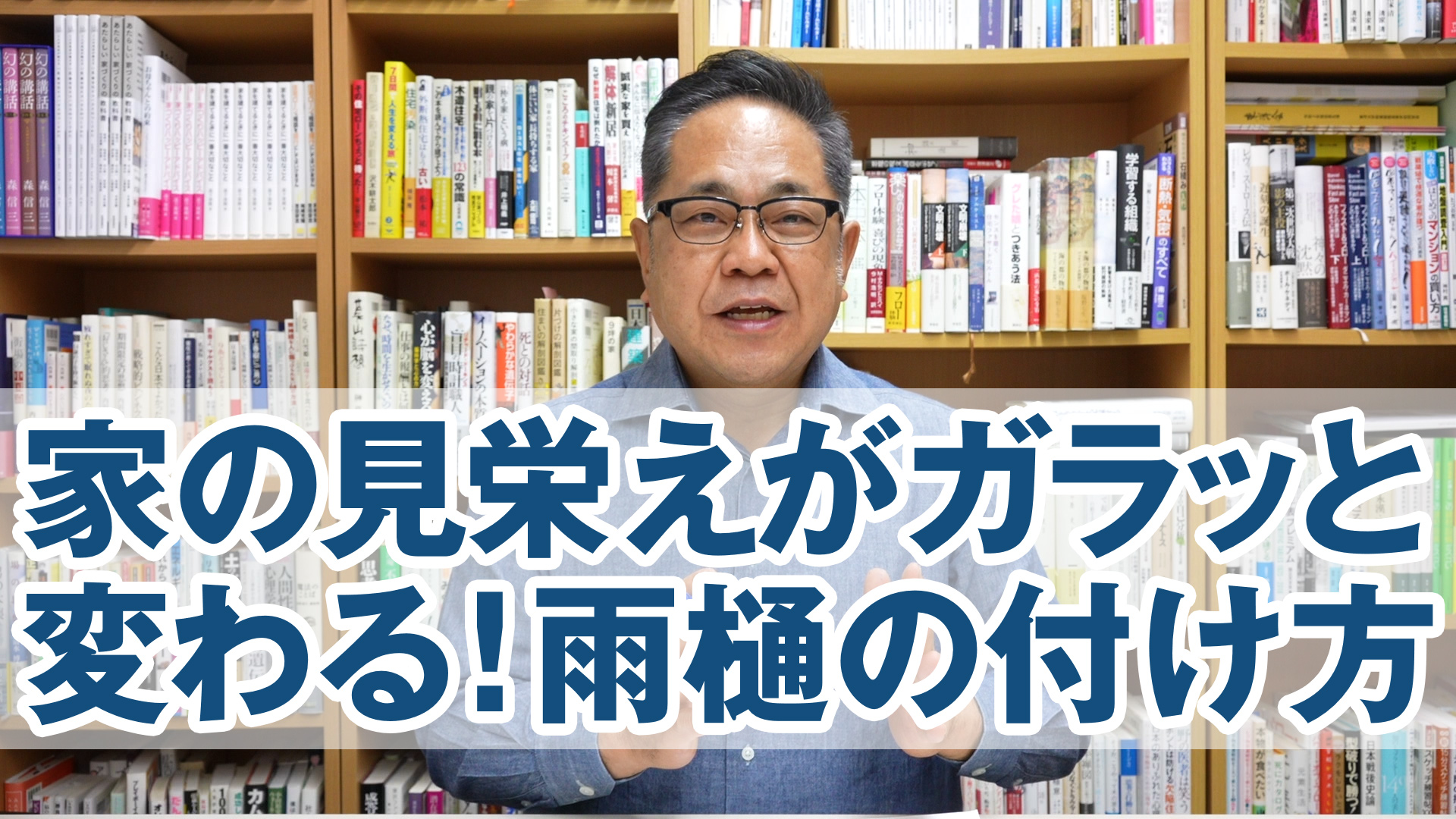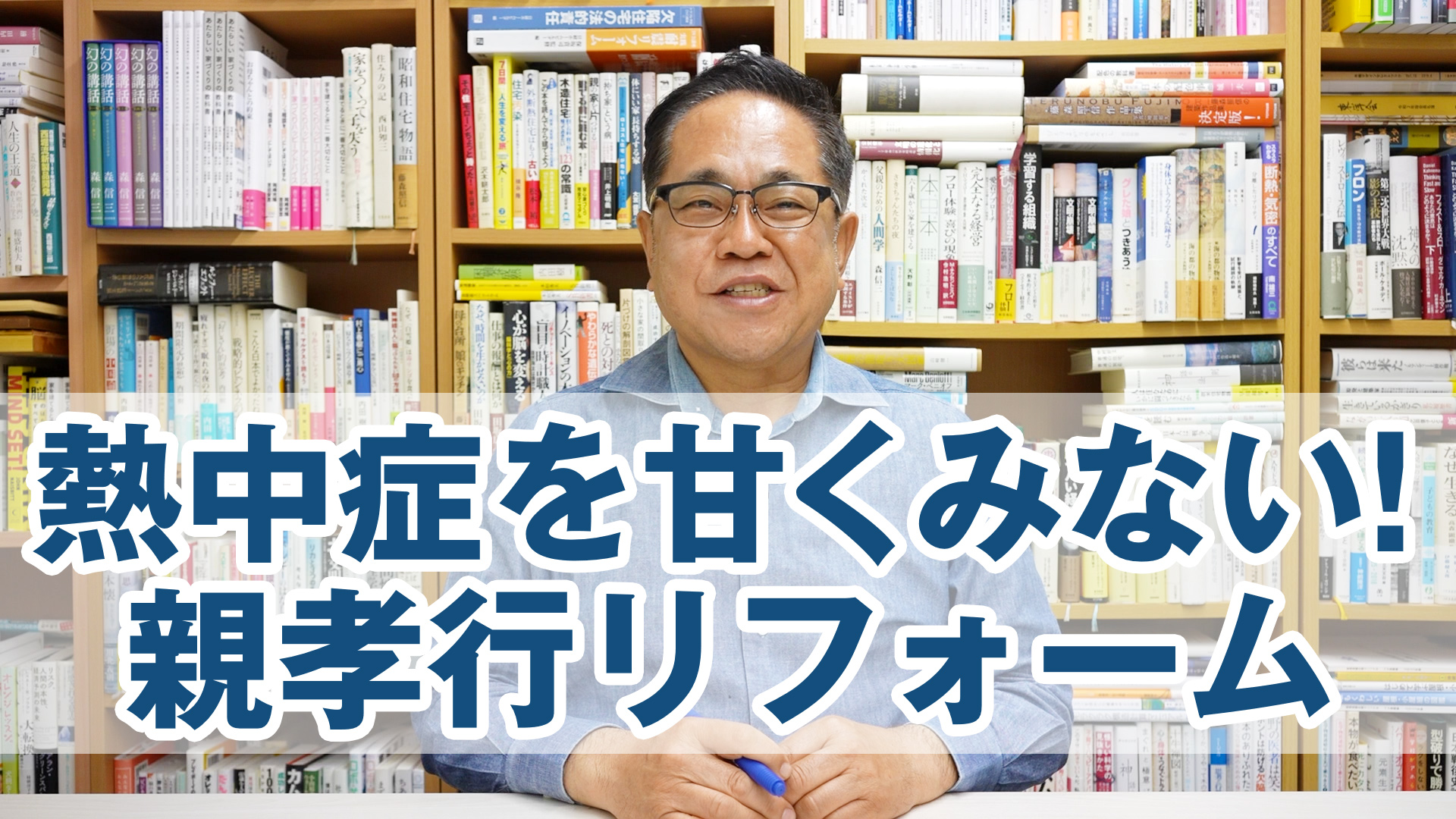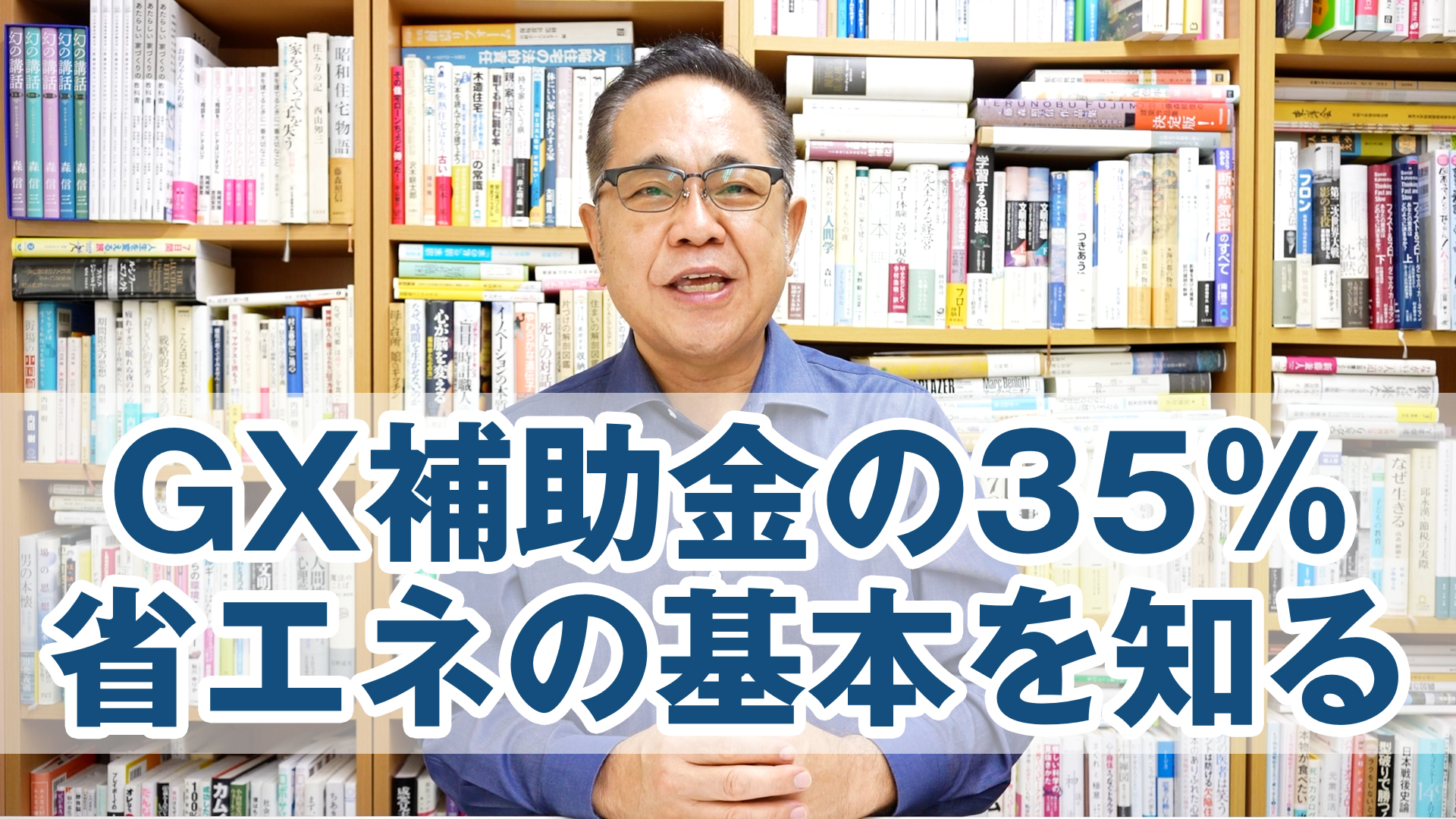これからの日本の家づくり必須:夏の高湿化への対策の基本
やっぱり梅雨時って、どうしても湿気が気になりますよね。これからの日本は本当に高温多湿になっていくと言われていて、そうなると、これにどう対処するかがすごく大事なポイントになってきます。今回も、前回の動画に引き続き「新建ハウジング」さんという、僕たちプロが読んでいる新聞があるんですけど、その6月10日号で松尾先生がとても重要なことを解説されていたので、僕なりの言葉で、今回は特に大事な部分をお伝えできたらと思っています。いつものように、僕の板書を見ながら聞いてもらえたら嬉しいです。
まず、この記事の前段として、松尾先生が湿度に関して「この数値がポイントですよ」とおっしゃっている部分があるんです。温度のことについては、みなさん「冬は何度以下だと寒い」とか「夏は何度くらい」とよく言いますけど、湿度について「こうしたらいい」って具体的に言える方って、意外と少ないんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうか。松尾先生がおっしゃるには、夏については「絶対湿度」が大事だと。よく「何パーセント」と耳にするのは「相対湿度」なんですけど、この相対湿度というのは、文字通り相対的に意味が変わってくるので、あまり本質的ではないんです。そこで、もう少し厳格に管理しやすい「絶対湿度」という考え方があって、この絶対湿度については、僕の別の動画でも詳しく解説していますし、もし分からない方はネットで調べていただいたり、その動画を見てもらえたらと思います。
▼湿度コントロールで快適にすごす(夏期編)
https://www.m-athome.co.jp/movie/shitsudo_control_kaiteki
この絶対湿度を基準に考えると、1立方メートル、つまり1メートル四方の空間に含まれる水蒸気の量が16gを超えたら、除湿してくださいと松尾先生は言っています。つまり、16gを超えると多くの人が「ジメジメしている」と感じやすいということなんですね。中には「13gぐらいがいい」と言う方もいるんですけど、これは空気1kgあたり13.3gという意味で、でもkg単位だと分かりにくいと思いますので、立米(りゅうべい)=立方メートル単位でお話しします。ですので、「1立米あたり16gの水分量になったら除湿が必要」、これがまず1つの目安です。
もう1つ、冬は逆に1立米あたり8gを下回ったら、それは乾燥しすぎているから加湿が必要です。なんとなく肌が乾くなあとか、風邪をひきやすくなるなあと感じた時は、だいたい8gを切っていると言われています。ですから、「8gを下回らないように加湿しましょう」というのが、快適・健康に暮らすための大前提なんです。この2つの数字、まず頭に入れておいてもらえたらと思います。
さて、そうした基準をもとに、今の日本の高温多湿化がどんな状況なのかというと、例えば昨年8月の東京では、平均の絶対湿度が空気1kgあたりで18.4gだったそうです。ちょっと分かりにくいので、これを立米あたりに換算すると、空気1立米はだいたい1.2kgですから、1立米あたりにするとなんと平均で21.6gもあったんです。そりゃあジメジメしますよね。だって松尾先生が「16gを超えたら除湿してください」と言っているのに、21.6gってだいぶ上をいっています。だから日本の夏が不快なのは、温度が高いことに加えて湿度もこれだけ高いからで、もし湿度が低ければ、例えばハワイみたいにカラッとして感じるはずなんです。でも日本は違う、湿度が多い。しかもこれは東京だけじゃなくて、だいたい全国6地域、どこも同じような傾向です。
この前提を踏まえて、例えば最近多い床面積100平米、いわゆる30坪くらいの住宅を例にすると、その家の空間容量は天井高2.4mで計算して、ざっと240立米くらいになります。今の法律で24時間換気が義務付けられていて、1時間あたり0.5回の空気の入れ替えが必要なんです。第三種換気の場合、1時間に120立米の空気を外に捨てて、外からも120立米入ってくる計算です。単純に考えると、この240立米のお家が「まあまあ涼しいな」と感じるには、立米あたりの絶対湿度を15.6gぐらいにしている状態です。じゃないと涼しく感じませんからね。
この状態の家の中に、立米あたり15.6gの湿気が240立米分あるわけですから、1軒の家には今3,744g、つまり3.7Lぐらいの水蒸気が含まれている計算になります。ペットボトル2本分くらいの水蒸気が家の中にあるんですね。そのうち半分の1,872gが外に出て、逆に外からは今21.6g×120立米分で2,592gの水蒸気が入ってきます。つまり、3,744gあった家の中の水蒸気が、1時間ごとに1,872g出て2,592g入ってくるので、結果的に4,464gになるんです。そうすると、1時間ごとに720gの湿気が絶えず増え続けている、これが今の日本の夏の現実です。
「720gも増えてるの?」と思うかもしれませんが、さらに4人家族が普通に暮らしていると、人間の体からも水分が出ますし、料理をしたりお風呂に入ったりもします。だいたい1日で4人家族が10Lぐらいの水分を出すと言われています。梅雨時には洗濯物も部屋干しすることが多いですよね。洗濯物10kgの半分、つまり5Lぐらいは水分として室内に出ますから、ひどい時は1日15Lぐらい水分が室内に供給されているんです。そうすると1時間あたりで換算すると、0.625Lの水分が人間の暮らしから発生している計算です。
つまり、24時間換気とエアコンを使っても、毎時720gの外から入る湿気と625gの生活由来の湿気、合わせて1,345g、つまり約1.35Lの湿気が1時間ごとに増え続けている、というのが今の住宅の状況なんですね。これはなかなかすごい量ですよね。ここまで第三種換気での話をしてきましたが、これを全熱交換型の一種換気扇にした場合どうなるかというと、外から入ってくる水分をだいたい半分ぐらい取り除けると言われています。これを「潜熱交換率」と言ったりして、カタログ上は70%とか80%と書いてあるものもありますが、実際はもっと厳しく見て50%ぐらいが現実的かなと思います。
仮に一種換気で考えると、換気量120立米、外の絶対湿度21.6gから室内の15.6gを引いた差分、その半分、つまり約360gが1時間あたり一種換気を使うことで減らせる計算になります。360gというと、だいたいコーラ1缶分ぐらいですよね。これが毎時間抑えられるということは、一種換気は結構大事なんじゃないかな、と松尾先生はおっしゃっています。これから家を建てる方には、本当にこれは必須じゃないかという提案です。
これまで一種換気というのは、どちらかというと冬の寒さ対策で重視されてきました。寒いところ、例えば北海道や長野のような地域では、暖房した熱を外に逃がさないために熱交換型の一種換気が必要だと言われてきたんです。でも温暖な西日本のような6地域では、「三種でも十分じゃないか、ロスで考えたら…」という意見もあったんですが、これだけ高温多湿になってくると、冬だけでなく、夏の湿気対策という視点からも、一種換気の効用がすごく重要になってきたと、松尾先生はこの記事で伝えてくれています。
「でも森下さん、エアコンをしっかり動かしておけば、ある程度大丈夫なんじゃないの?」とよく言われますし、僕も5~6年前まではそう思っていた部分もあります。ただ、ここ2~3年で増えているのは、エアコンが結構壊れるという現象なんですね。なぜかというと、エアコンは今、ものすごく過酷な環境で動かされています。湿気が多いので除湿量も多くなり、ずっと除湿し続けなければいけない。その分カビも発生しやすくなりますし、エアコン内部のフィルターを通過して、細かいホコリやPM2.5のようなものも中に入って、機械内部がカビや汚れ、湿気で傷みやすくなっています。その結果、エアコンが壊れやすくなっているということもあるんです。
ですので、これからはエアコンの負担も減らしてあげないといけないなと思うんです。この、毎時1,345gも増える水分をさらにエアコンで処理するとなると、エアコンの負担が大きすぎるんじゃないかなと、松尾先生も指摘されています。
ここで、ちょっとこの表を見ていただきたいんですけど、例えばコンプレッサー式の除湿器だと、1時間あたり416g除湿できます。デシカント式だと145g、ハイブリッドで383g、最近人気のダイキンの「カライエ」だと417gと、1時間でそれだけ除湿してくれます。なかなか優秀ですよね。ただ、消費電力という視点で見ていくと、エアコンは1,296gも除湿できてすごいんですが、750Wという電力を使います。効率で言うと、コンプレッサー式が1.43倍、エアコンが1.7倍と、エアコンと除湿器を組み合わせて除湿するというやり方もありますが、コンプレッサー式の除湿器は水が溜まったら捨てなければいけないという手間があります。排水型もありますが、多くは後から買い足すので、排水処理は面倒になりがちです。その点、ダイキンのカライエはドレンで排水できるので、そのあたりは便利ですよね。
そして、一種換気がどれくらい除湿できるかというと、計算上最大で710gくらい除湿に貢献できます。しかも、ただの換気扇ですから、消費電力は30W程度。エネルギー効率で言えば、24倍も除湿できるということになってきます。こうやって見ると、熱交換型の一種換気とエアコンを組み合わせるのは、かなり合理的なんじゃないかと思います。
これからの日本は、より強力な除湿が必要になってきますし、カビやホコリの問題でエアコンへの負担も増してきます。そう考えたとき、一種換気を改めて見直すことはとても大事な提案なんじゃないかと、松尾先生は言ってくれています。ですので、これから家づくりを考えている方は、一種換気はちょっと高いかな…と思われるかもしれませんが、こういった利点もありますので、ぜひ1つ頭に置いておいてもらえたらいいんじゃないかなと思います。
こう話すと、「私たちは共働きで日中は家にいないから、三種換気でも十分じゃないの?湿気もそんなに入ってこないんじゃない?」というご意見もありますし、実際僕らもそういう運用方法を提案することもありました。ただ、年齢を重ねてシニア世代になると、家にいる時間が増えてきます。定年退職しても、次に働くとしても、昔のような働き方はしなくなりますよね。そうすると、家で長い時間を過ごすことになりますし、熱中症など健康面でのリスクも出てきます。だからこそ、長く快適に暮らすためにも、換気設備はとても大切なんです。そんな老婆心も込めて、これからの換気・空調計画を考えてみてほしいなと思います。命や快適さを守るためにも、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。