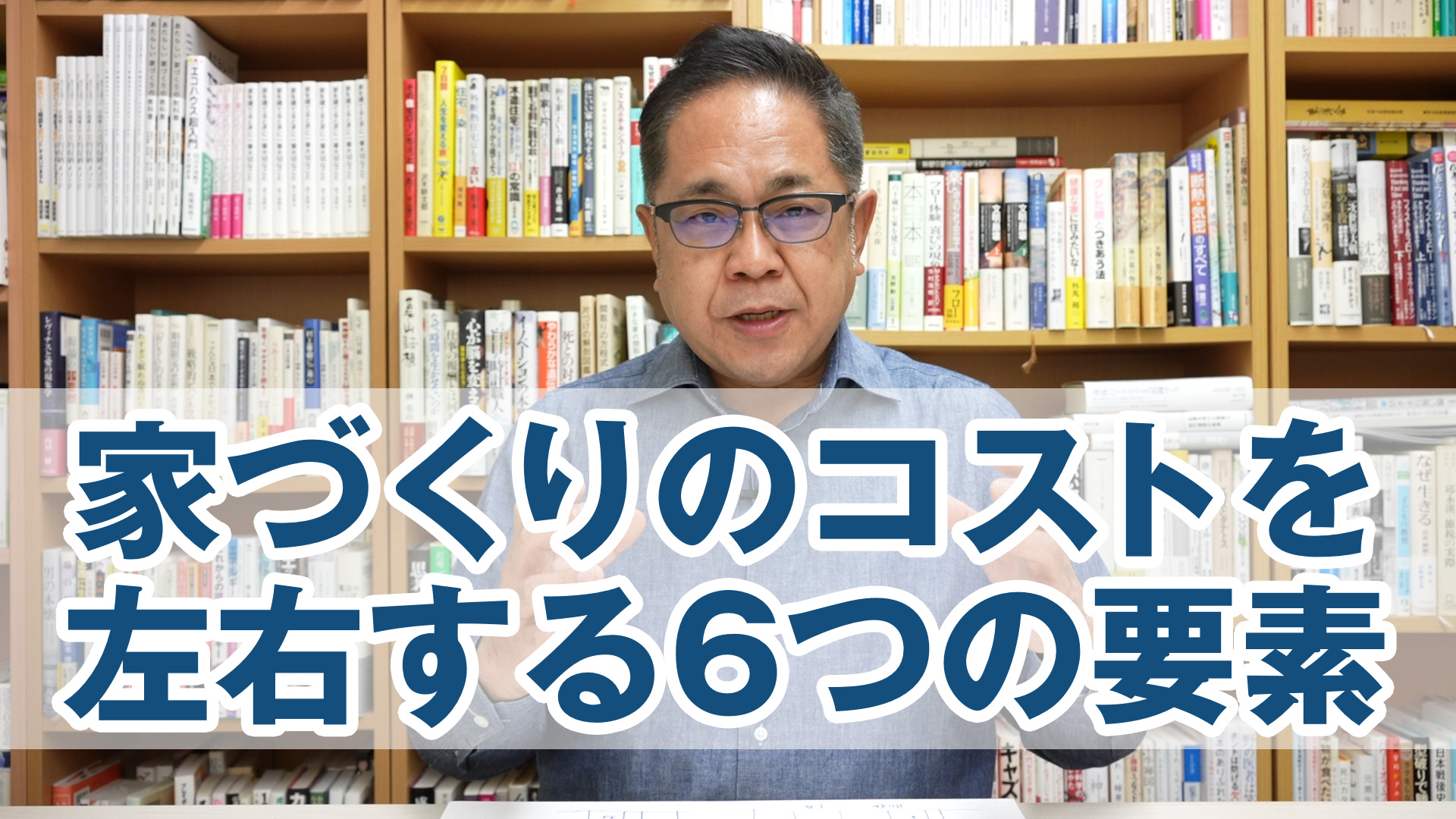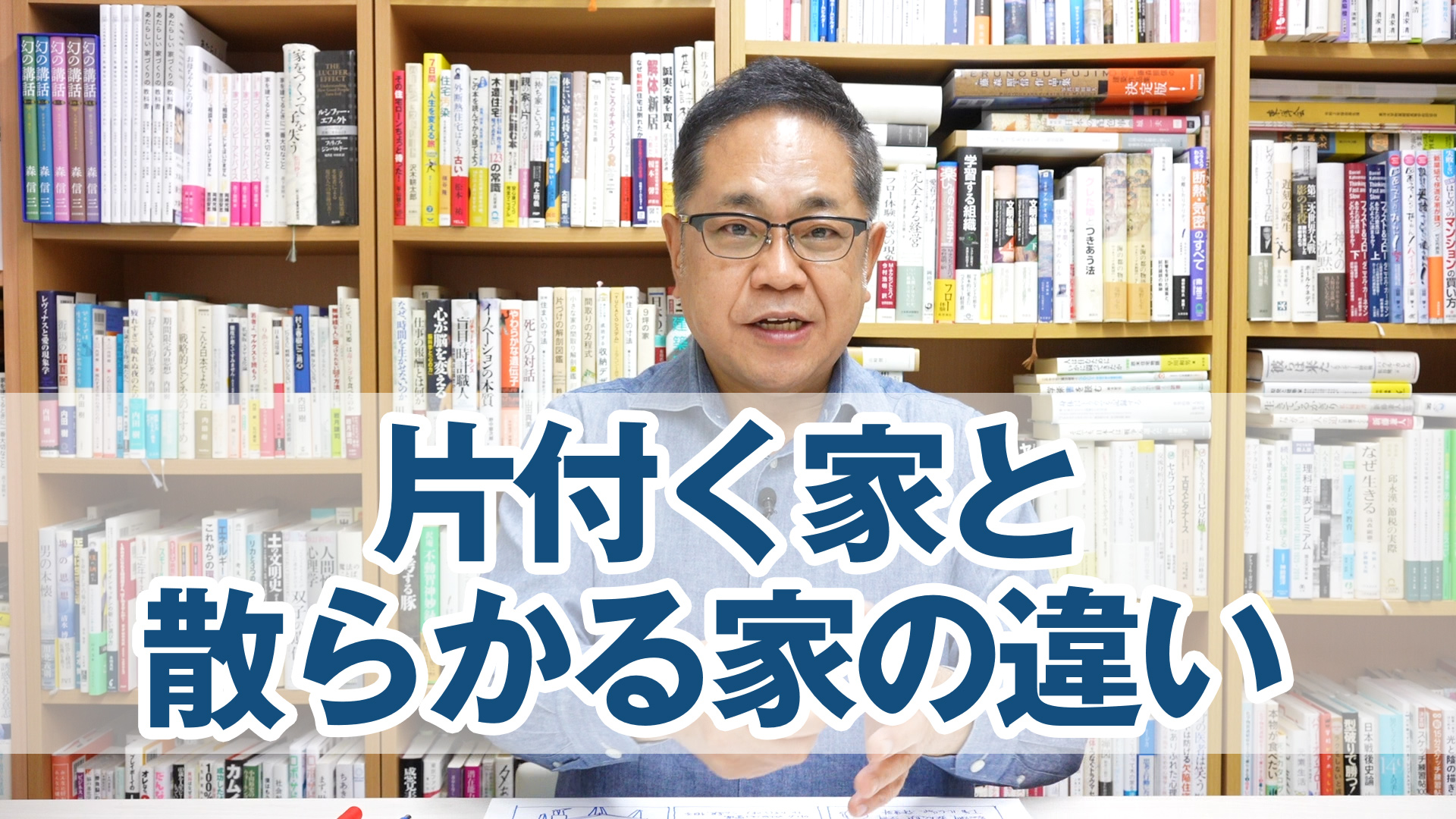2025年 注文住宅トレンド「スペパ・コスパ」について
今日は、先日ある若いお施主様から「森下さん、2025年の注文住宅は“スペパ”がキーワードみたいですけど、その辺はどんなふうにお考えなんですか?」と質問をいただいたんです。でも、正直に言うと私、「スペパ?」ってなってしまいまして…。なんかスパゲッティの品種か、メニューの名前かな、みたいな感覚で、スペパって?みたいな感じになってしまったんです。ほんまにストンキューな話で、「すみません、勉強不足です。ちょっとググらせてください…」みたいな流れからそのお客さんとの話が始まりました。きっと勉強熱心な皆さんからしたら「森下は何を言ってんねん」と笑っておられる方が多いと思うんですけど、中には僕みたいに「スペパ?」ってなる方もいらっしゃると思うので、今日は少し説明をしておきますね。
まず「コスパ」って有名ですよね。コストパフォーマンス、つまりかけたお金に対してどれだけの価値とか満足度が得られるか、いわゆるパフォーマンスのことを言います。最近は若い方の間で「タイパ」、タイムパフォーマンスという言葉もよく聞くようになりました。費やした時間に対してどれだけの満足度が得られるかという考え方です。僕もタイパくらいまでは何とかついていけたんですけど、「スペパってなんやねん?」ってなったんですね。調べてみると、これはスペースパフォーマンスの略で、簡単に言うと住空間において、限られた広さの中で効率的・効果的にどんな価値や満足度が得られるか、ということなんです。だから、コスパ・タイパに加えて、スペパを考えた家づくりをという流れが今あるんですね。マスコミの方が上手にそういう言葉を広めて、ブームをつくっている部分もあるんでしょうけど、よくよく聞くと「それはそうやな」と僕も思いました。
やっぱり背景には建築費用の高騰があります。今は本当に建築費が上がっているので、僕らも「コスパのいい小さな家を建てましょう」とよく言うんです。ただ、小さい家は当然スペースが限られるから、スペースパフォーマンスが高くないと住みにくい。これは当たり前の話なんですね。だから最近の企画住宅なんかも「小さな平屋」「30坪くらいの家」といったコンセプトが注目されていて、そこにスペパが大きなテーマとして入ってくるわけです。
じゃあ実際にスペパの高い家ってどんなものかというと、僕らも過去に「スペパ」という言葉こそ使っていませんが、似たような取り組みをやってきました。一つは省スペース。例えば玄関、戸建てだと1畳から2畳くらい取ることが多いですが、マンションでは75cm×40cmぐらいの本当にコンパクトな玄関も普通にありますよね。あるいは「いきなりリビング」。玄関を入ったらすぐ居室、すぐダイニング。12〜13年前に「育家事ハウス」というモデルハウスをつくった時も、玄関を入ったらすぐリビングという形でやらせてもらいました。当時としてはセンセーショナルでしたけど、「これはありですね」と言って採用された方も多くいらっしゃったんです。
最近では「お風呂キャンセル界隈」なんて言葉もあって、若い方の発想にはついていけない部分もありますけど、「湯船はいらないからシャワーだけでいい」という暮らし方を選ぶ人もいます。そうなると本来2畳ほど必要なバスルームが、90cm角のシャワールームだけで済む。これもスペパを高める工夫ですよね。
他にも辻井モデルハウスでは、玄関土間を拡張して遊べるスペース、自転車整備のスペース、草野球仲間で酒盛りできるようなスペースにしたこともありました。これは中途半端にせずに玄関を思い切って拡張することで、空間のパフォーマンスを上げる工夫だったと思います。それから、リビング・ダイニングの考え方も変わってきています。昔は大きなリビングと4人掛けダイニングが定番でしたが、今は家族がテレビの前に集まることも減って、ソファーひとつと小さなダイニングの方が暮らしに合っていたりします。結果的にリビングをコンパクトにしても、ダイニングで楽しい時間が過ごせる。これもスペパを高める考え方ですね。
さらに寝室や子ども部屋。布団を畳んで仕舞えば、そこは居室や遊び場になる。ベッドを常設しないだけで空間が有効に使えるわけです。また造作家具で壁面を余すところなく使ったり、水回りを一カ所にまとめて効率化したり。こうした工夫を重ねることで、僕らも知らず知らずのうちにスペパを意識した設計をしてきたんやなと感じます。
そして話が盛り上がって、僕が「日本は昔からスペパが高い家づくりをやってきたんですよ」と例に出したのが江戸時代の長屋です。4畳半ほどの部屋に家族が2人から5人ほど暮らしていました。玄関を開けるとすぐ土間、水がめがあって、かまどがあって、横におひつや米びつが並ぶ。物入れや柳行李も置いてあって、枕屏風で仕切って布団を敷いたら寝室になる。ご飯の時は膳を出してダイニング、片付けたらまた居間になる。まさにスペパの極致です。ただ、長屋にはお風呂やトイレはなく、銭湯や共同トイレを使っていたわけですが、住むための最小限の空間利用としては本当に合理的でした。
そこから昭和に入ると、ちゃぶ台なんかが登場します。食事の時は中心の家具、終わったら畳んで脇に置けば布団を敷ける。これもスペパの発想ですよね。屏風なんかも軽量で動かしやすくて、赤ちゃんを囲ったり、部屋を仕切ったりと実に多用途でした。こうして見てみると、日本の暮らしは昔からスペパの発想にあふれていたんです。
なので、今の注文住宅でも「コンパクトだから妥協する」のではなく、「コンパクトだからこそ粋を凝らす」と考えると楽しいと思います。スペパを意識してパフォーマンスで家づくりを考えたら、小さい家にたどり着くことは妥協ではなく、むしろゴールなんじゃないかなと。そんなふうに思いました。