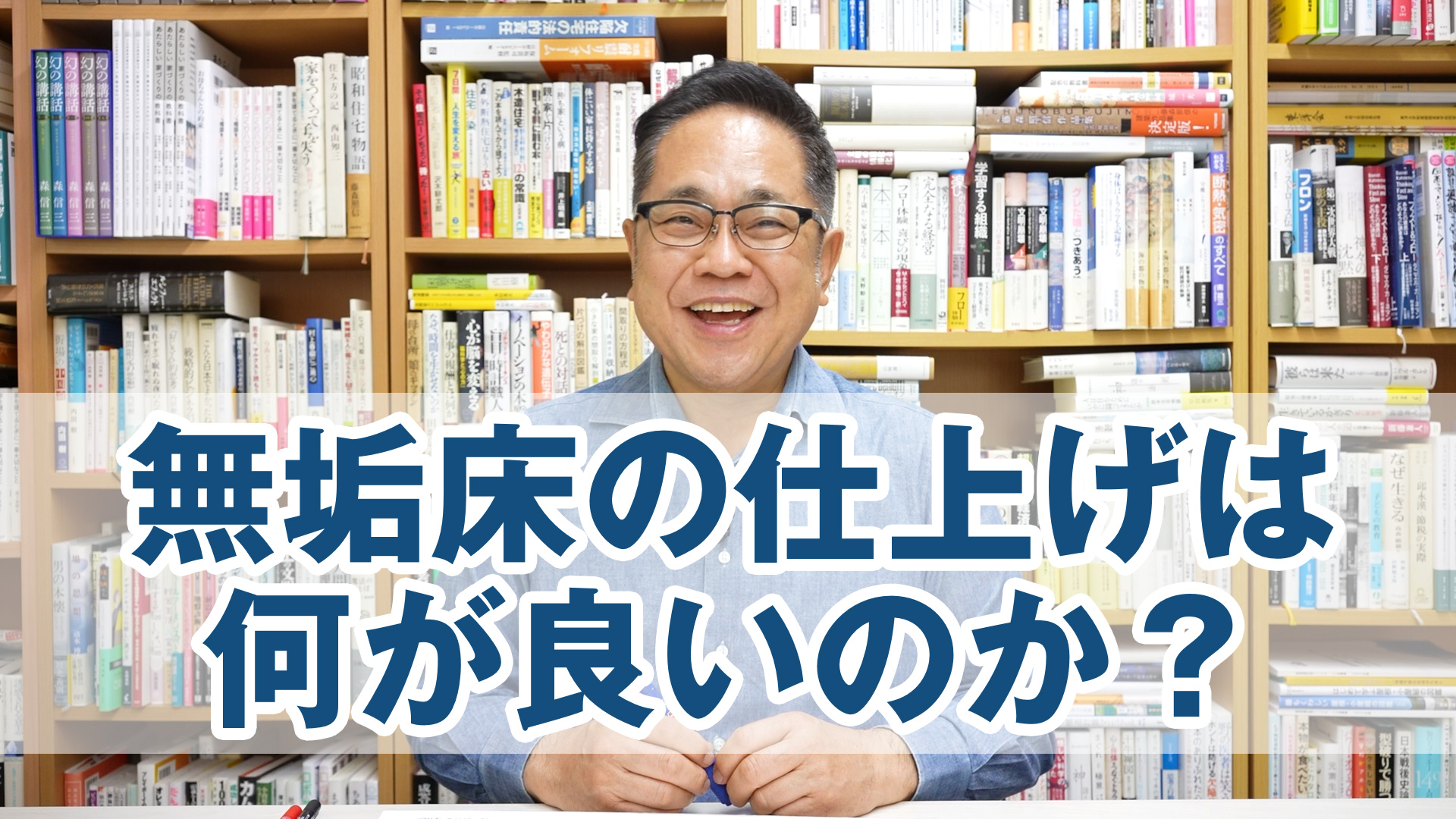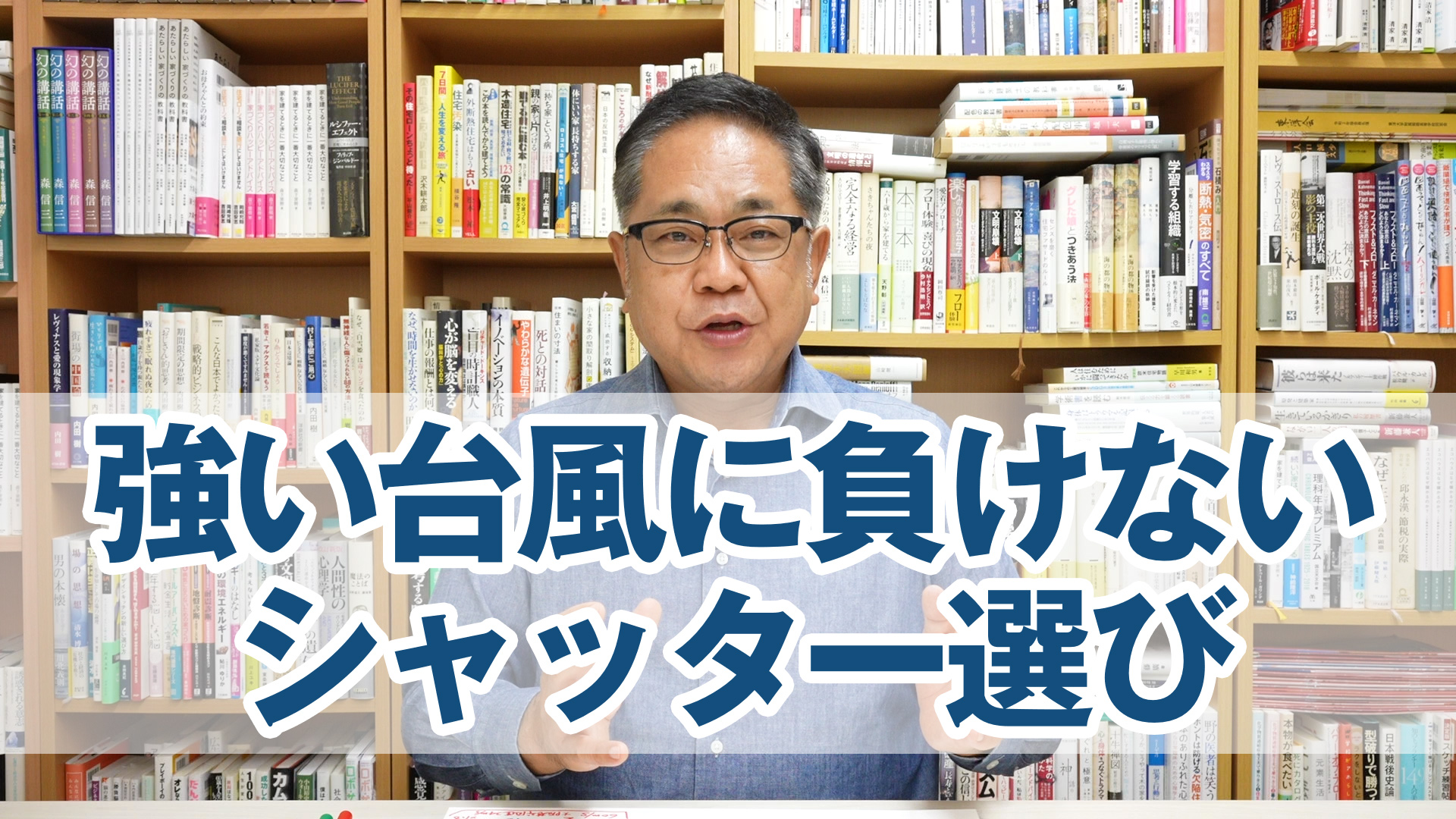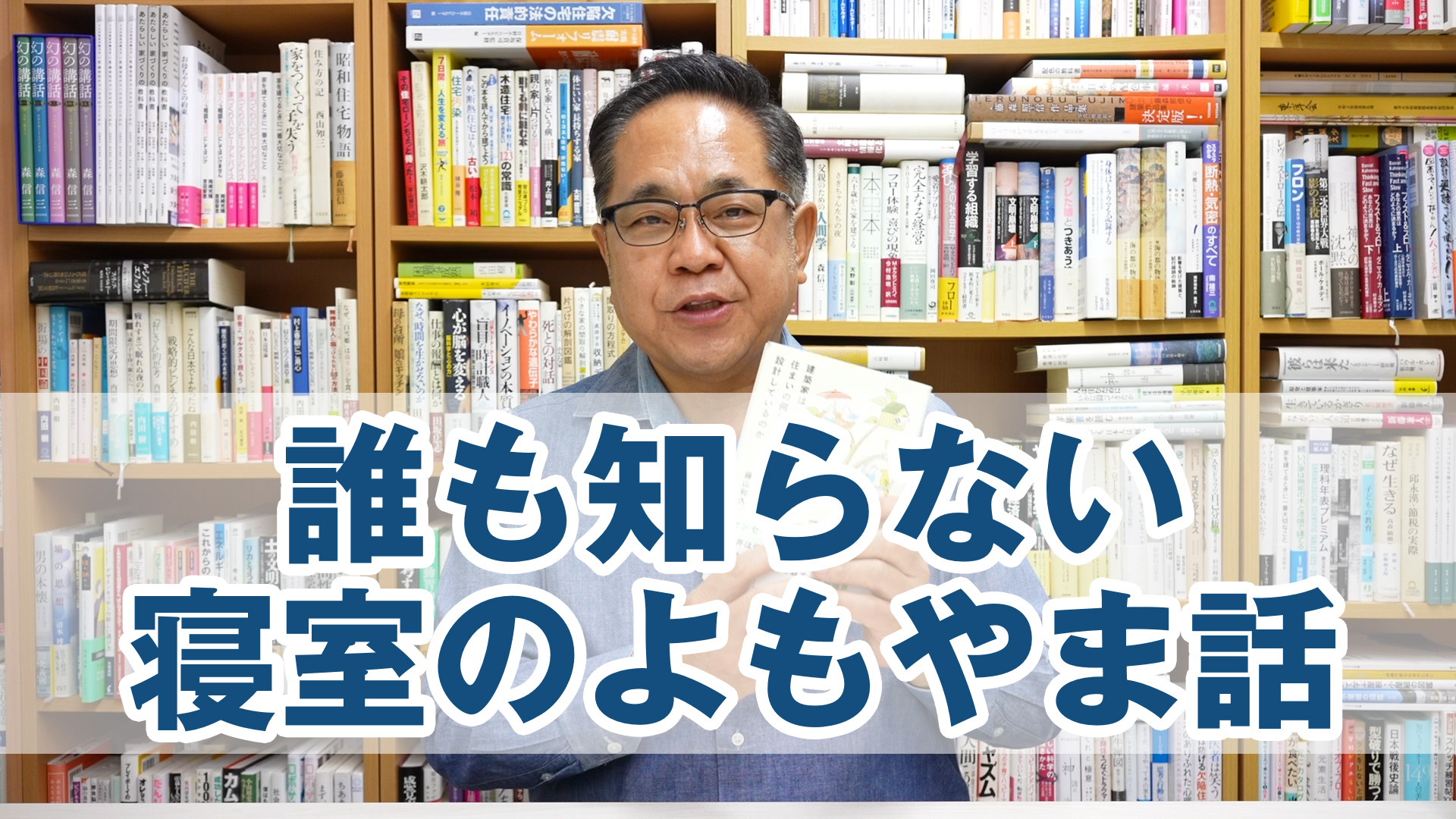【リプロダクション】石積みの美しさについて
今日はですね、少し古典的な話かもしれませんが、住宅をつくるときに必ずついてくる「庭」について、その中でも“石積み”、つまり石を使ったデザインの美しさについてお話ししたいと思います。今回の内容は『建築デザインの解剖図鑑』という本から少し引用させていただいておりますので、その点はあらかじめご了承ください。
さて、「なぜ今さら石積みなのか」というところなんですが、最近うちの山下社長が“リプロダクションコスト”という言葉をよく使うんです。建築の世界ではこれまで「イニシャルコスト」「ランニングコスト」「トータルコスト」といった考え方が一般的でしたが、それはあくまで“一世代分”の家の費用という意味なんですよね。でも、これからの家づくりというのは一世代で終わるものではなく、次の二世代・三世代と住み継いでいけるような、社会資源として価値あるものにしていくべきなんじゃないかと。そうすれば建築費用が高くても、複数の世代で負担すれば結果的に薄まりますし、より上質なものをつくることができる。リプロダクションとは「再生」という意味ですが、家も人生を終えてまた次の世代に引き継がれていく。たとえばイギリスなどでは築200年、300年の家が当たり前にありますよね。そういう“長く使われる家”を日本でもつくれたらいいなと。そうした考えの中で、長く使い続ける家の一要素として“石”という不変の素材を、もう一度見直してもらえたらと思うんです。
石垣や石積みに使う石には大きく分けて二つあります。ひとつは「野石(のいし)」といって、自然の中に転がっている石。川や山などから採れる自然石のことです。もうひとつは「樵石(きりいし)」といって、石切り場などで人の手によって切り出し、ある程度加工された石のこと。この二つが石積みの基本になります。野石の中でもさらに種類があって、「呉呂太石(ごろた)」というのは川の流れなどで角が取れて丸くなった石のこと。昔はおばあちゃんに「漬物の重しに使うからごろた石を拾ってきて」と言われて、河原で探したものです。そういう石を家づくりに使うのも、自然の優しさがあっていいですよね。もう少し小さくて粒がそろったものは「玉石」と呼びます。それに対して山から転がり落ちてくるような角ばった石は「野角(のかく)」、層をなすように薄く割れる板状の石は「野板(のいた)」といって、それぞれに表情があります。
一方で樵石の代表は「切石(きりいし)」です。レンガのように整った形で扱いやすい石ですね。それに対して「野面石(のづらいし)」は、樵石の中でも粗めに仕上げたもの。こうした石を使って石垣を積んでいくわけです。積み方にも種類があって、「整層積み」と「乱層積み」があります。整層積みは石を水平にきれいにそろえて積む方法で、「布積み」や「通し積み」とも呼ばれます。一方の乱層積みは、石をランダムに積んでいくやり方。姫路城などを見ると、場所によって整層的な部分と乱層的な部分があって、積んだ時期や職人の違いによって表情が変わるのが面白いところです。
家づくりでも、こうした石の使い方をうまく取り入れると、ぐっと奥行きや重厚感が出てきます。全部に使えなくても、道路に面した一角だけに取り入れても十分存在感がありますよ。
たとえば代表的な景色として、「野石を乱層に積む」いわゆる銀閣寺の石垣があります。ランダムに見えて実はとても緻密に計算されていて、石工の職人が真剣に積んでいる。僕の叔父も石工で、姫路城の昭和の改修に参加して「どこかに自分の名前を刻んだ石があるんや」と話していたのを覚えています。そういう背景を知って銀閣寺を見に行くと、石垣や生垣、竹垣の美しさがまた違って見えると思います。
次に「玉石の谷積み」というのがあります。丸い石を横に並べていくと石と石の間に谷ができて、そこに次の層の石を逆向きに積んでいく。ジグザグに重ねる感じですね。これは一見やさしい印象ですが、実はとても手間がかかる。玉石や呉呂太石は自然が時間をかけて丸くした石なので、簡単に集められないし、そろえるのも大変。だからとても贅沢な石積みなんです。東京の高級住宅地の斜面などで、たまに見かけることがありますね。
そしてもう一つ、「乱石積み」。これは最も一般的で、和風にも洋風にも合う万能型です。積むときには「役石」と呼ばれる基準の大きめの石から始め、角に「隅石(すみいし)」を置いて全体を安定させていきます。熊本城の地震の時も、この隅石だけが残って城を支えていたのが印象的でした。石積みの技術って本当にすごいんです。西洋でも「キーストーン」といって、アーチの頂点に“鍵”となる石を入れることで全体を支えていますよね。あれと同じ発想です。
昔は田舎の人たちはみんな、田んぼの畦や水路の石積みを自分たちでやっていました。大工さんと石工さんの仕事が混じるような感じで、共同作業で地域の景観をつくっていたんです。でも今はコンクリートに取って代わられて、簡単になった反面、味わいはずいぶん失われました。コンクリートは50年周期で壊されて無に戻りますが、石はそうならない。だからこそ、これから長く美しく暮らす家づくりの中で、石をもう一度見直してもらいたいなと思います。
最近は「蛇篭(じゃかご)」、つまり石をワイヤーメッシュのかごに詰めた“ガビオン”というものも流行っていますね。僕もよく使いますが、2メートル近い高さで塀のように積んでいるのを見ると、ちょっと心配にもなります。メッキのワイヤーは20年も経つと錆びたり破損したりすることもありますし、植物のツルが巻きつくとさらに劣化を早めます。ですから、もしガビオンを使うなら高さは1メートル以下にして、石積みの一部として取り入れるくらいが安心かなと思います。
ということで、今日は“石積みの魅力”について少し掘り下げてみました。外構を考えるときのエッセンスとして、どこかに石を取り入れてみるのもいいと思います。