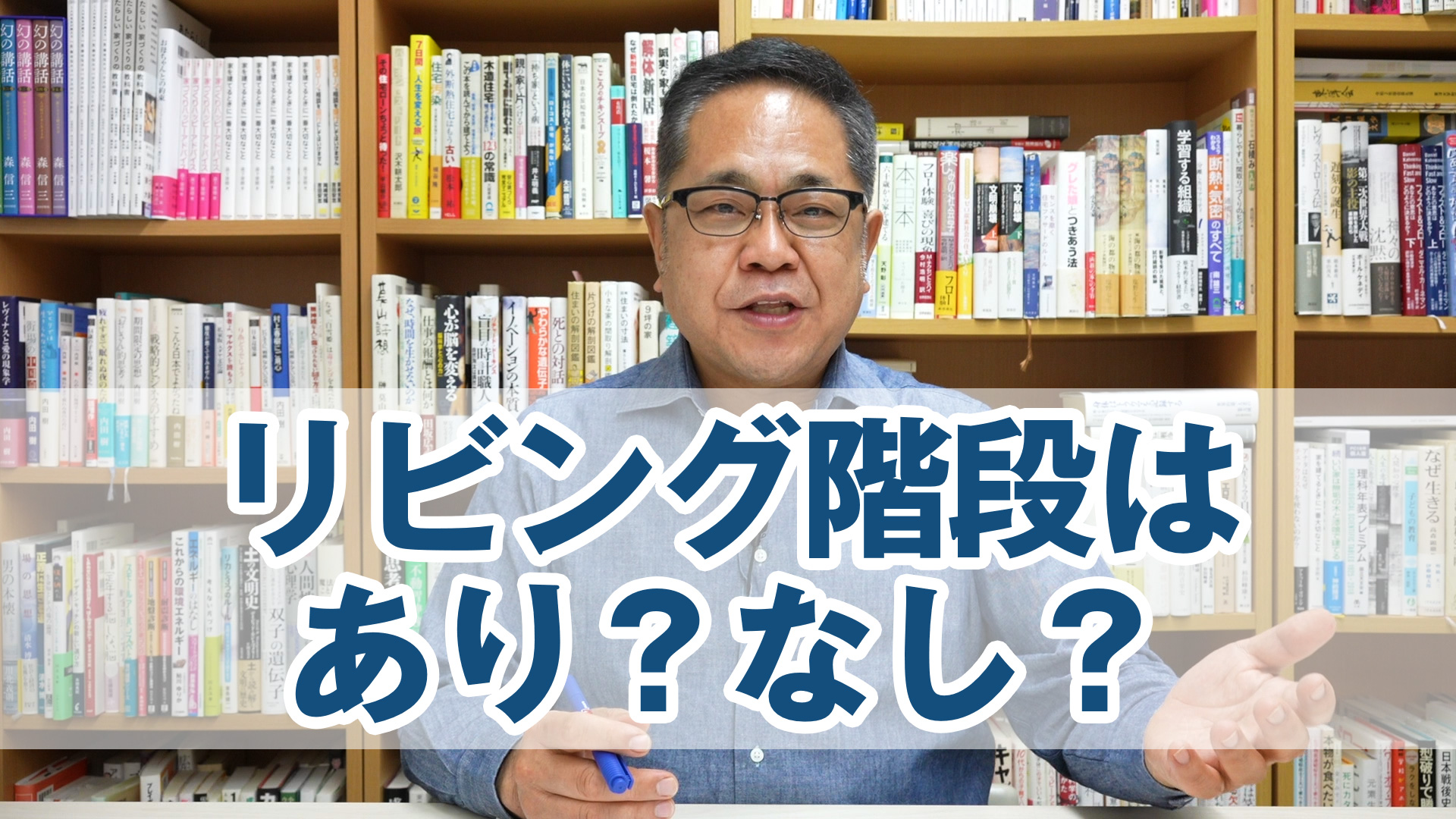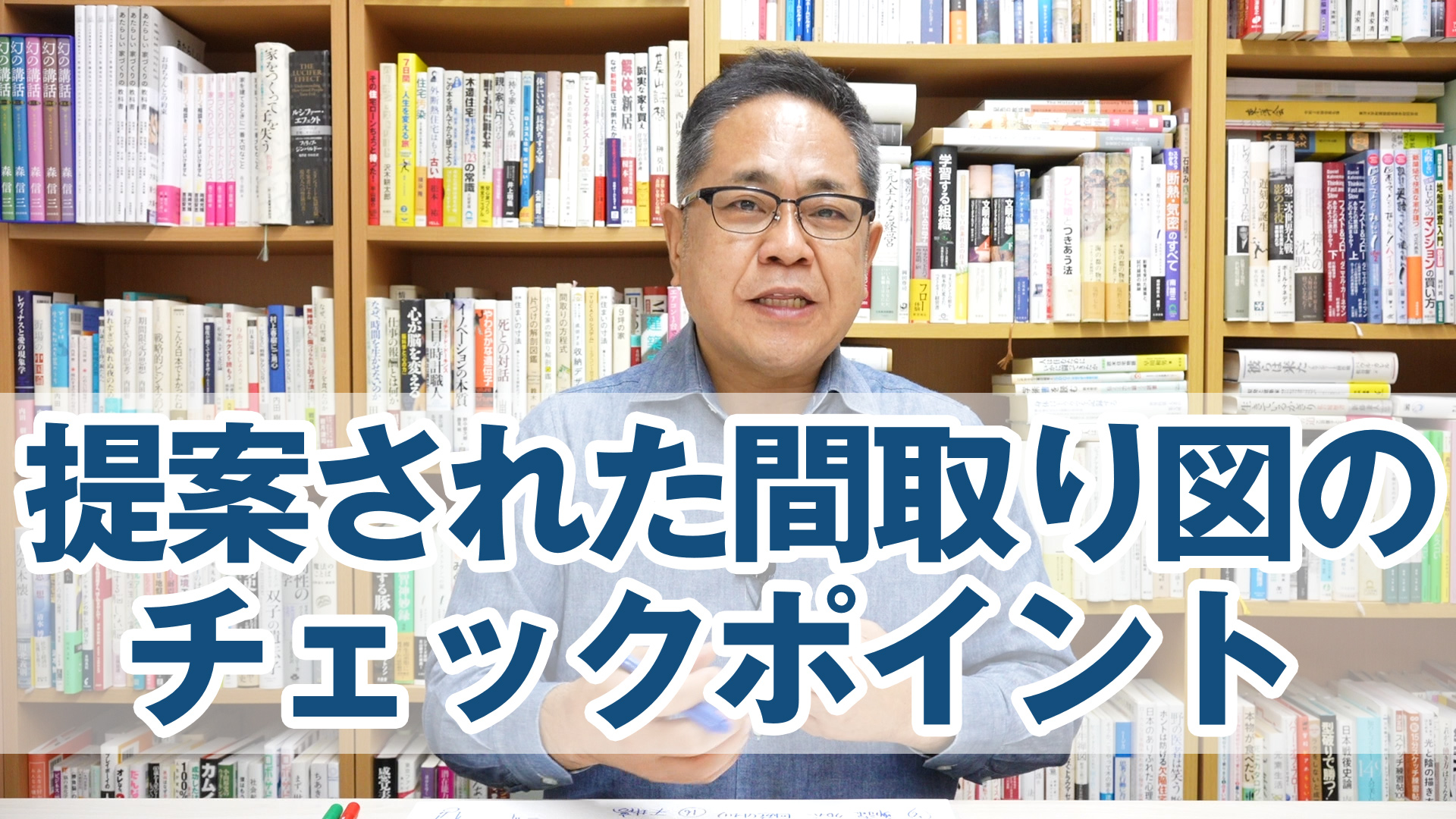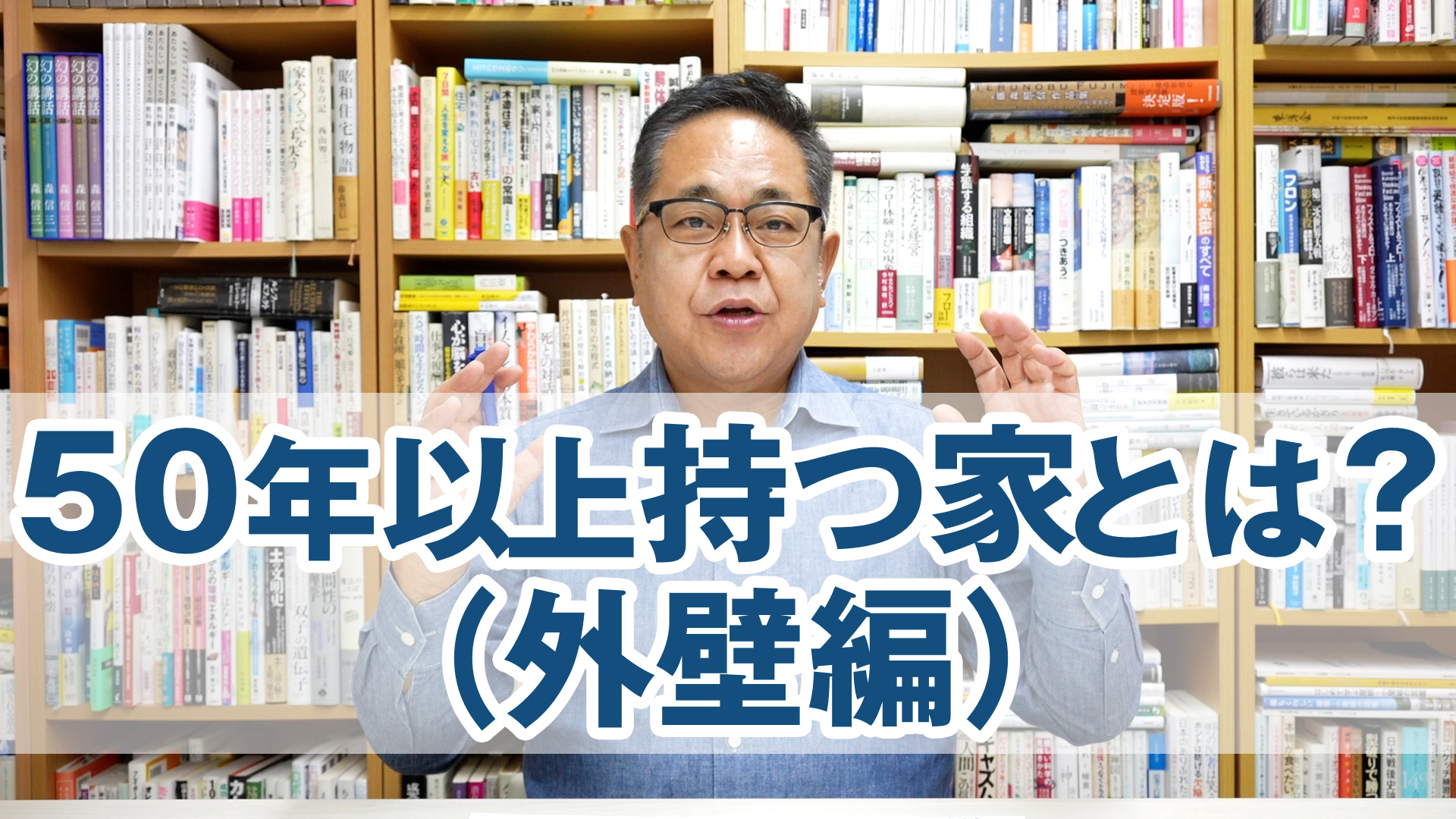「9坪の家」から「9坪の宿」になったスミレアオイハウスを訪ねて
今日は思わぬことから、以前動画でも紹介させてもらった「9坪の家」という小さなお家を、実際に見学するという幸運に恵まれまして、その訪問を経て感じたことを皆さんとシェアできたらと思ってお話させてもらいます。題しまして「9坪の家から9坪の宿になったスミレアオイハウスを訪ねて」というテーマで進めていきたいと思います。
僕、別の動画でも話しましたけど、私事ながらモリシタ・アット・ホームの社長を交代して、片腕だった山下くんにバトンを渡したんです。その交代が5月で、この6月に「建築好きジジイ」仲間たちが「節目やからお祝いしたろ。お前旅行一緒に行こう」と言ってくれて、イギリスやスペインに見たかった建物を巡る弾丸ツアーを計画してくれてたんですね。僕も楽しみにしてたんですが、その直前にうちの山下社長が「スミレアオイハウスを見に行く社内ツアーをやる」と。ところが日程を見ると、僕の旅行初日と丸かぶりだったんです。「えー、よしてくれへん?」ってかなり拗ねたんですけど、「会長は旅行に行ってください」と言われ、仕方なく受け入れてたんですね。
ところが当日の朝、旅行会社から「森下さんすみません、今日の飛行機飛びません」と一本のメール。代替便は翌日、つまり一日遅れで出発に。もう「なんどいやー!」って思いましたけど、仕方ないので「東京でおっさん同士で飲んで時間つぶすか」と思った時にふと、「ちょっと待てよ、スミレアオイハウスって三鷹市やん。今おるとこから近いやん」と気づいたんです。それで急遽、山下社長たちのツアーに合流しました。現場でみんな「え、来たんですか?」と驚いてましたけど、僕も念願叶って初めて実物を見学できました。
写真や文献で知ったつもりになっていましたが、やはり実物の持つ力は違います。もう本当に素敵な空間やなと感じ入りました。この動画をご覧のみなさんには、先に山下社長たちが訪ねた動画を見てもらってから、僕の話を聞いていただくと、より伝わりやすいと思います。今回の目論みは、念願が叶ってスミレアオイハウスを見学した僕の気づきや感激を、皆さんと共有することなんです。
▼スミレアオイハウスを見学してきました
https://www.m-athome.co.jp/movie/sumire_aoi_house
スミレアオイハウスというのは、萩原修さん・百合さんご夫妻が子育てのために建てられたお家です。もともと1952年に建築家・増田誠先生が自宅として建てた「最小限住宅」が原型にあり、それを1999年の「日本人と住まい博」で実寸再現した展示をきっかけに、修さんが感銘を受け、奥様に「家建てるぞ!」と宣言して実現したのが始まりなんです。家具デザイナーの小泉誠さんがリデザインを手掛けられ、細部のこだわりが随所に活きているのも実物を見て強く感じました。
名前の由来も素敵で、長女すみれさん、次女あおいさん、この二人の娘さんを大切に育てたいという願いから「スミレアオイハウス」と名づけられています。実は僕自身も娘が二人いまして、妻が冗談で「愛翔ハウス」って呼んでたこともあり、すごく感情移入してしまいました。すみれは可憐で愛される花、葵は誠実さを象徴する文字。そこに込められた願いに共感して、他人事に思えなかったんです。
9坪の1階に、2階は6坪、残り3坪は吹き抜けで、延べ15坪という小さなお家です。建てられた当時、修さん38歳、百合さん37歳、すみれちゃん9歳、あおいちゃん7歳。まさに子育て真っ只中のご家族でした。その後、この9坪の家の思想に影響を受けて「9坪ハウスプロジェクト」が全国に広がり、本も出版されるなど一大ムーブメントになりました。
そこから2019年、築20年を迎えたこの家を「9坪の宿」としてリフレッシュするプロジェクトが始まります。クラウドファンディングで資金を募り、再生した家は泊まれる宿となり、僕らのように予約すれば誰でも体験できるようになったんです。その案内をあおいさんご本人がしてくださったことも、とても印象的でした。
そして、山下社長が僕に「これからの家はリプロダクションコストが大事なんです」と言ったんです。最初意味がわからなかったんですが、再生・再新させて家を生かし続ける、そのためのコストという考え方なんですね。これを聞いたとき、本当に衝撃でした。家は建てて終わりじゃなく、手入れしながら生き返らせていく。その発想が未来を明るくするんやと改めて思いました。
▼リプロダクションコストについて考える
https://www.m-athome.co.jp/movie/reproduction_cost/
今回スミレアオイハウスを訪れて強く感じたのは、家族は期間限定であるということです。子どもはいずれ巣立ち、パートナーともいつか別れが来る。だからこそ、その時々の家族の形に寄り添う家が必要なんです。長寿命で高耐久の家を目指すのも大切やけど、実際には変化に合わせて手を入れ、再生していくことが現実的やと思います。
最後に、内田樹先生の『期間限定の思想』の一節を紹介しました。家族はテンポラリーなものであり、いずれ離散する。そのことを意識している方が、むしろ仲良く暮らせる、という内容です。僕もこのスミレアオイハウスを通じて改めてそのことを実感しました。
子どもは巣立ち、パートナーとも別れがあるかもしれない。そして家もまた寿命を迎える。でも、再生することで次の家族を支えることができる。そんなサイクルを受け入れて、家づくりに向き合うことが大切なんじゃないかと思いました。
最後に少し蛇足ですが、ぜひ体験してほしいのがあのはしごのような階段です。年を取ったら上がりにくいと思うでしょ?でも実際に踏んでみると、鳥が止まり木に止まるような感覚で、すごく安心感がありました。腰が痛い僕でも怖くなかったです。だから「これなら年を取っても住めるな」と思ったのも大きな発見でした。
そんなことも含めて、スミレアオイハウスには学びと気づきがたくさんあります。ぜひみなさんも機会があれば行ってみてください。