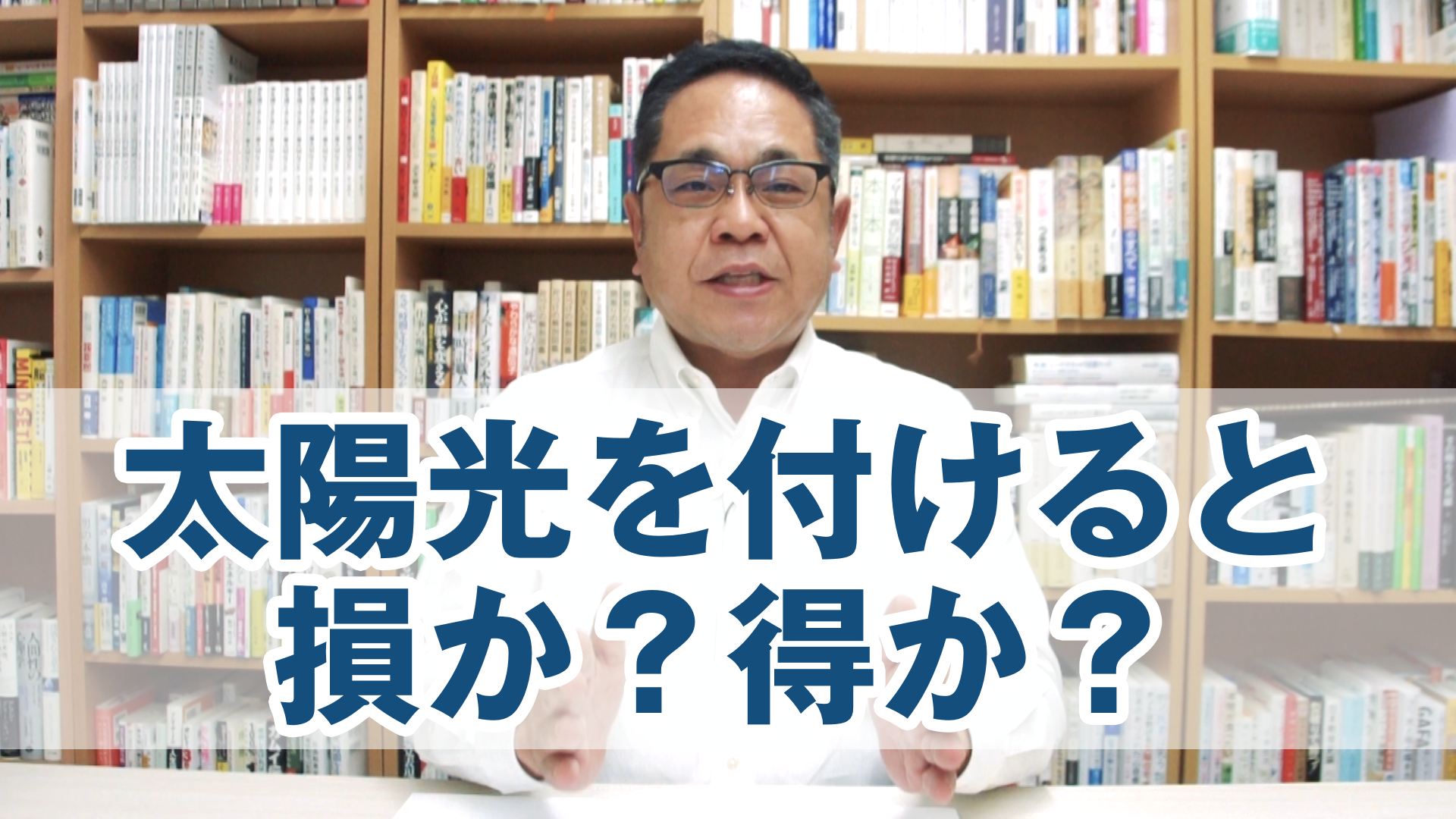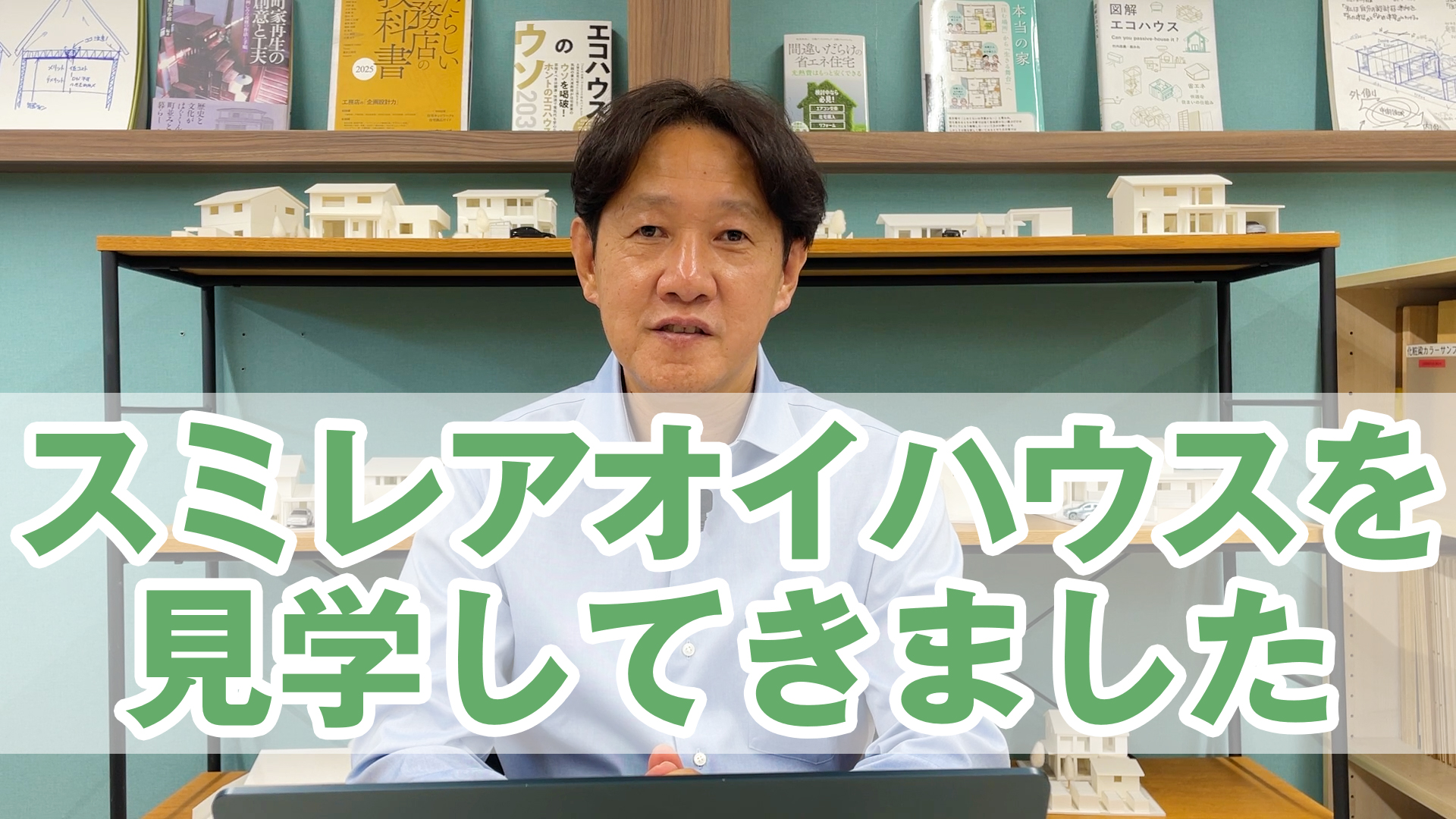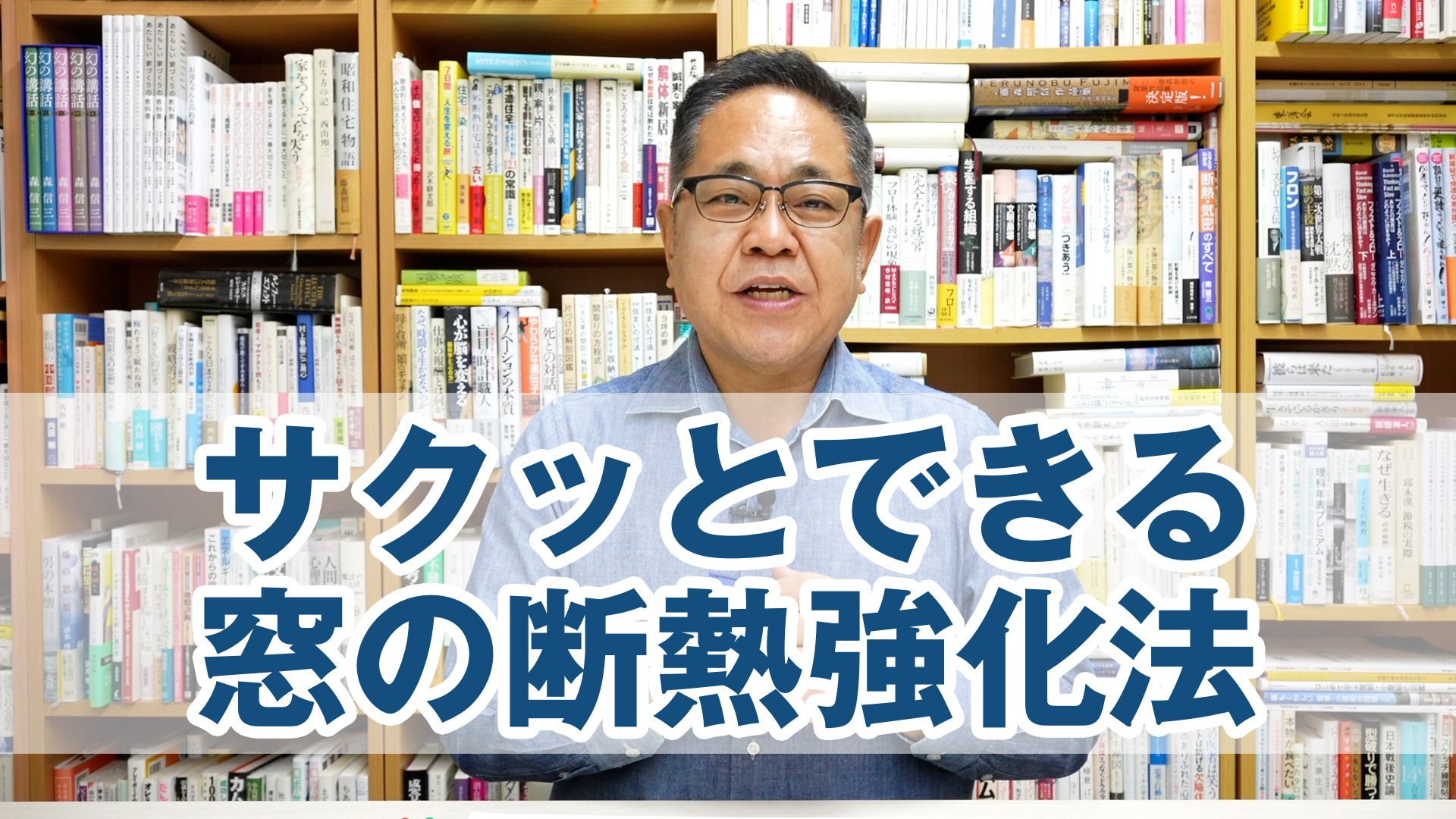Q&A:風通しの良い間取り・窓の種類、風通しを改善する方法
今日は、ここのところやらせてもらっているQ&Aの中で、「風通しの良い間取りや窓の種類、風通しを改善する方法を教えてください」という質問をいただきましたので、今回はその“風通し”についてお話ししていきたいと思います。風通しの話はこれまでも何度かしてきましたので、「あ、それもう聞いたことあるで」という方もいらっしゃるかもしれませんが、ご質問にお答えする形で、改めて整理してお話ししたいと思います。
ただ、このテーマをこの時期に持ってきたことで、「今それ?」と思われる方もいるかもしれませんね。実はこの動画を収録しているのは10月なんですが、「風通し」と聞くと、どうしても夏前に語るイメージがあると思うんです。でも僕は最近、風通しというのは“夏に考えること”ではなくなってきてるんじゃないかなと思ってるんです。なぜかというと、今の夏は本当に暑いし、湿気もすごいですよね。高温多湿で、まるで昔に行ったシンガポールとか香港みたいな蒸し暑さを感じるようになってきました。そんな湿気まみれの熱風を家に通したところで、気持ちいいのかどうか…と考えたりもします。
なので今回はまず、日本の季節感を少し整理してみようと思うんです。日本は“四季折々の国”と言いますけど、天文学的な区分で見てみると、春は3月21日頃の春分から6月の夏至まで、夏はそこから9月22日の秋分まで、秋はそこから12月22日の冬至まで、そして冬がまた春分までという分け方になっています。つまり理屈上はきれいに四等分なんですが、体感としてはどうでしょうか。僕の地元・兵庫県姫路あたりだと、昔は4月10日くらいまで桜が満開で、夜桜を見に行ったら寒くて「風邪ひいたわ」なんて言ってた記憶があります。そう思うと、春と言っても4月上旬までは冬と地続きのような感覚でした。
それから「小さい秋」って言葉、最近あまり聞かなくなりましたよね。僕の子どもの頃は佐藤八郎先生の童謡「小さい秋」を幼稚園で歌ってたくらい馴染みがあったんですけど、あれはまさに秋の始まりが短く、冬の訪れが早かった時代の感覚なんでしょうね。11月の終わりには肌寒くなって、12月に入ったら「師走やなあ」と言いながらセーターを出していた、そんな季節感でした。
それが今はどうでしょう。冬が長くなったというより、明らかに“夏が大きくなった”印象があります。桜も3月末には咲き始めて、4月頭にはもう春本番。そして6月に入るとすぐ梅雨が始まり、そこから10月初旬までずっと暑い。10月10日を過ぎてようやく「秋っぽくなったな」と感じるくらいです。つまり、昔よりも夏がぐーっと長くなって、秋がギュッと短くなったように思うんです。
そうすると、風通しを楽しめる季節というのは本来“春や秋”なんですけど、そこにもう一つ厄介な問題が加わりましたよね。そう、花粉です。スギ・ヒノキ花粉が2月から6月頭くらいまで続き、6月から9月はイネ科、そして8月から11月にかけてはブタクサも飛びます。花粉症の人にとっては、ほぼ一年中つらいわけです。うちも家族全員スギ・ヒノキに弱いので、春は窓を開けたくない季節なんです。そうなると、気持ちよく風を通せる時期って、実は10月10日くらいから11月にかけての1か月ほどしかない。だから、風通しの話をこの秋にするのは、むしろちょうどいいタイミングなんです。
今この撮影をしている時期は、外に出るのが本当に気持ちいい頃です。ウッドデッキに出て、虫はいるけど秋の虫です。コオロギとかね。夕暮れ時に虫の声を聞きながら、こっそりビールを開けて飲みつつ、うちの愛犬・小太郎くんの頭をなでて、「芋食うか?」なんて話しかけてると、奥さんに「いつまで外おんの!早よお風呂入り!」って怒られるんですけど(笑)。でも、そんな時間こそが“内と外がつながる家の醍醐味”なんですよね。
そんなわけで、今日は「秋こそ風通しを楽しもう」という話がしたかったんです。少し前置きが長くなりましたけど、ここからが本題です。風通しが良い間取りといえば、一般的には“対面に窓がある”配置がいいとされています。ただ、実際の引き違い窓はクレセントを開ける関係で、左側の窓が開けやすい構造になってるんですね。なので、左右の位置関係を考えると、風は部屋の中を緩やかに斜めに抜けていく。これが意外と大事なポイントなんです。
また、もし南側に大きな窓がある場合、北側の窓は小さくしたいことも多いと思います。そのときは“外開き窓”を対角線上につけると、風がきれいに通り抜けます。つまり間取り全体というより、部屋単位で“風の通り道”を考えるのがコツです。例えば、南北に部屋が並んでいるなら、水回りの窓も含めて風が抜けるラインを作る。中の建具も引き戸などでつなげると、家全体の通風がぐっと良くなります。
そして小さな窓でも、開き方を工夫すればしっかり風が通るんです。例えば、右吊り元・左吊り元をうまく組み合わせて、風の入り方を制御する。これだけでも全然違います。それに加えて、平面だけでなく断面でも考えてほしいんです。下の“地窓”から風を入れて、上の“高窓”から暖かい空気を抜く。この組み合わせはとても有効です。夏でも、熱気を上から逃がせるので、自然な空気の流れが生まれます。
最後に、窓が一方向しかない部屋の場合の工夫です。窓を全開にしても風が入りにくいことってありますよね。これは内圧が高まって、風が入りづらくなるからなんです。そんな時は、2枚の引き戸を左右均等に開けてみてください。すると中央部分に抜け道ができて、意外と風が通るんです。虫が気になる人は、後付けのアコーディオン型網戸をつけるのもいいと思います。あるいは両側が開くタイプの窓に交換する方法もあります。ちょっとした開け方の工夫でも、風の抜け方は驚くほど変わります。
こうした工夫を取り入れて、内と外のつながりを感じられる季節——それが今、この秋なんじゃないかなと思います。もちろん春でも、雨上がりで空気が澄んだ朝なんかは気持ちいいですけどね。ぜひ、そんな“風のある暮らし”を楽しんでもらえたらと思います。
今日はちょっとした小ネタでしたが、風通しについてお話しさせていただきました。こんな感じで、これからもQ&A形式でいろんな家づくりの話をしていきますので、よかったらYouTubeのコメントや、モリシタ・アット・ホームの問い合わせフォームから「こんなこと聞きたいねん」と送ってください。僕が必ず見て、できるだけ取り上げていきます。ネタ切れ気味なので、ぜひ助けてもらえると嬉しいです。