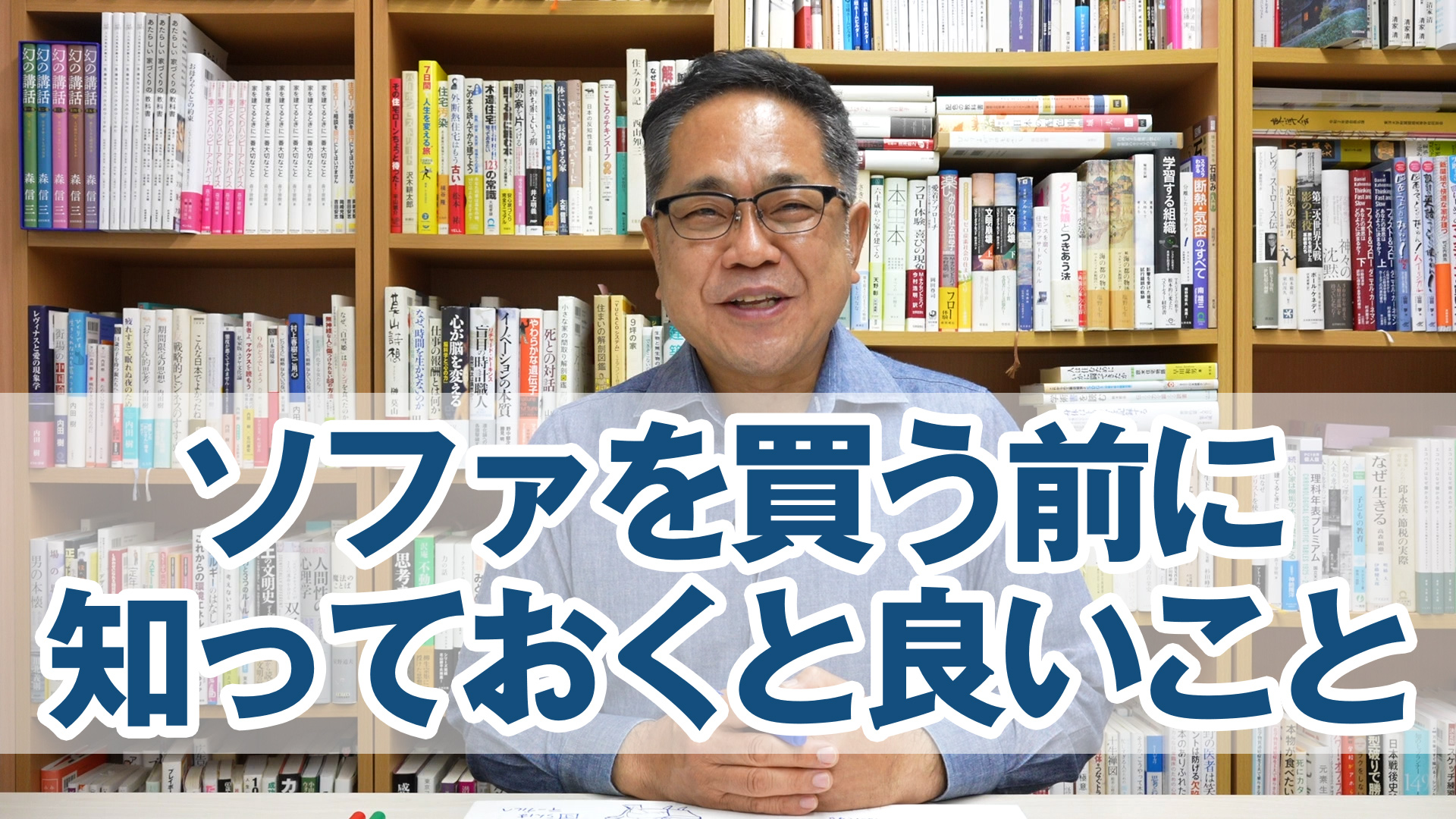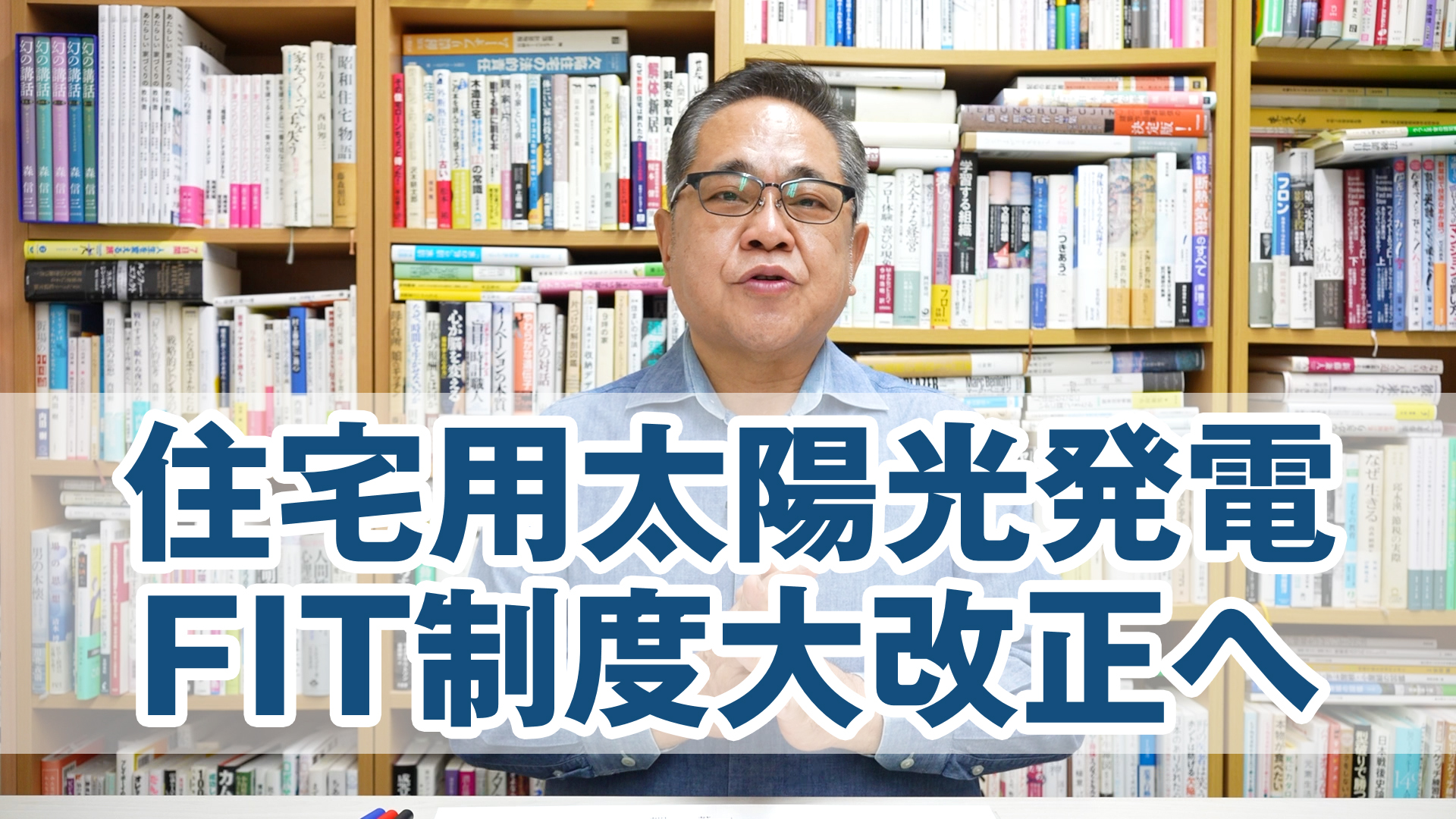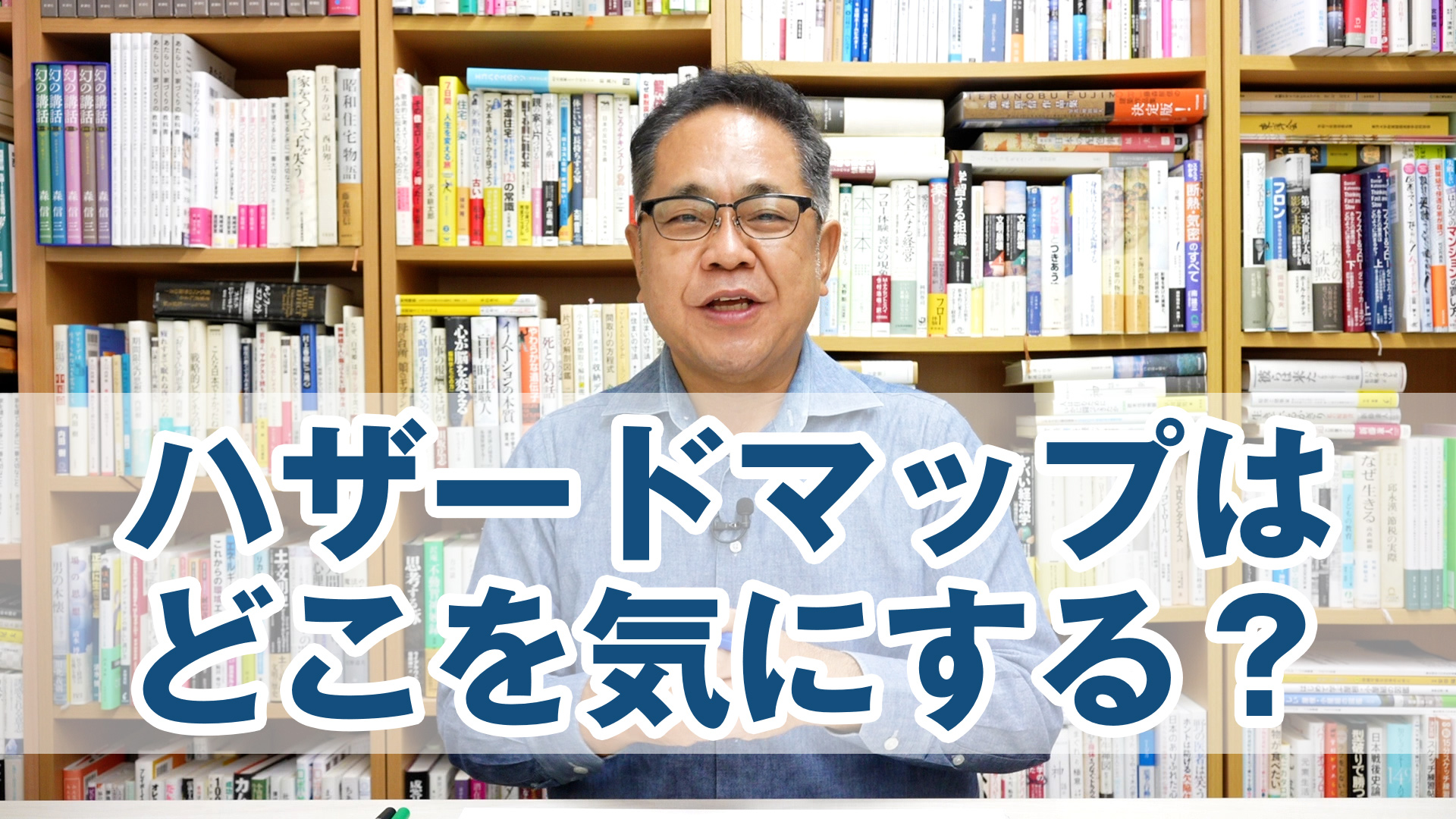住まいの終活を考えるシリーズ② 「実家じまいで失敗しない今からできる3つの整理」
今回も「住まいの終活」、いわゆる実家じまいで失敗しないために、今からやってもらいたい3つの整理方法について解説していきたいと思います。
▼住まいの終活を考えるシリーズ① 「実家じまいがうまくいかないケースと対策」
https://www.m-athome.co.jp/movie/shukatsu_case_taisaku/
まず、整理には3つの方向性があると思うんです。その1つ目が「お金についての整理」。2つ目が「行く末の整理」、そして3つ目が「自分の気持ちの整理」。この3つの視点で整理を考えていくのが良いんじゃないかなと思います。
まず最初に「お金の整理」ですが、実家じまいや空き家の対策になりますので、当然、不動産に関するお悩みということになりますよね。この不動産が、今の状況の中でどれぐらいの経済的価値があるのか、あるいは場合によっては経済的損失を生みそうなのか、そのあたりをまず知ることが大切です。それから、「この家、もう使わないから誰かに借りてもらおうかな」となったときに、そもそも貸し出しができるのかどうか、貸すとしたらどれぐらいの収益になるのか、そういった部分を把握すること。これはいわゆる「不動産の査定」ということになります。
この部分が分からないと、前回もお話ししましたが、具体的な対策を立てようとしても、方向性が見えてこないということになります。そして、「売るも貸すもなぁ、家が古くてボロボロやし…」という場合は、「じゃあ解体せなアカンのちゃうか」という話になりますよね。その際に、解体費用がどれくらいかかるかを、ちゃんと調べておかないといけません。ネットなどで地域による違いも見てもらえたらと思いますが、木造の解体費用は坪あたり3万円台後半から5万円くらいまでかかることが多いようです。
ただ、そのコストでは収まらない場合もあります。それは何かというと、古い家にありがちな「アスベスト」の問題です。家が古いというだけでなく、年代的にアスベストが使われている可能性がある家というのがあるんですね。例えば築100年以上の家なら、かえって大丈夫だったりするんですが、築40〜50年というのが一番怪しい時期なんです。アスベストが使われていると判明すると、「管理型の解体」をしなければならなくなり、費用が3倍以上かかるというケースもあります。ですので、信頼できる専門家に調査してもらって、解体にかかるコストを正確に知っておくことが大切なんです。
ちなみに、僕の地元・兵庫県姫路市では、古くて危険なお家を壊す際には、補助金が一部出る場合があります。たしか最大で100万円くらいだったと思いますが、もちろん予算も決まっていて、申請の時期や家の条件によっては補助対象外ということもあります。「どこがアカンのか」といった細かい規定もありますので、そういったことは詳しい人にしっかりと聞いてもらったほうがいいと思います。こうしたことを含めて「お金の整理」というのはとても重要で、むしろ一番大きな要素かもしれません。ここが整理されないと、他のことがなかなか進まないという面もあるんですね。
その上で、次に考えるのが「行く末の整理」です。これは、どんな出口を想定するかという話になります。家を「売る」というのは一つの処分の仕方、「貸す」というのは活用の仕方。だから、処分や活用といっても、一つではなくいろんな方法があるんです。その中で、自分たちに合った選択肢はどれかを知っておくことで、初めて適切な判断ができるようになる。ここも非常に大事な部分です。
そして、「行く末の整理」で欠かせないのが「権利関係」。例えば、抵当権がまだついているとか、借地権があるとか、ご近所との土地の境界がはっきりしていないといったケースもあります。そういったことが、行く末を大きく左右する問題になることもあるんです。仮に、境界の問題で揉めているような家だったら、もう隣の人に「この土地、全部買いませんか?」と相談してみるというのも、一つの考え方かもしれません。境界線が問題になる前に、まるごと引き受けてもらうような形ですね。
それから、田舎に行くと実家の近くにお墓があるというお家もありますよね。僕の田舎もそうなんですが、お墓がなくても、仏壇や神棚があると、それもまた処分や活用の際に重要な要素になってきます。ですので、こういったことも含めて「行く末の整理」は必要なんじゃないかなと思います。
そして3つ目が「気持ちの整理」です。これは、おじいちゃんおばあちゃん、つまり所有者の方の気持ちでもあり、それを継いでいく子や孫たちの気持ちでもあると思います。先祖代々の家だと、「俺で5代目や」「うちは10代続いてる家や」といった思いがあって、自分の代で処分するのはどうなんやろう…って、やっぱり罪悪感を感じたり、後ろ髪引かれたりする気持ち、ありますよね。
でも、家族の状況や仕事の都合で、そうせざるを得ない時もある。そういった時に、自分の気持ちとどう折り合いをつけていくかが大事なんです。たとえば、「お父さんがすごく大事にしていた家や庭やから…」というような思いもあるでしょうし、そこには家族それぞれのこだわりや愛着、思い入れがあるものです。「この家は、わしが一生懸命考えて、丹精込めて建てた家やから。俺が死んでから好きにしてくれたらええ」という方もおられます。でも、いざその時が来る前に、やっぱり決着をつけておかないといけない場面が出てくるんですね。
すべての家には、それぞれの物語があります。だから、経済的な合理性だけで割り切って進めていけるかというと、やっぱりそれだけでは難しいと思うんです。なので、この「気持ちの整理」は、とても大切なポイントやと思います。
そして、実家じまいや空き家の活用・処分で一番大事になってくるのが「家財の整理」です。家の解体っていうと、建物そのものは解体してくれますが、中の残地物が残っていたら、「それは別途処分してください」と必ず言われます。つまり、「一緒にまとめて全部捨ててください」とはいかないわけですね。
できれば、住んでいるうちに、所有者の方、つまりおじいちゃんおばあちゃんが元気なうちに、少しずつ整理をしていくのが理想です。でも現実には、「それは私が死んでからにしてちょうだい」とか、うちの母もそうですけど、「私が死んでからでええわ」って言う人も多いんです。でも、「お母ちゃん、これをお母ちゃんが整理してくれんかったら、わしらではなぁ…」っていう場面、ありますよね。
だから、さっきのお話にもありましたように、やっぱり所有者の方、つまり親御さんの気持ちに寄り添っていくことが大事なんです。そして、それは何も「全部捨てる」とか「全否定する」ってことではなくて、「これからの暮らしをより良いものにするための準備」なんだと。「死んでいく準備や」なんて言うと、ちょっときつい表現になってしまうかもしれませんけど、でも「気がかりを抱えたまま、病気になったり死んでいくのは嫌なんや」っていう気持ち、きっとあると思うんですね。そういった気持ちに、子どもである自分たちがちゃんと寄り添って、自分の思いも伝えながら、一緒に整理していく。この「気持ちの整理」もまた、大変だけど大切な作業やと思います。
そういった時には、「お金の整理」や「行く末の整理」を踏まえた上で、「気持ちの整理」もつけていく。この3つは、まさに三位一体で進めていく必要があると、僕は思います。
それで、「じゃあ、これから家族で整理をしてくださいね」って、いきなり言われても、やっぱりしんどいですよね。僕自身もそういうの、よく分かります。一人で決めるのも難しいし、家族だけで話そうとすると、時には夫婦喧嘩や親子喧嘩にまで発展することもあります。
なので、僕がおすすめするのは「第三者を利用する」というやり方です。簡単に言えば、「話し相手を持つ」ということですね。第三者で、ある程度ニュートラルな立場の人がいてくれると、「お父さんのお気持ち、よく分かりますよ」とか、「でもお子さんの心配も、ごもっともですよね」と言ってくれる。そうやって間に入ってもらえると、「あんたがそう言ってくれるなら、そうかもしれんな」って、話が滑らかに進んだり、やるべきことが明確になったりするんです。
こういう相談相手の存在は、ぜひ頭に置いておいてもらえたらと思います。これは、必ずしも不動産屋さんじゃなくてもいいと、僕は思います。不動産屋さんの中には、親身になって相談に乗ってくれる方もいますが、基本的には、整理や方向性がある程度決まってから動くという立場ですし、そこまで介入するのは難しいのが普通です。だからこそ、そういう整理に特化した第三者の相談相手というのは、非常に大きな力になると思います。
次回は、実家じまいや空き家対策における「出口」のこと、いわゆる「出口戦略」について解説していきたいと思います。