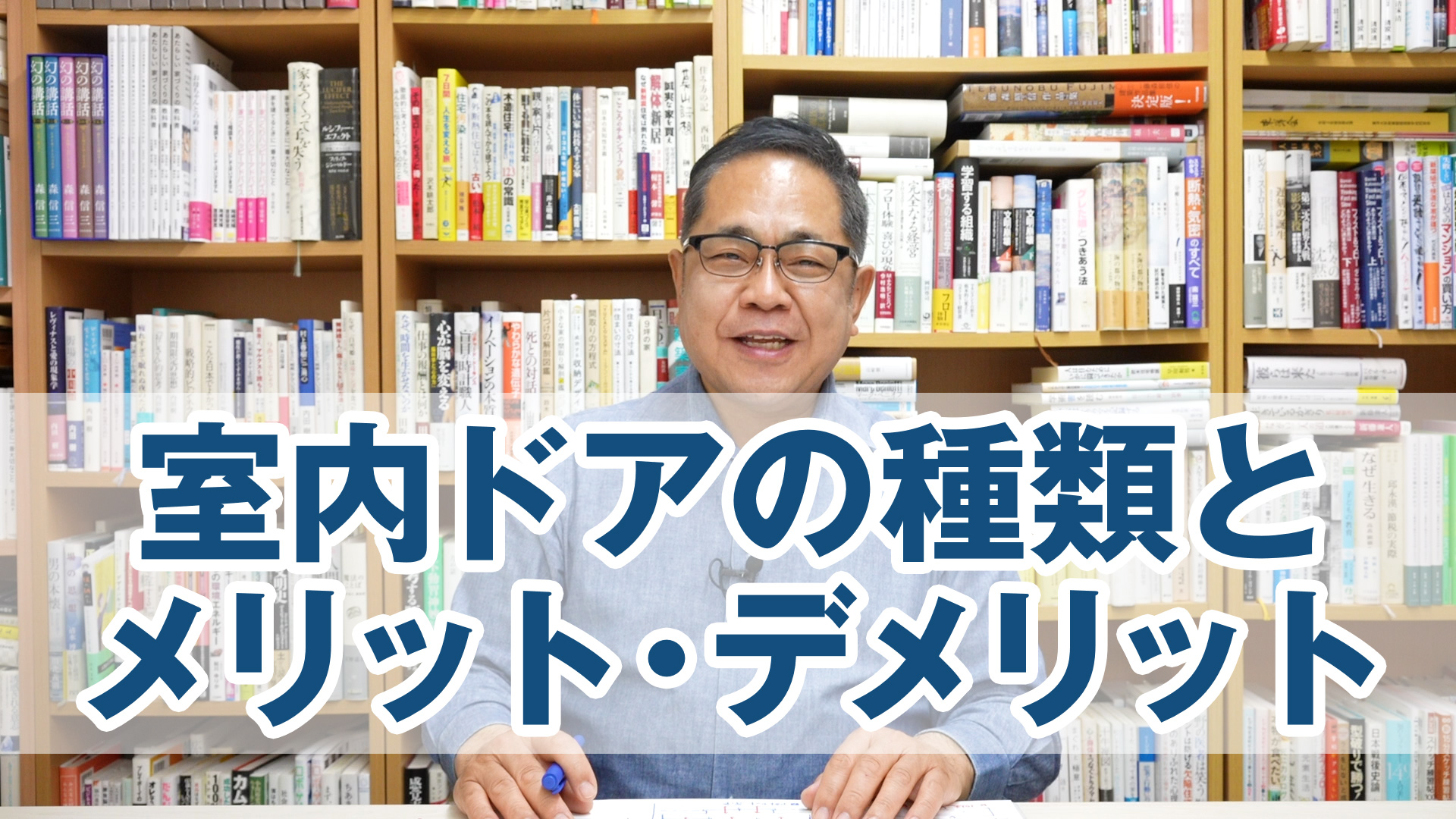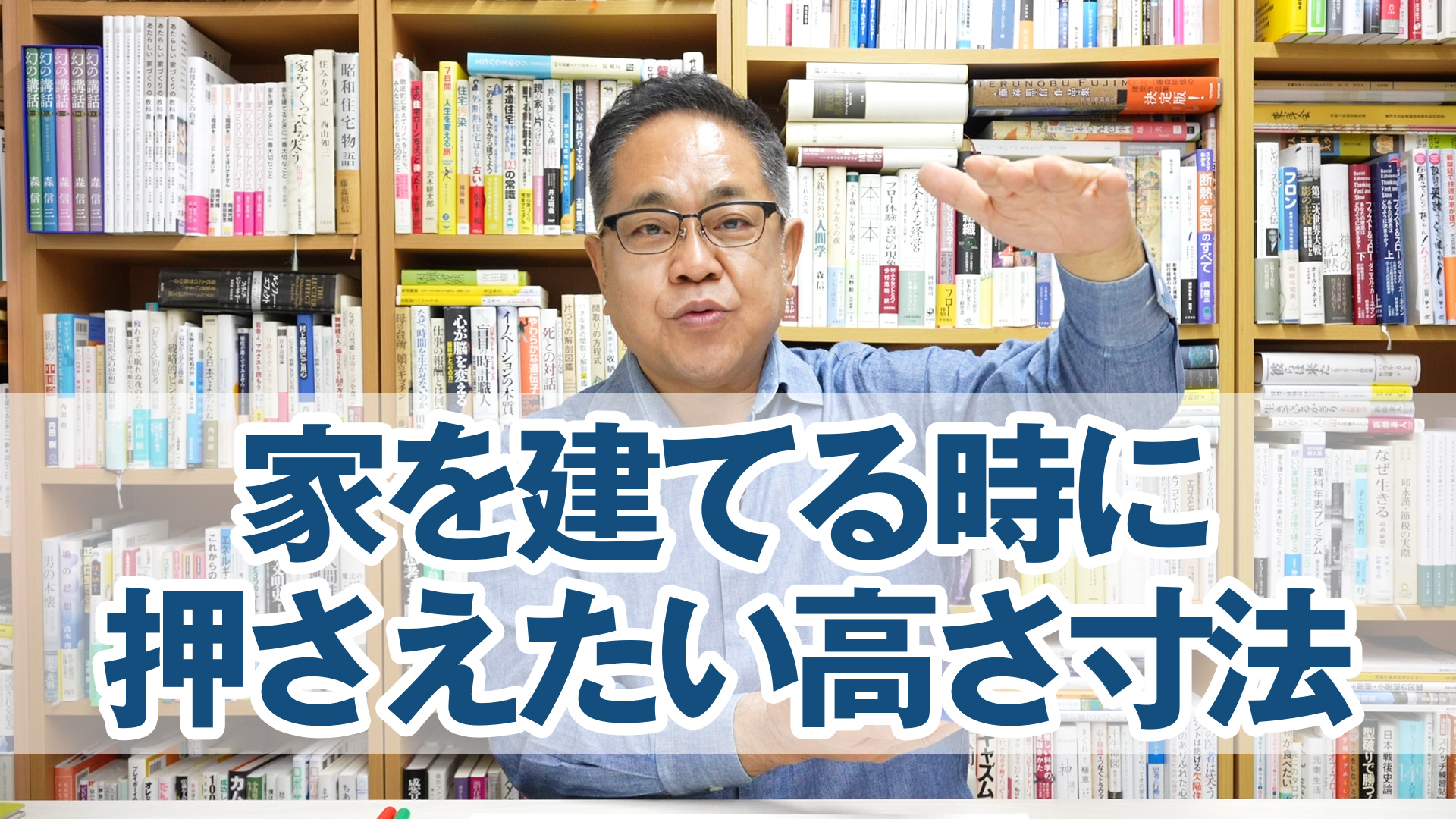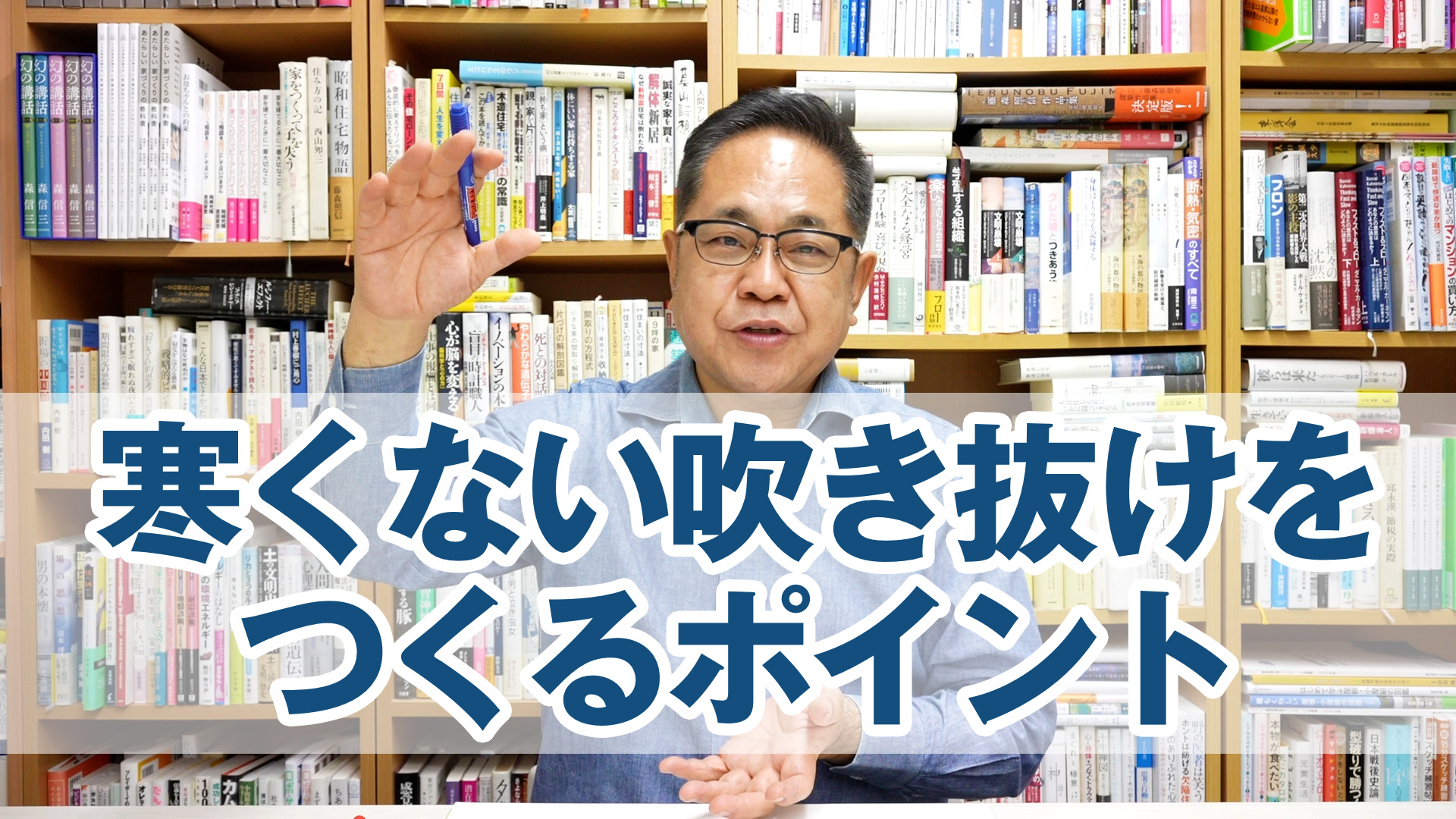間取りの新常識:それぞれの居場所のつくり方
今回は「家族それぞれの居場所」というテーマで解説をします。
きっかけになったのは、先日も紹介した「間取りのすごい新常識」という本です。発行は2020年で、僕が以前に買っていた本なんですけど、お客さんとの間取りやプランの打ち合わせの中で、何かに行き詰まった時などに、古い本を漁って読み返すことがあります。その中で、家族の居場所というテーマについて改めて考えさせられたので、今回はそのエッセンスを含めて解説します。
長年家づくりをしてきた中で、間取りを考える時は「夫婦と子ども」という括りで最適な形を考えることが多かったんですが、最近ではそれ以外の家づくりが増えてきています。たとえばシニアの終の住処や、お一人様の暮らし、子どもが大きくなって大人だけの暮らし、またコロナの影響もあって在宅勤務が増えたことなどから、これまでなかった家の使い方が求められてきました。そうした変化を踏まえて、今回は居場所のつくり方として4つの事例を紹介します。
1つ目は「玄関直結の仕事場」です。玄関の土間が広くて、そこから仕事場に直結しているプラン。LDKにもつながっているんですが、仕事の来客がある場合、外部の人が靴のまま土間で打ち合わせできるようになっています。住まい手はサンダルなどで出られるようにすれば、来客とのプライバシーを保ちつつ、生活との切り替えもできる。これは仕事だけでなく、趣味のスペースとしても応用できます。たとえば僕だったら自転車の整備などを、外では寒いからここでやる。家族に迷惑をかけないようにしながら、自分のスペースとして使える。仕事や趣味に没頭できる場所としても、とても良いつくり方だと思います。
2つ目は「家族が集う場所の近くにこもれる空間をつくる」パターンです。ダイニングの近くに2畳ほどの空間があり、本棚とテーブルがあって、ヘッドホンをしてオーディオを聴いたり、ゲームをしたり、本を集中して読んだりすることができる。僕だったら大画面を置いて映画に没頭する空間にもいいなと思います。リビングでそれができないわけではないけれど、リビングは家族の気配もあるので、こういった“おこもり”の空間があると、より集中できると思います。
3つ目は「暗室のある間取り」。デジタル時代になっても、写真を扱う人にとっては暗室が必要らしいです。リビングに隣接した納戸の奥に暗室を設けるプランで、完全に隔てられた空間です。ここにこもって、何時間でも没頭できる。アクセスは悪いけれど、それが逆に集中を高めてくれる。これは例えばギターや楽器など、自分の趣味に没頭する場所としても転用できます。リビングで音を出せば怒られるけど、こういう空間があれば好きなことに没頭できます。
4つ目は「2つの個室をバルコニーで穏やかに分ける」方法です。家族4人の暮らしでは、リビングの心地よさ以上に、各部屋の居心地が重要になることもあります。食事の時間がバラバラで、それぞれの生活リズムで暮らす時代には、それぞれの空間が重要になる。兄弟で暮らす場合でも、バルコニーを挟んで気配は感じられるけど干渉しない。天気が良い日はバルコニーに椅子を出して、自然と会話が生まれたりもする。リビングだと親の目が気になる、そんな時に兄弟や姉妹だけの中間領域としての空間になる。もちろん夫婦にも当てはまります。
たとえば、定年後に旦那さんが「目障りだ」と言われる話、あれは冗談みたいで、でも現実によく聞く話です。実際、僕のまわりの奥様方に聞くと「目障り」とはっきり言う方も多い。だから、お互いを尊重しながら、それぞれの居場所が確保できる間取りは、今後ますます大事になると思います。
結局、家族団らんというのは理想ではあるけど、現実にはそれぞれが自分のペースで暮らすことが多い。だからこそ「いつでも一緒にいられるという安心」と「いつでも1人になれるという安心」を両立できる家が求められる。これは新しい間取りの考え方の根っこになると思います。
ステレオタイプな子育ての家づくりだけじゃなくて、その先の暮らしまで見据えたプランを考えることで、より豊かな家づくりができます。今は家づくりにお金がかかる時代ですが、だからこそ、ディープに考えて、自分たちらしさを追求する家づくりをしてもらいたい。ぜひ今回の視点も、みなさんの家づくりのヒントにしていただけたらと思います。