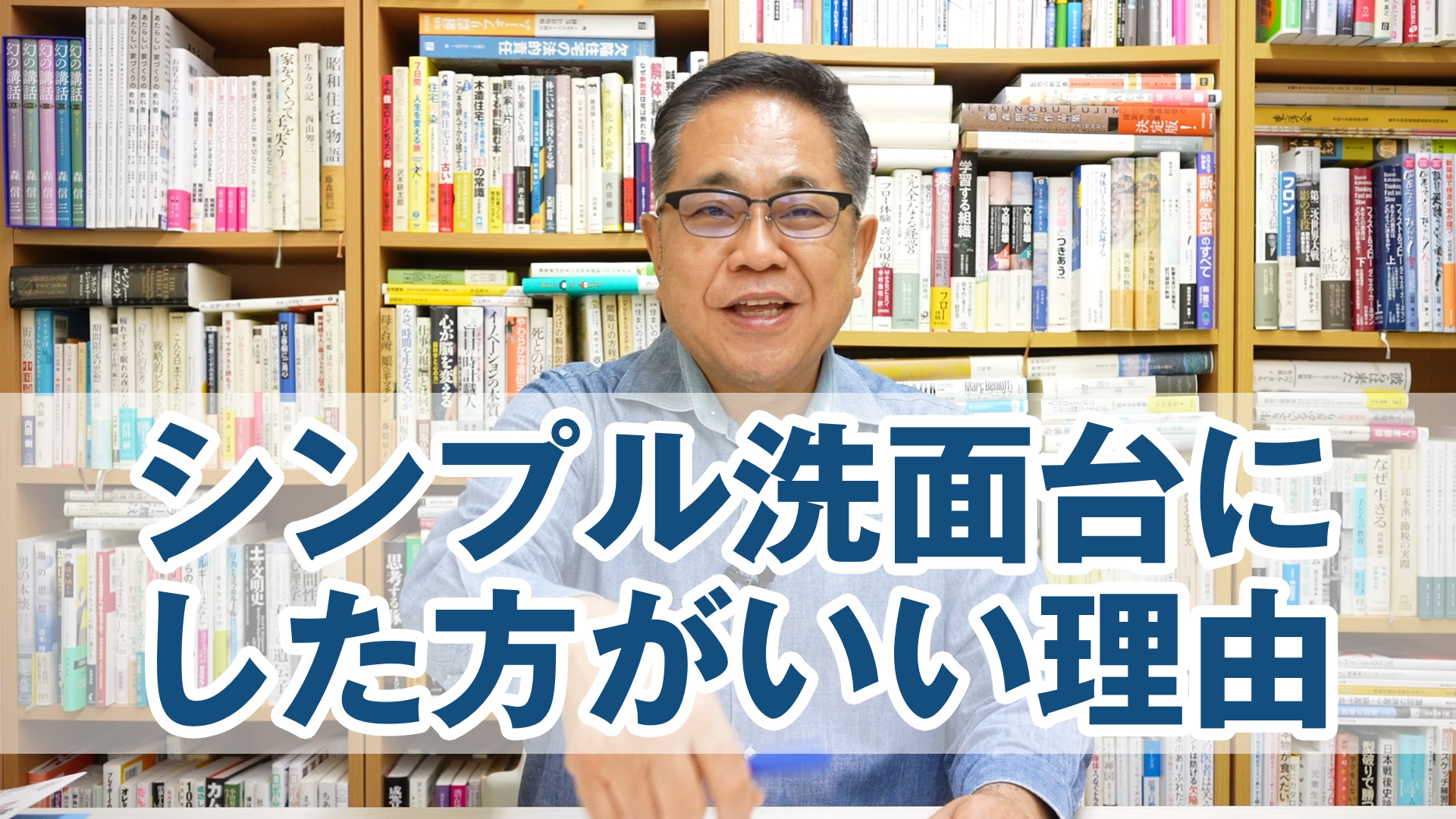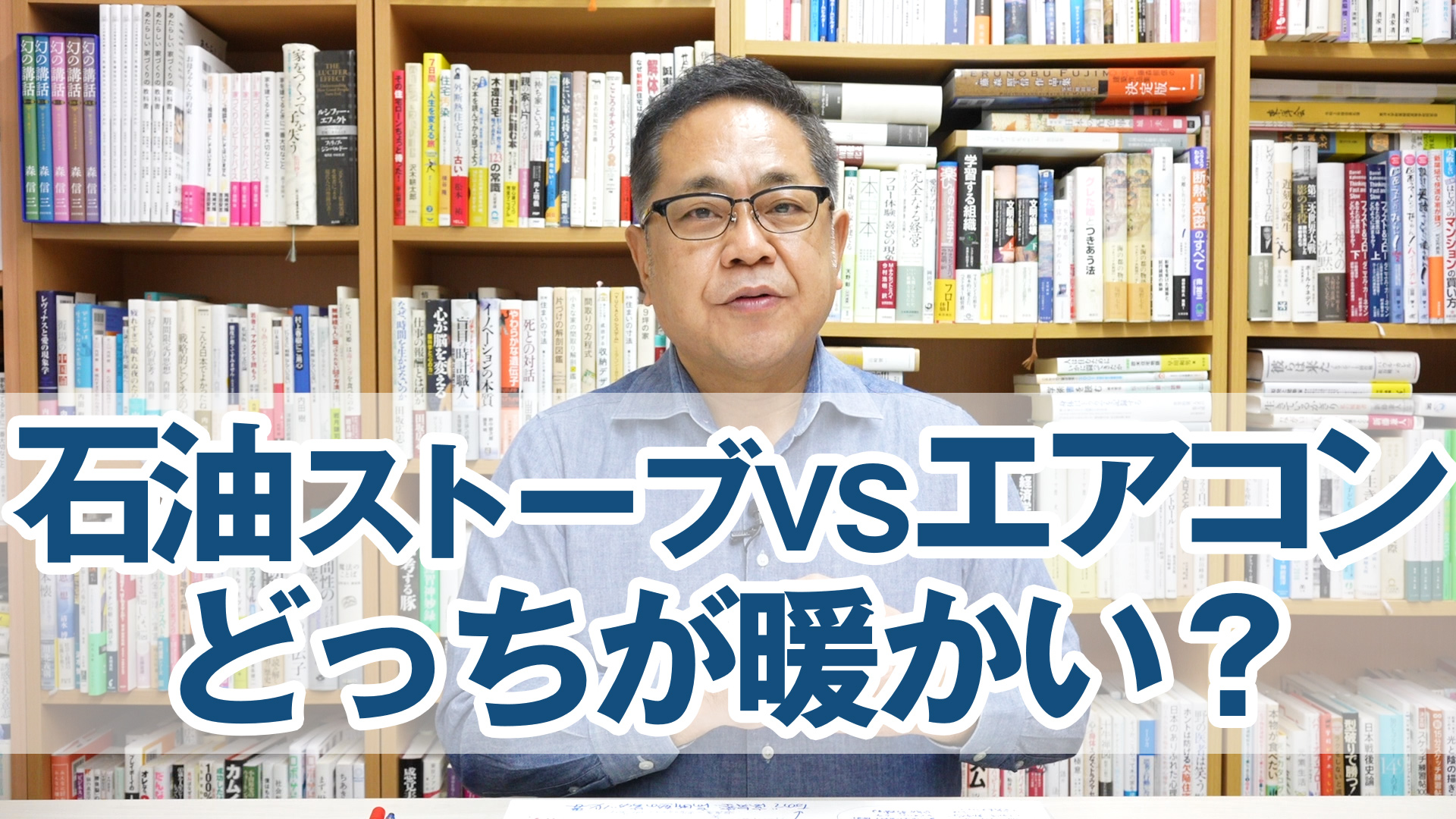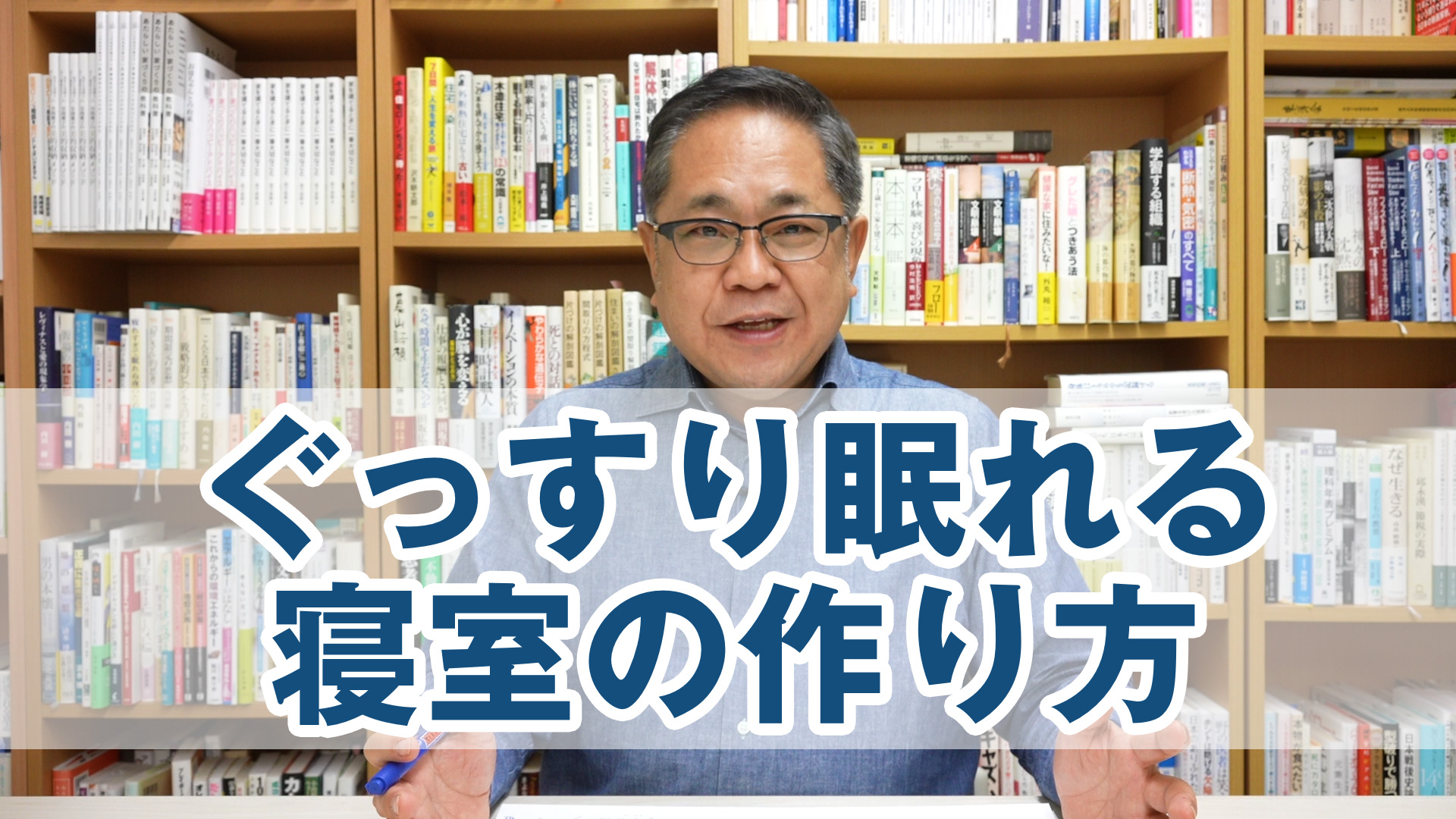梅雨時の家づくり:雨養生が大切な理由
さて、先日あるお客様からこんなご質問を受けました。というのも、その方のご近所で木造の建物の棟上げがあったそうなんですけど、それが3日ほどかけて行われていて、「多分、あれは2×4の建物なんじゃないかな」とおっしゃってたんですね。ただ、その時すごく雨がひどくて、構造材がベタベタに濡れていたそうなんです。で、「森下さん、あれって大丈夫なんですか?木材を水に濡らしたらアカンのちゃいますかね?」というご質問だったんです。
それを受けて、今日は僕がこれまで経験してきたことを交えながら、少し解説していきたいと思います。いつものように、僕の板書を見てもらいながら、思い出話も聞いていただけたらなと思います。
実は僕、2016年に国交省が主導するある研究事業に関わらせてもらったことがあります。それがですね、名前が長くて舌を噛みそうなんですけど、「木造住宅の耐久性向上を目的とした、実大木造建築物の各部位における水分の挙動に関する研究」という、かなりアカデミックな研究です。この研究には、近畿大学の湯和舞先生や、東海大学の石川先生といった、建物の耐久性について非常に詳しい先生方も関わっておられました。
それから、ハウゼコさんという建築の水切り部材などを作っているメーカーの神部社長が中心となって進められた実験なんです。この「実大木造建築物」っていうのは、実際の家と同じサイズの本物の家を建てて、そこでさまざまな検証を行うという、いわゆるリアルスケールの実験ですね。その実験用の建物を、ありがたいことに私たちモリシタ・アット・ホームが建てさせていただいたんです。先日紹介した山下社長が、当時の現場責任者を務めてくれました。
山下社長も現場でいろんなことを実際に見て、驚いたり、なるほどと勉強になったことが多かったそうです。この実験で建てた家は、今流行りの「フラットルーフ」の形をしてまして、四角いキューブ型のデザインです。一般的には屋根って三角の形をしてますけど、フラットルーフの家は屋根が平らに見えて、実際には三方向が立ち上がって壁のように見え、中は少し下がっていて水勾配がついた屋根があり、その一方に雨樋がついて雨水を排水するような構造になっています。北海道なんかに行くと「落雪型」といって、もっと建物の中央に雨を集める構造もありますけど、西日本ではこのフラットルーフの構造がよく見られます。
この実験で建てた家は、基礎や構造体は同じなんですけど、外壁や屋根の仕上げ、細かい収まりが異なる仕様で比較をしました。例えば、柱の間に通気層を作って壁を構成し、その上に屋根をかぶせるという一般的な構造においても、その通気層の出口や防水処理の方法に違いがあると、どう変わるのかを比較したわけですね。
特に、雨がよく当たる壁の上部では、雨漏りを防ぐために防水や止水処理が重要になります。一方で、通気層からしっかりと湿気を逃がす構造も必要でして、そのバランスが難しいんです。実際に、昔から防水優先で構造を組んでいたエリアと、今回の実験で通気を重視して設計したエリアで、どんな違いが出るかを確認しました。
この家では、特殊な換気部材を使って、空気は通すけど雨水は入らないという工夫を施した屋根と、従来通り完全防水優先で換気をあまり考慮しない屋根の2種類を作って比較しました。実際に完成してから約1ヶ月後に、先生方や関係者の皆さんと一緒に現場を点検したんですけど、防水優先で通気を確保していなかった方の屋根の点検口を開けたとき、黒い水がジャジャーッと落ちてきたんです。僕も「雨漏りか?」と一瞬思ったぐらいでしたが、実際には雨水ではなくて、湿気がこもって結露した水だったんです。
その部分は特にフラットルーフの構造で、屋根の通気がうまくできていなかったんですね。一方で、空気の流れをしっかり設計して換気がうまくいっている方の屋根は、点検したときもカラッと乾いていて、含水率計で測っても15%と、非常に良い状態でした。ところが、防水重視で通気ができていなかった方は、水分量が多くて、含水率計の針が振り切れるぐらいになっていました。
この時、建築中に少し雨が降って屋根の下地材が軽く濡れたことがあったんですけど、それでもちゃんと換気ができていれば乾くんです。だけど、換気ができていないと、こんなに湿気がこもってしまうんだと、改めてわかったわけです。現場ではどうしても、急に雨が降ることってありますから、濡れたとしても、ちゃんと乾く仕組みや管理体制が重要なんだなと実感しました。
また、この実験で印象的だったのは、1階と2階の床にも仕上げのフローリングを貼る前に構造用合板を敷いてるんですけど、その1階部分でちょっとしたトラブルがありました。というのも、工法の都合で、1階の土台と床下地を先にやっておいて、後日一気に上棟するケースがあるんですね。そのときに床下地の合板が少し濡れたんです。そんなにベチャベチャではなかったんですが、それでも濡れてた。
で、乾いてからカラーフロアを張ったんですけど、しばらくしてから、その床に変なシミが出てきたんです。ゴーストみたいな模様で、「これ何やろう?」ってなったんですが、どうやら下地の合板に残っていた湿気が、じわじわとフローリングを通して出てきたんですね。カラーフロアは表面にウレタン樹脂の塗膜があるので、サランラップのように水蒸気を通しにくいんです。そのため、湿気が逃げきらずに溜まってしまって、それがシミになった、ということだったんです。
この経験から僕が思ったのは、在来木造の柱や梁などの無垢材は、多少濡れてもちゃんと乾くんです。でも、構造用合板っていうのは、薄い板を何層にも接着剤で貼り合わせて作ってるので、一旦中まで水が染み込んだら、乾くのにすごく時間がかかるんですね。もしかしたら、完全に乾くまで1年近くかかることもあるかもしれません。
だから、極端に言えば建物が潰れるということはないかもしれないけれど、内装材に影響が出たり、結露の原因になったりする可能性はゼロじゃないと思うんです。冒頭のお客様の質問への答えになりますけど、たとえば2×4の家を作っているような大手のハウスメーカーさんでは、柱や梁にはしっかり撥水処理がされていたり、床の合板には防水ラミネートが貼られていたりと、対策が取られているようです。だから、「大丈夫です」と言える論拠があるわけです。
ただ、それでもあまりにベチャベチャに濡れてしまったら、やっぱり構造用合板が水を吸い込んでしまって、内装材に悪さをしたり、空気の流れが悪くなって結露の原因になったりすることもゼロではないと思うんです。特に北側とか条件が重なる場所では、そういうことも起きうると思って、僕は一定の心配はしています。
でも、だからといって「欠陥住宅だ!」なんて言いたいわけじゃないんです。そうじゃなくて、「できるだけ濡らさん方がええよね」っていうことなんです。僕もよく言うんですけど、よっぽど大きな家じゃなければ、在来木造の場合は1日で上棟を済ませることが多いです。で、上棟したその日に屋根のルーフィング、防水処理を先にやってしまうことで、上からの雨が降ってももう濡れないようにする。さらに、その後も大型のブルーシートで建物全体をくるんで、できるだけ雨がかからないようにして養生しています。
ただ、天候が悪ければ無理せず、上棟を延期することもあります。これは現場での判断で、本当にそういうふうにしています。ただ、2×4の工法はどうしても3日ぐらいかかるので、大手さんがしっかり対策されているのは大事なことだと思います。でも、分譲住宅などで価格を抑えた2×4の家を見ていると、「これ、大丈夫かな?」と思う現場があるのも事実です。これは批判ではなくて、建築家としての純粋な心配です。
だから、皆さんもご自宅が建つときに、「この現場ではちゃんと対策されてるのかな?」と、遠慮なく聞いていただいていいと思います。それはクレームではなく、安心のために聞くということです。実際に現場監督さんに、「乾燥状態ってどうやって確認してますか?」と聞いていただければ、ちゃんとした会社さんなら「含水率計で測ってますよ」と答えてくれると思います。
濡れた場合には、コンクリートや木材からの湿気で表面にカビが出たりすることがあります。カビ自体は拭けば済むんですが、本当に怖いのは木材を腐らせる「腐朽菌」です。これは含水率が20%を超えると発生しやすいと言われています。だから僕たちは、14%とか15%に乾いてるかを測って確認しているんです。
あとは、仕上げ材の選び方にも影響があります。無垢材でオイル仕上げのようなものは、湿気を逃がしやすいので安心なんですけど、表面にウレタン塗装がされているような重厚なタイプは、湿気が抜けにくいので注意が必要です。
こうやって考えていくと、「木造は雨に弱いからダメなんじゃないか?」って思われがちですけど、それは鉄骨だって一緒です。例えばALCの壁材なども、水を吸いやすい素材なので、乾かすことが大事なのは同じなんです。つまり、濡れることが問題なんじゃなくて、濡れたときにどうリカバリーするか。ちゃんとエビデンスを持って、管理して、説明できることが大切だと思うんです。
だから、建てるときには「雨養生ってどうなってるんですか?」と聞いてもらうといいと思います。それもまた、家づくりの楽しみの一つかなと思います。天気と付き合いながら進める家づくり、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。