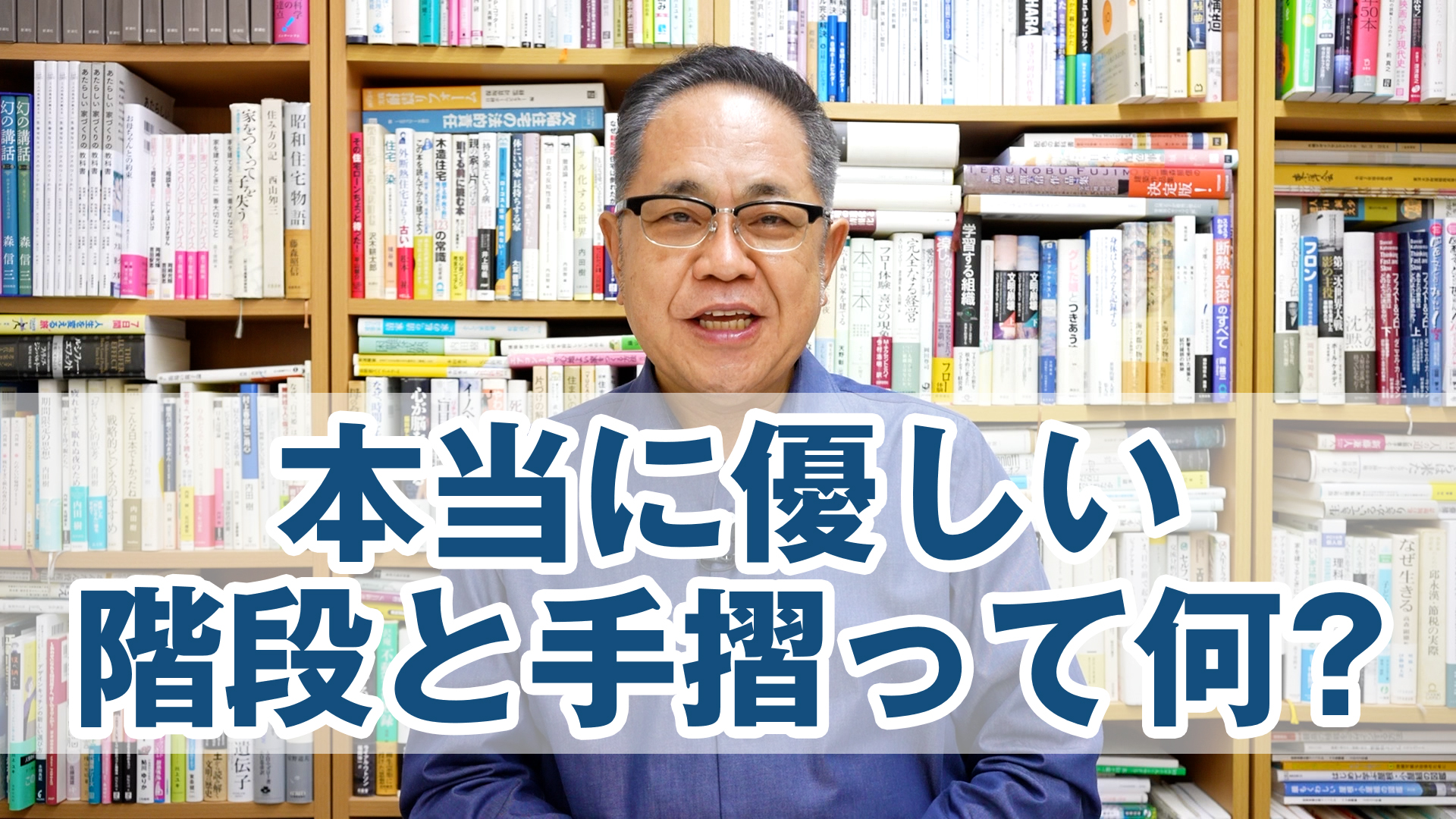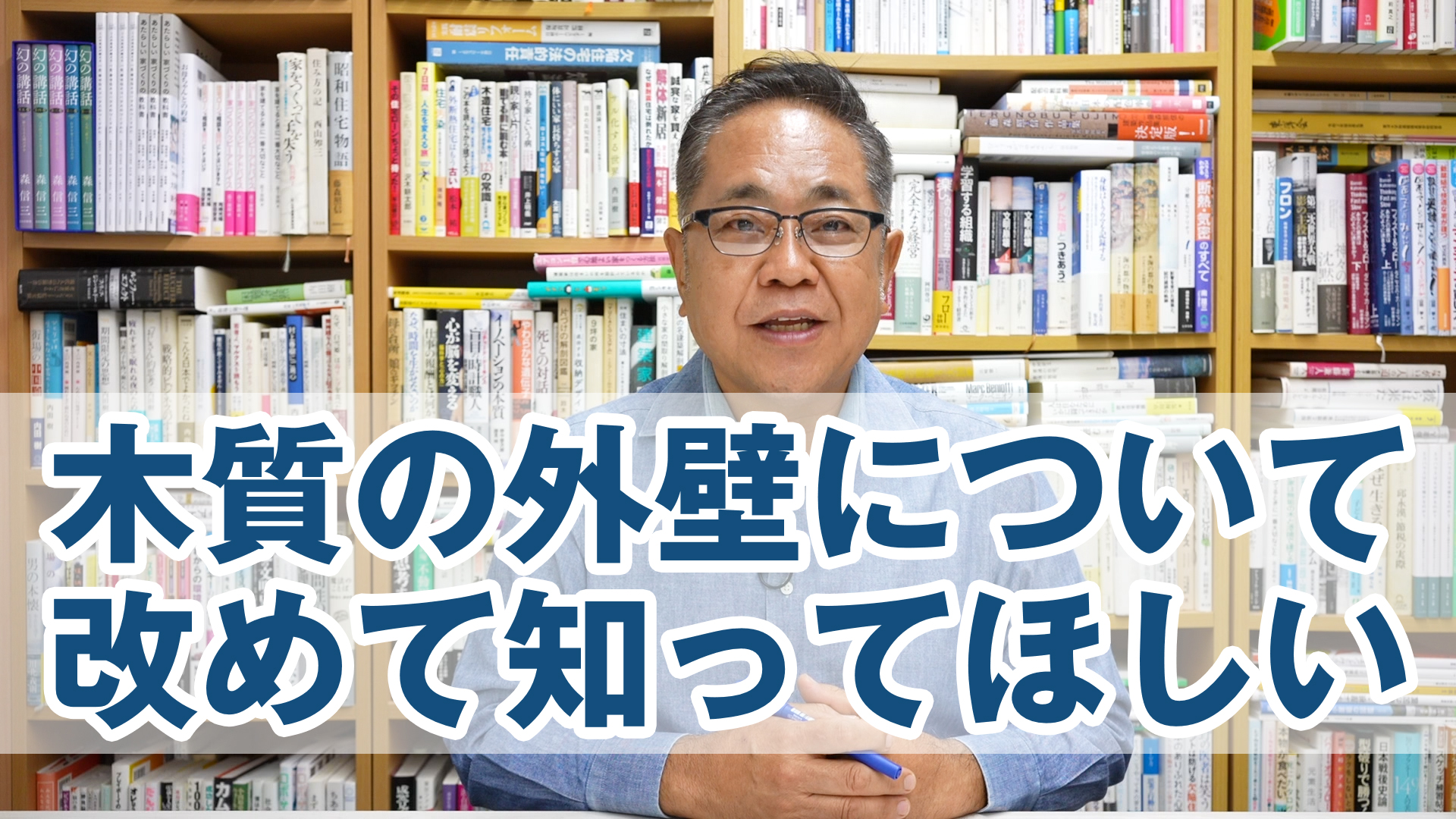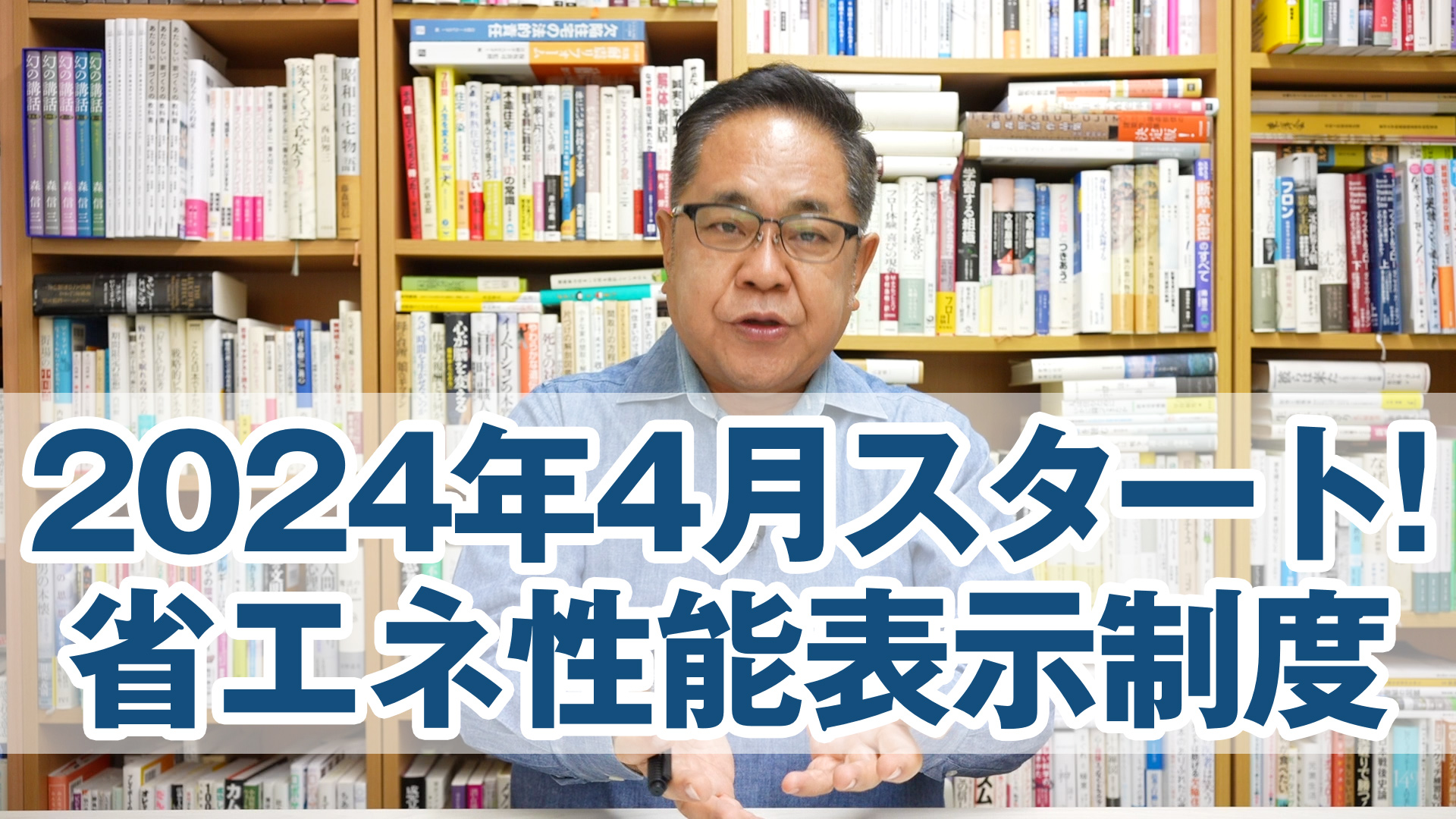広島の巨匠に会って開眼! 天窓はアリか?ナシか?
今日は、屋根につける窓、いわゆる天窓は「あり?それともなし?」というお話をしたいと思います。実は僕、前までは天窓に対してやや否定的で、積極的に使うべきなのかなと疑問に思っていたんです。でも最近、趣旨変えをしまして、なぜそうなったのか、その背景を踏まえつつ、天窓の面白さについてお話しさせてもらえたらと思います。いつものように僕の板書を見ていただきながら聞いてくださいね。旧森下は、天窓ってどうかなと考えていました。デメリットが多いとよく言われていたからです。僕の体験で言うと、実はうちの家にも天窓をつけているんですが、まず夏は暑い。日が入って暑い。一方、冬は日が入れば暖かいんですけど、太陽高度が低いから入りにくい。昼間は良くても、日が陰った途端に当時の仕様だとガラス1枚みたいな感じで冷気が伝わって、温めた空気が逃げるような寒さを感じる。寒い時期は中がうっすら結露して、木部が黒ずんだり、メンテナンスがうるさい印象もありました。今は二重にしてだいぶ減りましたが、雨仕舞いの不安から「開かない仕様にするか…」と悩むこともあって、雨漏りの話もよく聞いた。ハウスメーカー時代の記憶では、天窓をつけた方が雨漏りしたという事例がちらほらあり、どうしても否定的になっていたんです。
ところが先日、広島の“巨匠”からいろんなことを教わった時に、「天窓はいいですよ」とズバッと言われました。どんな方かというと、高気密・高断熱を掲げて勉強している団体「新住協」の創設時から関わる、いわばチャーターメンバー級の重鎮。机上の空論ではなく現場主義で、長い経験と工夫の蓄積がある、本当に実践家の方です。僕の大親友の小暮さんが「絹川親分ってすごい人がおるんや」と紹介してくれて、「森下さん、ぜひ会ってみたら勉強になる」と言うので伺ったら、これがもう、全然偉そうじゃなくて独特の語り口。僕も広島に10年ほど住んでいたので、広島弁で「こういうふうにやりんさいや」と、ごついけど温かい感じで。僕が「天窓どうなんすかね」と言うと、「そうなん?森下くん、そんなこと思っとるんか。わしは天窓が大好きなんじゃ」と。70代の先輩が「大好き」とおっしゃるなら、これはただ事じゃない。しかも「広島の街にはぴったりなんだよ」と。正直、僕はハウスメーカー時代の経験から天窓に苦手意識があったので意外でしたが、話を聞いて納得がいきました。
広島って都会で、川の三角州にできた町です。川が何本もあって湿気も多く、都市部だから高い建物もいっぱいある。そんな中で戸建てが南に高い建物の影になるケースがあるんですが、この時に天窓が救いになる。実は、たとえ前方に建物があっても、乱射・反射があるから南窓にも光は入ってくる。そこに天窓を組み合わせるとすごく重宝する。さらに、北側の天窓は非常に安定した光が取れるので、とてもいい。自然光は健康的で開放感が出るし、都市部で1階に掃き出し窓を作ると防犯やプライバシーが気になるけれど、天窓ならそこを確保しやすい。建築基準法の採光計算でも、同じ窓面積なら天窓は壁付け窓の3倍の採光扱いが認められているくらいで、たっぷり光が入るんです。通風性も工夫すれば、同面積の壁窓より4倍風を通すことができる組み合わせがある、と。しかも見える屋根に天窓をつけるデザインもかっこいい。外観が締まるし、何より内観がかっこよくなるんだと。はて、どういうこと?と思いましたが、例えば南の天窓から降り続ける光は、朝・昼・夕方で角度が移ろい、まるで日時計のように室内の光の表情が変わる。光が織りなす空間の雰囲気が美しい、と。もちろん、ソファに直撃して特定の時間帯に眩しいなどの懸念はあるから、そこはプロがシミュレーションしてヘッジする。上手に設計すれば、これほど楽しいものはない、とおっしゃっていました。
メンテナンスについて僕が「面倒じゃないですか?」と聞くと、「それは確かに。厳格にやらないと弱点には変わらん」とはっきり。けれど「良さと引き換えに10年に1回のオーバーホールは必要。嫌ならやめなさい」と、広島弁のテンポで明快でした。雨漏りの懸念についても、いろいろ試行錯誤した結果、ベルックスさんというメーカーの天窓に巡り合い、選択として非常に有効だと感じるようになったそうです。かつての大手メーカー品で雨漏りが多かったのは、施工の問題なのか当時の納まりなのか、今となっては定かではないけれど、印象としては「結構漏れてた」。その点ベルックスは非常に優秀で、経験的にきちんと納めればまず心配ない。10年に1回のオーバーホール時にも過去の部品がちゃんと揃う。そういう意味でも良いメーカーだ、と評価されていました。
また、「夏の日射で暑いんちゃう?」という“嫌がられる元”については、ベルックスさんあたりの今どきの天窓は日射カット72%、紫外線カット96%くらいで、しっかりしているからそんなに暑くないよ、と。過去の経験にとらわれたり勉強不足だと、昔のイメージで語ってしまうから要注意だと、僕もドキッとしました。さらに、もし夏の日差しがきつい場面でも、今は天窓自体に電動ブラインドがあるので、それを閉めれば暑さはほぼ抑えられる。だから“短所”と決めつけるのは違う、という認識に改めた方がいいんじゃないかな、と。仕様も、電動・手動に関わらずパコッと開くタイプもあれば、フィックスもある。ただ、フィックスを選ぶのは、例えば1階北側で日が当たりにくい場所を明るくしたい時など限定的で、大概は開けられるタイプを選ぶ、と。ルーフウィンドウという、ワーンと大きく開く感じのものもあって、吹き抜けの一番上に付け、パコンと開ければ、夏の熱気溜まりがスーッと逃げて涼しくなりやすい。熱も湿気も抜ける。高気密・高断熱で冬の日射取得がバッチリだと、晴れた日にオーバーヒートすることがあるんですが、その時もこれをリモコン電動にしておけば一発で熱気を排出でき、家じゅうの窓を開けて回る必要がない。取り付け方向も、勾配に対してこう開くか、こう開くかで性格が変わる。高台側に向けて開けば春秋は涼しい風がスムーズに入る一方、夏は下手に開けると湿気がドバーッと入ってくる今の日本では要注意。要は“暴れ馬”。どこにどう効かせるかが腕の見せ所で、上手に乗りこなせばこれほど頼もしい相棒はいない、というわけです。
なるほどなと僕も腑に落ち、プランニングの選択肢として積極的に検討するようになりました。実際の建物で設計提案だけして、いろいろなご事情でボツになってしまった案件がありますが、参考にご紹介します。平面は1階がこう、2階がこうという構成で、南側に台所があり小さな窓のみ。北側は広い道路で開けているけれど、東西は家が建て込んでいて、1階は光が取りにくい。2階は南からはある程度入るものの、プランが南北に長く、北側採光は期待できる一方で真ん中の部屋が暗くなりやすい。これは個人情報の兼ね合いから元案は出せませんが、僕の修正案では、2階階段ホール(内観パースの7あたり)に天窓を設けました。斜めからの内観(5)でも天窓の雰囲気が分かると思います。ここから光を落として、2階真ん中の部屋をしっかり明るくする。さらに吹き抜けを切って、1階のリビング側(内観1・2)にも上から光が降り注ぐようにしています。これは南側に高い建物があっても、天窓を切ることで実現できる。空調を上手に計画すれば、1階・2階の熱気は最終的に2階の天窓付近に溜まるので、そこで開放すれば風の出入りも良くなる。これが形になっていれば、とても素敵な家になっていたんじゃないかなと思います。
今後は僕も、壁面窓でうまく明かりが取れないお家には、都市部であれば特に天窓を積極的に提案したいなと思っています。もちろん都市部に限らず、郊外でも使い方次第で面白い空間が作れる。以前は僕自身、否定してきた1人なんですが、今は「あり」。費用感としては、ベルックスの天窓でだいたいフィックスが10万円くらいから、電動だと高いもので20万円くらい、ルーフウィンドウは30万円くらい。工事費で前後はします。例えば20万円のものを2か所で40万円、でも立派な3枚建ての大開口をつけたら同程度かそれ以上かかることもある。天窓もトリプルガラス仕様が選べたりしますから、うまく組み合わせれば、都市部でも光の内観を楽しめる素敵なお家ができるはずです。もしよかったら、「天窓もあり」という目線で考えていただくと、家づくりがもっと楽しくなるかなと思って、今日はお話ししました。