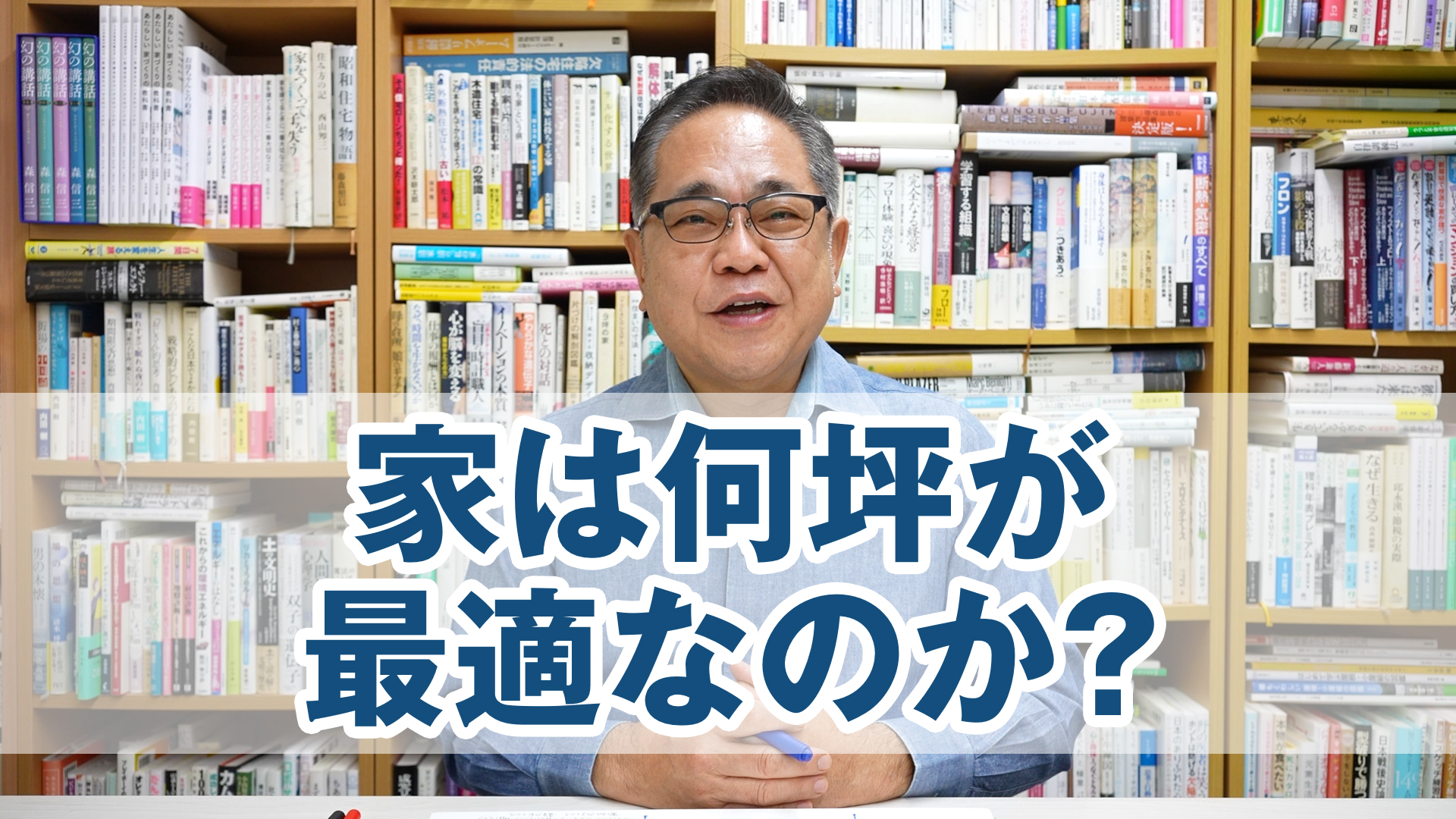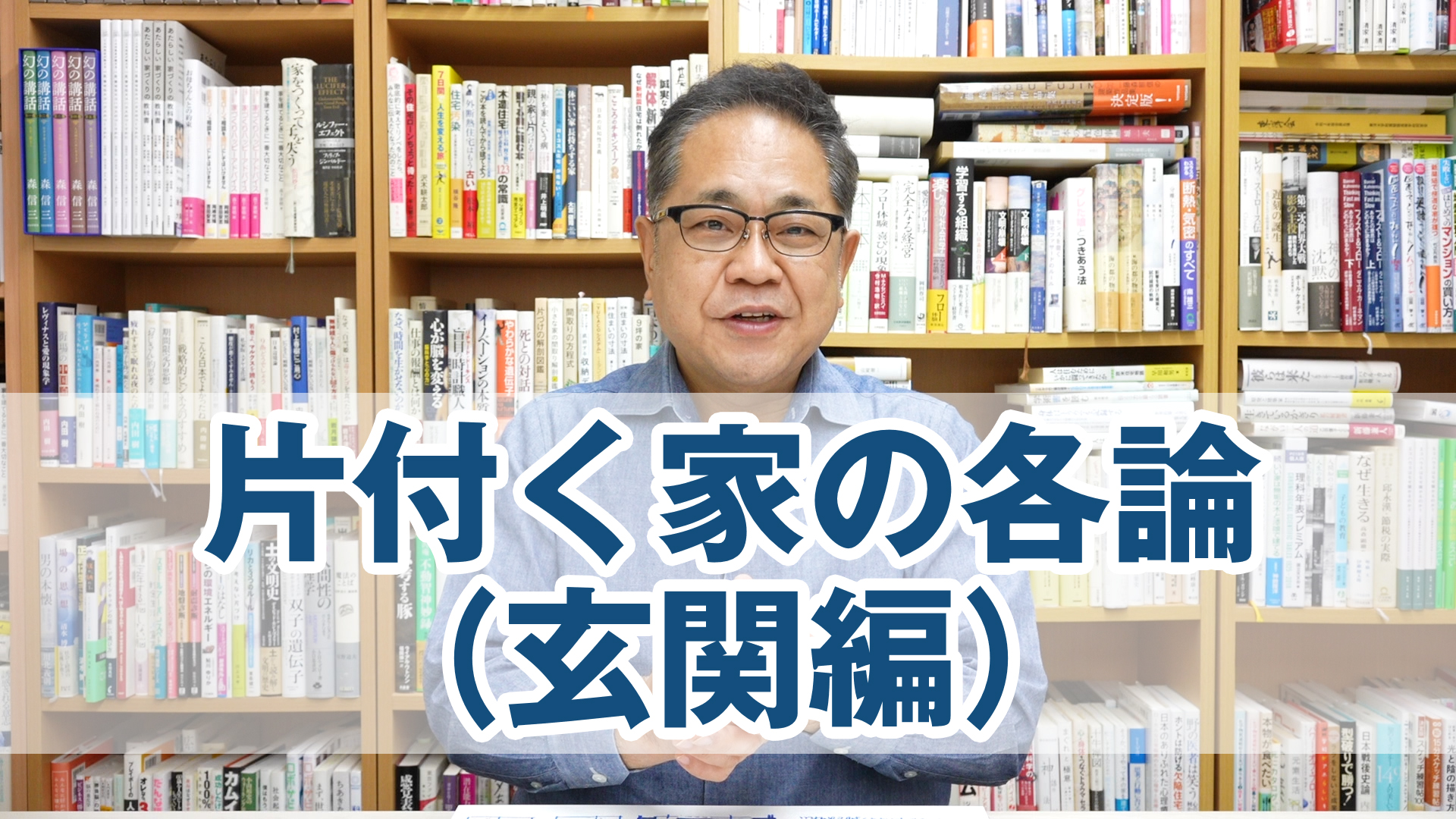詩人で建築家の夢「ヒアシンスハウス」を考察する
今日は以前ご紹介した「スミレアオイハウス」、別名“9坪の家”という建物についての続きのお話です。このスミレアオイハウスの動画を見てくださった方から、「森下さん、次はスミレアオイハウスだけじゃなくて、ヒアシンスハウスという家もぜひ取り上げて解説してほしい」とご要望をいただきました。そこで今回は、「詩人であり、かつ建築家の夢として生まれた小さな家、ヒアシンスハウス」について、解説と考察を交えながらお話ししていきたいと思います。タイトルからして可愛らしい家ですよね。ヒアシンスと聞くと花を思い浮かべる方も多いと思いますが、その名の通り“花のような家”なんです。写真をご覧いただくとわかる通り、とても小さくて可愛らしい。少しメルヘンチックな印象もあって、昭和のおじさん世代が扱うにはちょっと気恥ずかしいくらいかもしれません。でも実際は、埼玉県の別所沼という美しい沼のほとりに建つ小さな小屋なんです。
このヒアシンスハウスは、スミレアオイハウスの施主である萩原さんがエッセイとして取り上げたことでも知られています。1999年にスミレアオイハウスが建ち、その少し前の1995年には、建築家・藤森照信さんが「タンポポハウス」という自邸を建てられています。あの“トトロの家”のようなユーモラスな建築で有名な方ですね。スミレアオイハウス、タンポポハウス、そしてヒアシンスハウスを合わせて「花ハウス三部作」と呼ぶ人もいるそうです。ではそのヒアシンスハウス、どんな家なのかというと、僕が描いた拙いスケッチで説明しますと、だいたい10尺×20尺、約5坪ほどの小さな小屋なんです。南側から上がって右に入ると、長いテーブルと腰掛けがあって、まるで仲良しの大人4人がひそひそ話をしているような空間。そして北側には大きな窓があり、別所沼の向こうに広がる林が見える。横にはベッド、東側にはコーナー窓があり、それをガッと開けると、まるで「夏の扉」が開くように目の前に沼が広がります。これは建築好きならピンとくると思うんですが、建築家レイモンドの「夏の家」へのオマージュなんです。
この建物自体は2004年に建てられた比較的新しいものなんですが、その原案となる設計を描いたのは、なんと詩人であり建築家でもあった立原道造さんなんです。彼は1914年生まれ、大正3年生まれですから、ずいぶん前の人ですね。東京帝国大学工学部建築学科を卒業し、学内で最優秀とされる「辰野賞」を3回も連続で受賞したという超エリート。彼の1年後輩があの丹下健三さんですから、そのすごさがわかりますよね。丹下さんが「立原先輩はすごい」と尊敬していたくらいの存在なんです。そして驚くことに、彼は詩人としても一流でした。1938年には中原中也賞を受賞。中原中也といえば「汚れちまった悲しみに」で知られる詩人ですが、その名を冠した賞を若くして取るほどの才能です。しかも師匠は室生犀星。谷崎潤一郎や芥川龍之介らと並ぶ文学界の巨匠ですよ。建築でも詩でもトップクラス、しかもイケメン。そりゃ伝説になりますよね。
でも彼は残念ながら卒業後すぐ、1939年に当時不治の病といわれた肺結核で亡くなります。25歳という若さでした。学生時代、彼は親しい友人や詩人仲間に「いつかこんな小屋を建てたい」と語り、スケッチを何枚も残していたそうです。その夢のスケッチをもとに2004年、仲間たちによってヒアシンスハウスが現代に復元されたというわけです。名前の“ヒアシンス”にも意味があります。ギリシャ神話の美少年ヒュアキントスが太陽神アポロに愛され、嫉妬した西風の神ゼピュロスに殺され、その血から咲いた花がヒアシンス。美しくも儚く、そして悲劇的な物語です。立原さんがこの名を選んだのは、自身が病を抱えながらも、美しい詩や建築を生み出そうとしたその想いと重なっていたのかもしれません。
彼のスケッチには、机の上の燭台、椅子の形、コーナー窓の十字のモチーフまで丁寧に描かれていました。まるで詩人らしい繊細なデザインで、「俺はこんな小屋に暮らしたい」と夢見ていたんでしょう。ただ実際のスケッチにはキッチンや風呂はなく、トイレが小さくついている程度。つまり“自立した家”ではなく、生活のための機能をそぎ落とした、詩人の夢の空間なんですね。後にこの家を復元した「ヒアシンスハウスをつくる会」の方々も、きっと立原さんはこの小屋の周囲に共有の場――たとえば銭湯や共同キッチンのようなもの――を想定していたのだろうと考えたそうです。いわば一つの“離れ”、あるいは“コテージ”のような位置づけだったのかもしれません。日本でいうと、鴨長明の『方丈記』に出てくる方丈の庵にも通じるものがあります。
つまり、ヒアシンスハウスとは、日本的な感性、ギリシャ神話の儚さ、そして西洋建築の理想が融合した、小さな詩的空間なんです。若くして病を抱えながらも、美しいものを信じた詩人の夢が形になった――そう思うと胸が熱くなりますよね。この家は2004年11月に再建され、今も別所沼のほとりに静かに建っています。萩原さんはスミレアオイハウスの設計にあたって、このヒアシンスハウスの精神を“離れ”という形で受け継いだといいます。究極の住空間の中に小さな豊かさを象徴する“離れ”がある。立原さんは、そんな世界を夢見ていたのかもしれません。
立原さんの書いた論文には少し難しい言葉が並びますが、萩原さんが見つけた一節にこうあります。「住みよいという言葉で表される建築体験があるけれど、それ以上に“住み心地よい”という体験が区別されるべきだ」と。つまり、住むことの本質には“心地よさ”という感性がある。それがたとえ青臭くても、夢のようでも、そこにこそ人が惹かれるのだということなんです。
ヒアシンスハウスはたった5坪の小さな建物ですが、中に入ると誰もが「狭くない」と言うそうです。それは北側の大きな窓や、東南のコーナー窓の開放感によって、内と外が自然につながるから。性能重視の今の家づくりでは、窓を小さくする傾向もありますが、本当の豊かさは“外とつながること”にある――それをこの小さな家が教えてくれる気がします。
そして、うちの山下社長が今、新しいモデルハウスを計画しているんですが、そこにも“離れ”という概念を取り入れています。ヒアシンスハウスとはまた違う形で、山下流の解釈を加えたガレージ付きのコテージのようなモデルハウスです。2026年1月にオープン予定とのことですので、家づくりを考えている方は、ぜひ一度“体験”してみてください。大きくて立派な家だけが豊かさではなく、小さな空間の連なりが生み出す暮らしの面白さ――そんなことを感じていただけると思います。