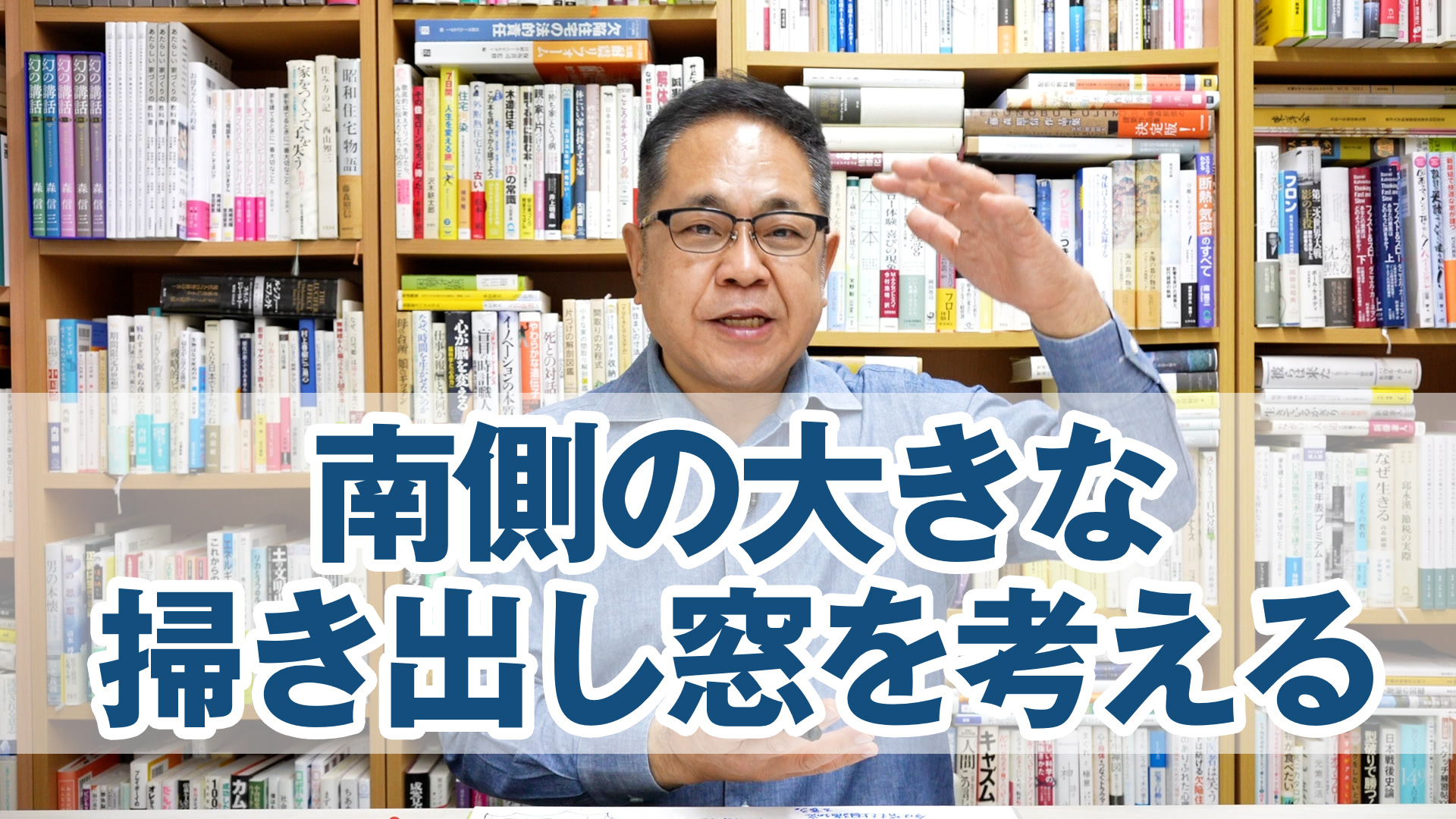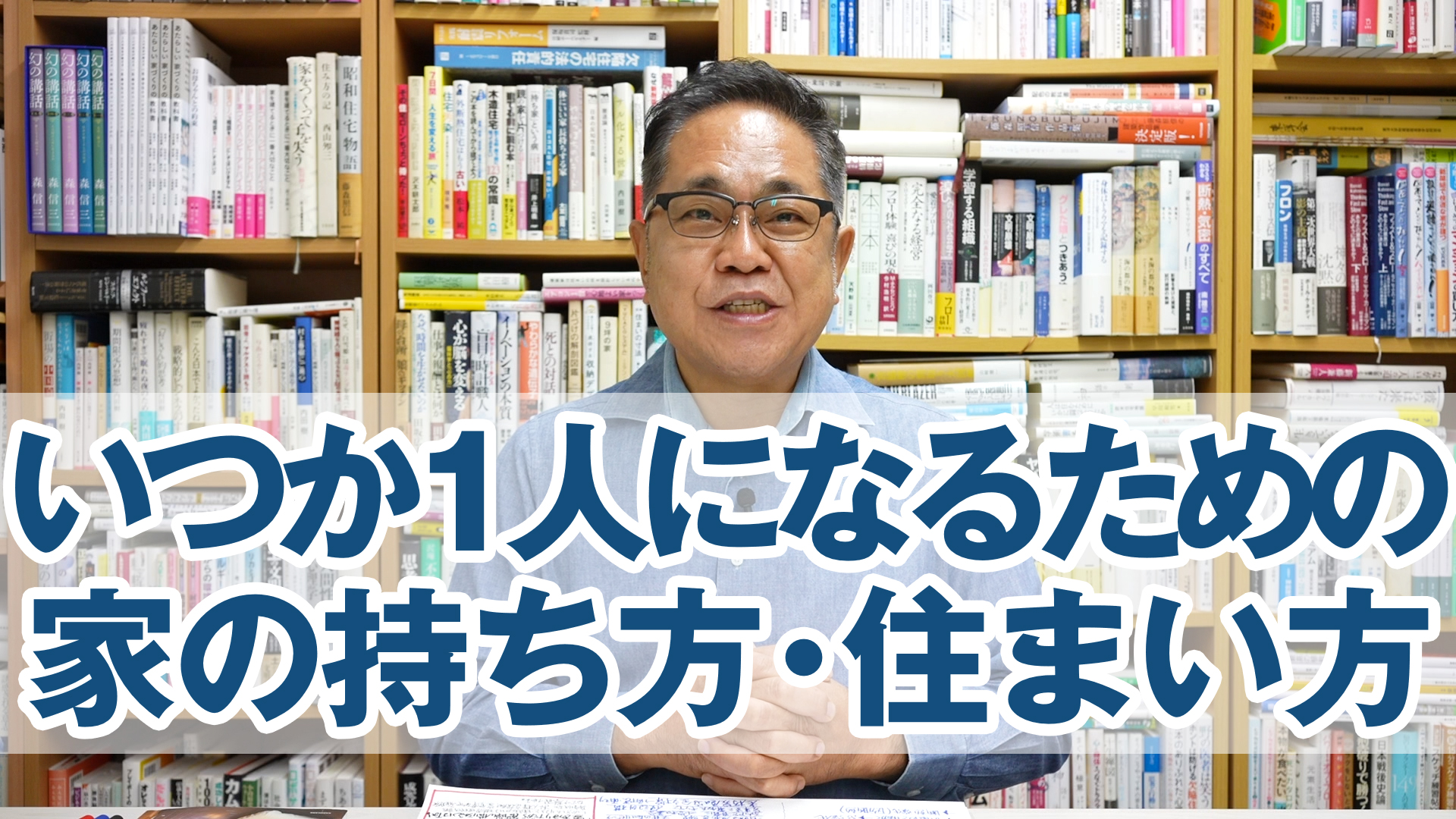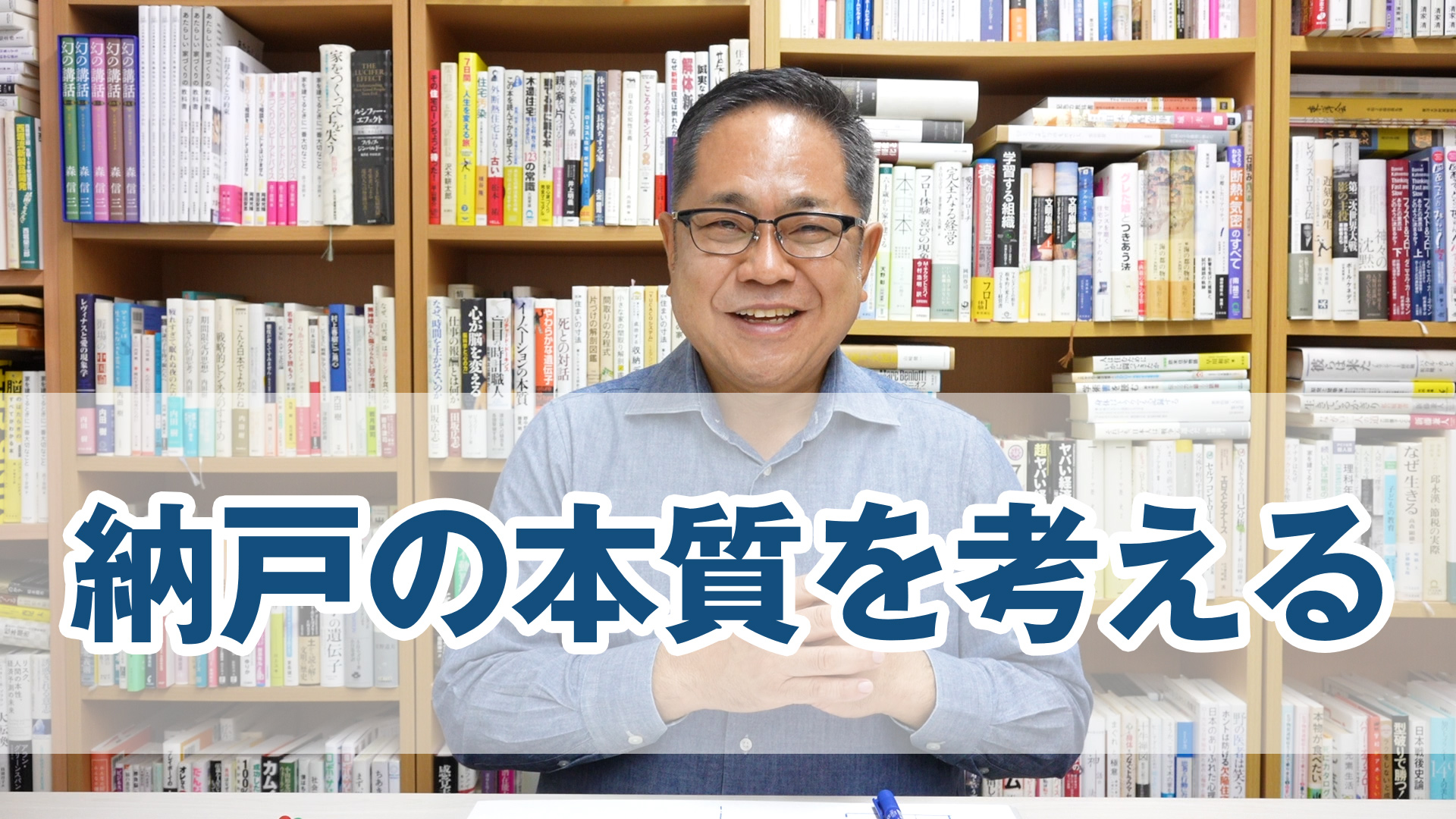設計と施工はどちらが大事なのか?
今日は先日、ある若いお客様から「建築の世界では設計と施工という言葉をよく聞きますが、どちらがどういうふうに大事なんですか?」という質問をいただきました。これから家づくりをされるにあたって、少し不安もあったのかもしれません。そこで今日は、僕なりに感じていることを、いつものように板書を交えながらお話ししていきたいと思います。
まず「設計」という言葉ですが、僕は大きく分けて2つあると思っています。ひとつは基本設計。住宅でいえば、家をどう配置するか、どのくらいの大きさにするか、間取りをどうするかといった大枠の計画です。さらに外観デザイン、階高(1階・2階・屋根の高さ)、UA値(断熱性能の指標)、耐震等級などの性能面も含まれます。光熱費などのランニングコストや、外壁・屋根の素材選びによるメンテナンスコスト、内装の仕様や設備、自然素材か新建材かといった選択もすべて基本設計の範囲です。さらに庭や外構、中間領域(家の内でも外でもない豊かな空間)といった部分も重要な要素になります。
もうひとつが実施設計(詳細設計)です。これは基本設計で決まった内容をもとに、具体的な施工図面を描く工程です。例えば展開図では部屋の4面それぞれに窓やドア、本棚の位置、高さなどを細かく記します。建具表や施工詳細図、収まり図も含まれます。鉄筋コンクリートの基礎なら、鉄筋の太さや長さ、継手の位置、アンカーとの干渉など、現場で実際に組めるかどうかを確認します。設計図だけでは物理的に収まらない場合もあるので、現場の制約を踏まえた施工図に落とし込む必要があります。こうした作業は設計者と施工者が密にやり取りし、相互に乗り入れるような領域です。施工者が描いた方が合理的な場合もあれば、設計者が現場で学びながら描くこともあります。
次に施工の段階ですが、ただ図面通りにつくるだけではなく、品質を確保するための管理が必要です。管理には大きく分けて2つあり、ひとつは設計監理。これは基本設計を担当した設計者がお施主さんの代理として現場を見て、図面通りか、品質が守られているかを確認します。もうひとつは施工管理。これは現場監督や施工者が自主的に品質をチェックし、問題があれば是正します。さらに第三者機関による検査もあり、鉄筋の配筋、防水、金物の固定など重大な品質項目を確認します。ここでミスがあると、いくら設計が良くても性能は発揮されません。断熱材が隙間なく入っていなければUA値通りの性能は出ませんし、気密性能(C値)も現場の精度次第です。耐震性能も、指定通りの金物や釘が使われていなければ意味がありません。
では「設計と施工、どちらが大事か?」という問いですが、僕の答えは「どちらも大事」です。家づくりの両輪ですから、片方が良くても片方が悪ければ意味がありません。この議論になると「設計・施工を一貫してやるか、分離するか」という話になります。僕たちの工務店は一貫して行っていますが、分離方式にも利点があります。設計者と施工者を分ける場合は、設計者が現場をよく理解し、本当に監理できるかが鍵です。現場任せで尖ったデザインだけを優先すると、雨仕舞いが甘くなって雨漏りの原因になることもあります。コーキング頼みの収まりでは、10年後に劣化して不具合が出る可能性があります。理想的なのは、設計者と施工者が基本設計の段階から関わり、実施設計を見て「これで現場が収まるか」を確認し合い、お施主さんの利益を守る形です。
基本設計は「家という器」を決める工程、実施設計は「質」を決める工程だと僕は思っています。この2つが融合して初めて、良い家ができる。そして施工段階では、それを正しく形にする力が求められます。一貫方式の強みは安全側に立てることですが、その反面、尖ったデザインを避けがちになる弱点もあります。逆に設計事務所はデザインの自由度が高い反面、施工任せになるリスクがあります。だからこそ、お互いが歩み寄り、立場を超えてお施主さんの利益を守る姿勢が必要です。尖ったデザインであっても、雨仕舞いや耐久性の根拠をしっかり持ち、設計と施工が協力して実現する。それが一番美しく、お客様に喜んでもらえる形だと思います。