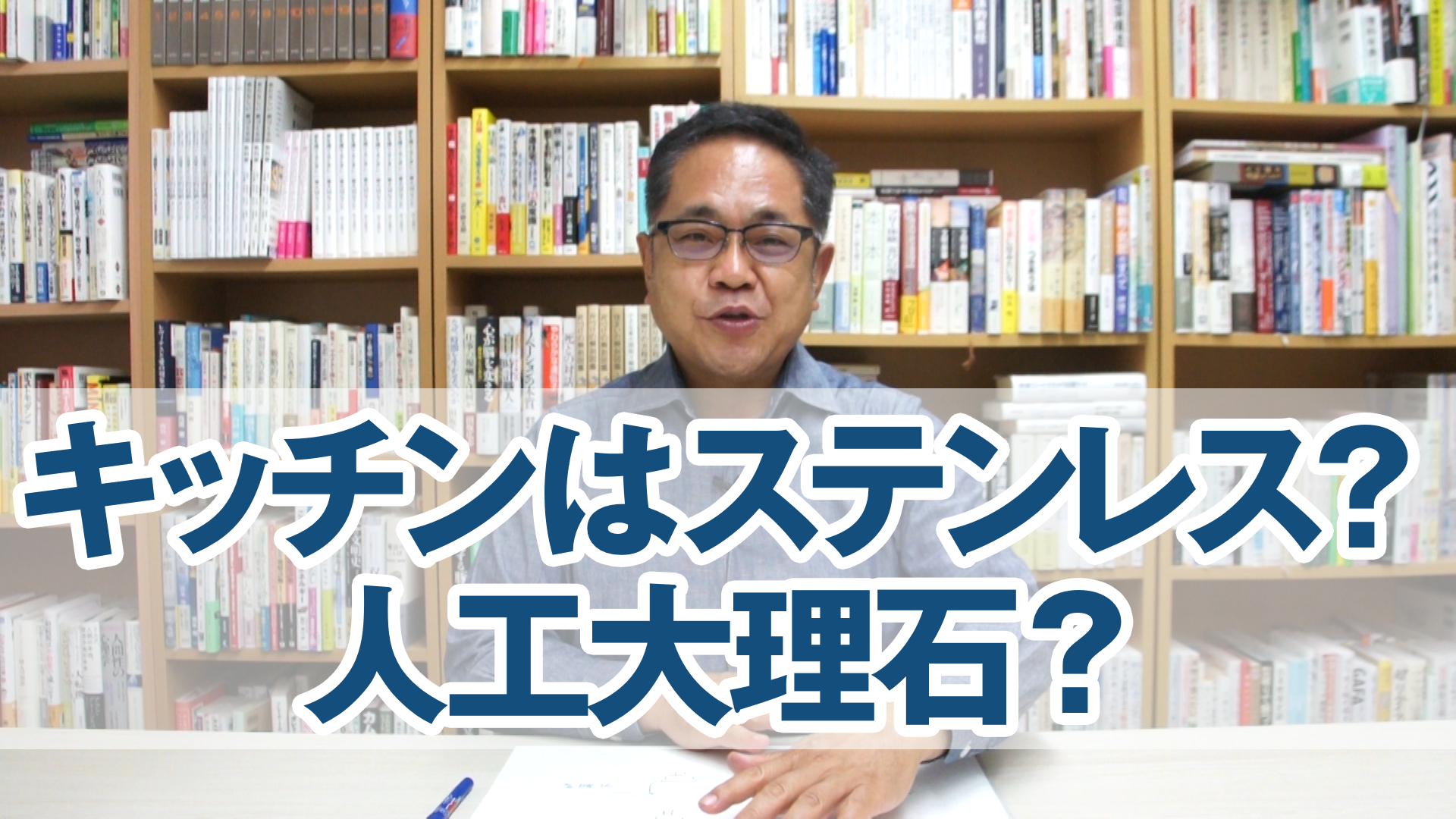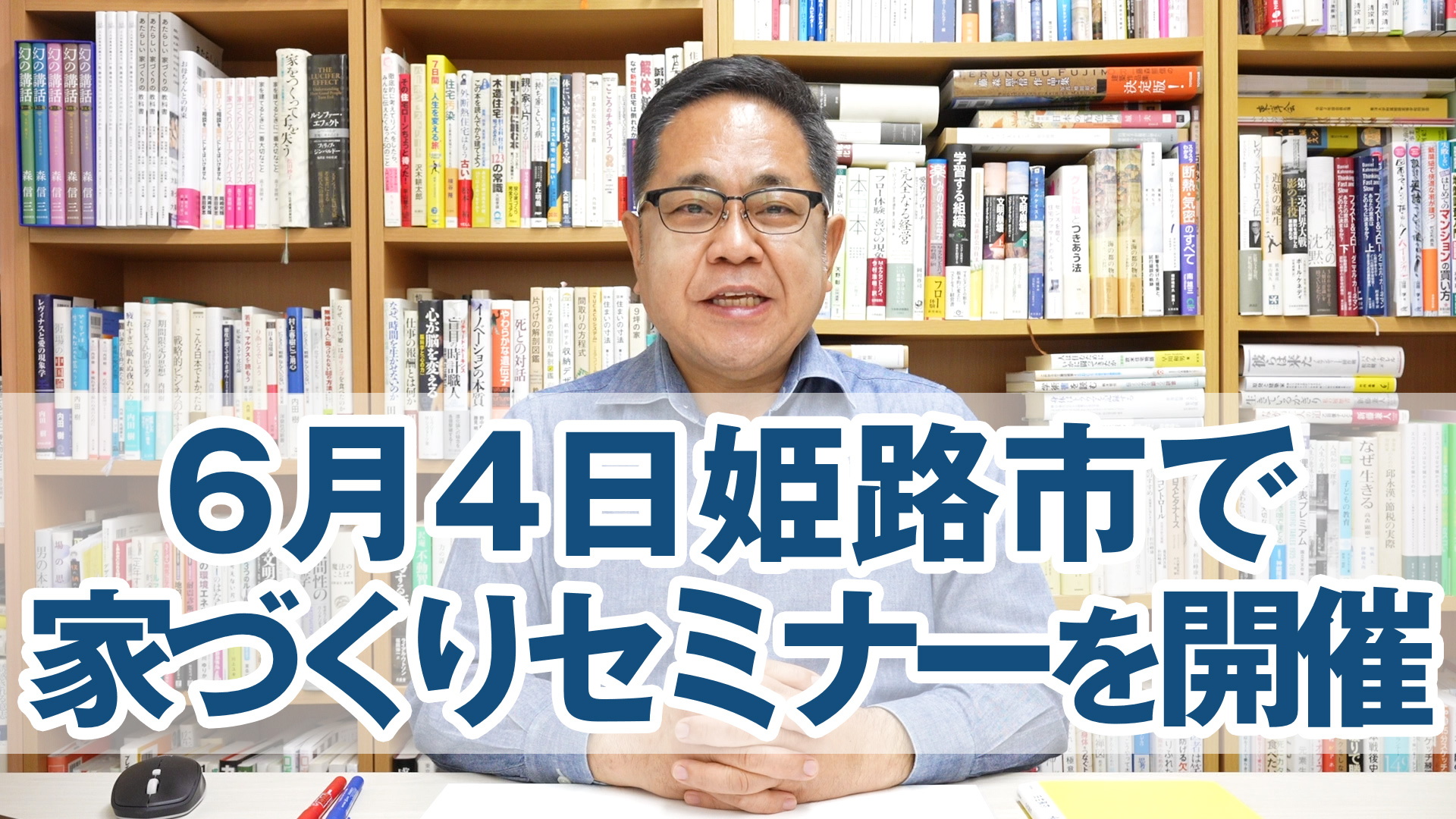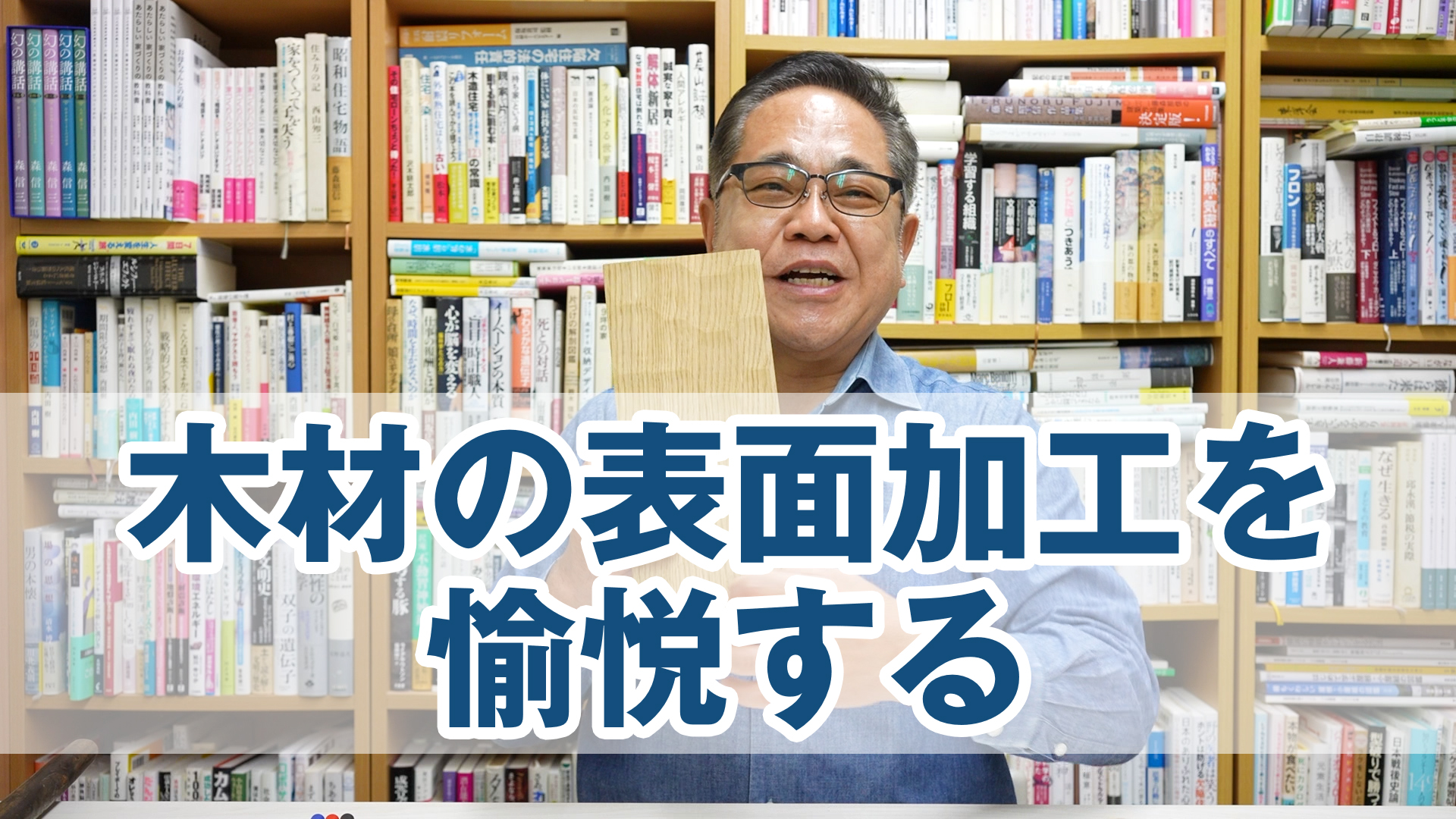来年に備えてGX補助金の35%省エネの基本を知る
▼エネルギー消費性能計算プログラム
https://house.lowenergy.jp/program/
▼松尾先生の動画
https://youtu.be/95DuuPSjMwQ
今日は、今年いろいろ話題になったGX補助金についてお話ししていきたいと思います。みなさん、GX補助金ってご存じですか?正式には「GX志向型住宅に対する補助金」と言われるもので、新築を計画されている方がある一定の要件を満たすと、1棟あたりなんと160万円の補助金が出るというものなんです。160万円って、かなり大きい金額ですよね。これが発表された時は「えらいこっちゃ!」と一気に注目が集まり、皆さんこぞって申請されたんですが、残念ながら今年の11月くらいまでは続くと思われていたこの補助金、7月22日の時点で予算達成となり、「これにて打ち止めです」となってしまいました。つまり、「さあ使おう!」と思っていた方々にとっては、まるで冷や水を浴びせられたような結果になってしまったんですね。
ただ、今日は「もう終わった話をなんで今?」ということではなく、この出来事の背景や意味について少し掘り下げてお話ししていきたいと思います。まず、このGXという言葉、聞き慣れない方も多いと思います。「グリーントランスフォーメーション」、つまり脱炭素社会への転換を意味していて、世界的に“もうやらなあかん”という流れの中で、日本も取り組みを強化しているわけです。これまではZEH(ゼロエネルギー住宅)という言葉が先行していましたが、経産省主導だったものが、今回は国土交通省や環境省も加わって「脱炭素社会に向けて国全体でやっていこう」という動きになったんです。
このGX志向型住宅というのは、省エネ性能の高い住宅を広めることを目的にした制度です。中でも「子育てエコホーム支援事業」という枠組みの中で展開されていて、長期優良住宅を建てれば80万円(子育て・若年夫婦限定)、ZEH水準なら40万円、そしてGX志向型住宅を建てれば160万円という形になっています。しかもGX志向型だけは、年齢制限なし。シニア世代も対象なんです。国としては、省エネ性能の高い、資産価値のある住宅を増やしていくことが目的であり、炭素削減という社会全体の課題にも貢献してもらおうという狙いがあるんですね。
では、このGX志向型住宅ってどんな要件なのか。4つあります。まず①断熱等級が6以上。今の標準が4なので、そこから約30%の省エネ性能が求められます。②太陽光発電を除いた一次エネルギー消費量を35%以上削減。つまり、設備などの工夫で断熱以外に5%の省エネを稼ぐ必要があります。③太陽光発電を含む一次エネルギー削減が100%以上、つまりZEH相当。④それらを効率よく制御する「HEMS(ヘムズ)」というエネルギーマネジメントシステムを導入していること。この4つを満たした家がGX志向型住宅として認められ、160万円の補助が出るというわけです。
今年度分は終了してしまいましたが、来年以降も似たような補助が継続する可能性は十分にあります。だからこそ、これから家を建てようという方は、このGX志向型住宅という考え方をしっかり頭に置いておくと良いと思います。実際の性能確認には「エネルギー消費性能計算プログラム(WebPro)」を使います。国交省が公開しているサイトで、誰でも無料で見られます。自分の家がGX補助の対象になるレベルかどうかをシミュレーションできる便利なツールなんです。僕の師匠である松尾先生も、素人の方でもこのプログラムを使えば自分の家の性能がある程度チェックできると紹介されています。先生の動画も概要欄に貼ってますので、ぜひ見てみてください。
さて、ここからが今日の本題です。最近、僕たちの住宅業界では、一条工務店さんのように「高性能住宅を当たり前にしよう」という動きが広がっています。それ自体はとても良いことなんですが、他の大手ビルダーさんもこぞって高性能化を打ち出す中で、少し“やりすぎ”とも思えるオーバースペックの家が増えてきているんです。特に僕が住む兵庫県の姫路市のような温暖地では、そこまでの性能が本当に必要なのか?と疑問に思うこともあります。寒冷地ならともかく、瀬戸内や九州、四国などでは、過剰な性能はコストだけが上がってしまうケースもあるんです。
国が160万円も補助するのは、それだけ高性能化にお金がかかるから。でもそれを逆手に取って、「補助金が出るから高くても大丈夫ですよ」と言って、結局お施主さんの負担が減らないような売り方をしているところもあるのが現実です。本来なら、補助金は家計の助けになるべきなのに、それを口実に高額化しては意味がないですよね。だから僕は、性能を高めすぎず、必要十分なバランスを取ることが大切だと思っています。
そしてもうひとつ大事な話。僕たちが尊敬する東大の前先生も、このGX志向型住宅について「問題あり」と指摘されています。なぜかというと、気密性の基準が含まれていないから。断熱性能ばかり強調しても、気密が取れていなければ実際の快適性や省エネ性は確保できません。特に鉄骨系の住宅では気密が不十分なケースも多く、実際の性能が計算通りに出ないこともあるそうです。さらに、このWebProという計算プログラムは、断熱の省エネ効果をやや過小評価する傾向があるため、結果的に“やりすぎ”を招く可能性があるとのこと。だからこそ、「この計算通りにすれば完璧」と思い込むのは危険なんです。
では、どうすればバランスを取れるのか。例えば暖房・冷房・給湯のエネルギー効率を細かく入力したり、高断熱浴槽を選んだり、日射遮蔽をきちんと設計したりといった“小技”を積み重ねていくことです。これらを丁寧にやっていくと、大きなコストをかけなくても35%削減が十分達成できます。逆に、大技で一気に高スペック化するよりも、トータルコストは下がり、補助金160万円がまるまる活きてくるんです。
最後に少し専門的な話ですが、外皮の「ηA(イーターA)」という指標、これは太陽の熱をどれだけ取り込むか・遮るかを示すものです。夏は日射遮蔽、冬は日射取得。つまり、庇をしっかり設けたり、窓の位置を工夫するだけでも、実は性能は大きく変わります。これを怠ると、せっかくの高性能住宅も無駄になってしまうんですね。
ということで、来年以降の補助金の詳細はまだ分かりませんが、間違いなくGX志向型住宅の流れは続いていきます。これから家づくりをされる方は、「性能が高い=いい家」ではなく、「補助金を上手に活かして、バランスよく建てる」という視点を持ってもらえたらと思います。そして、メーカーさんや設計士さんに相談する際は、「WebProでうちの家の性能を具体的に説明してください」とお願いしてみてください。そうすることで、本当に無駄のない、コスパのいい家づくりにつながります。