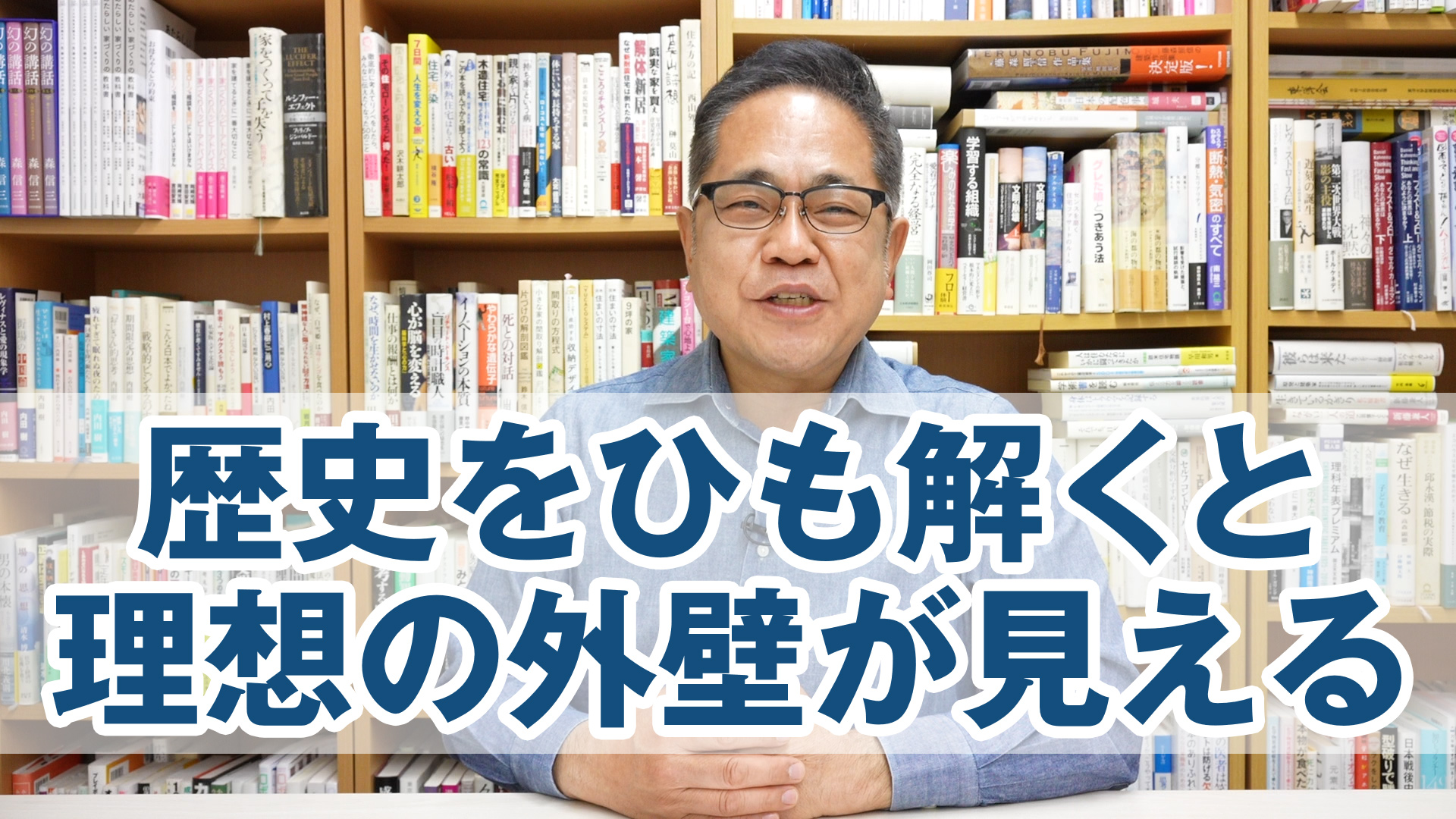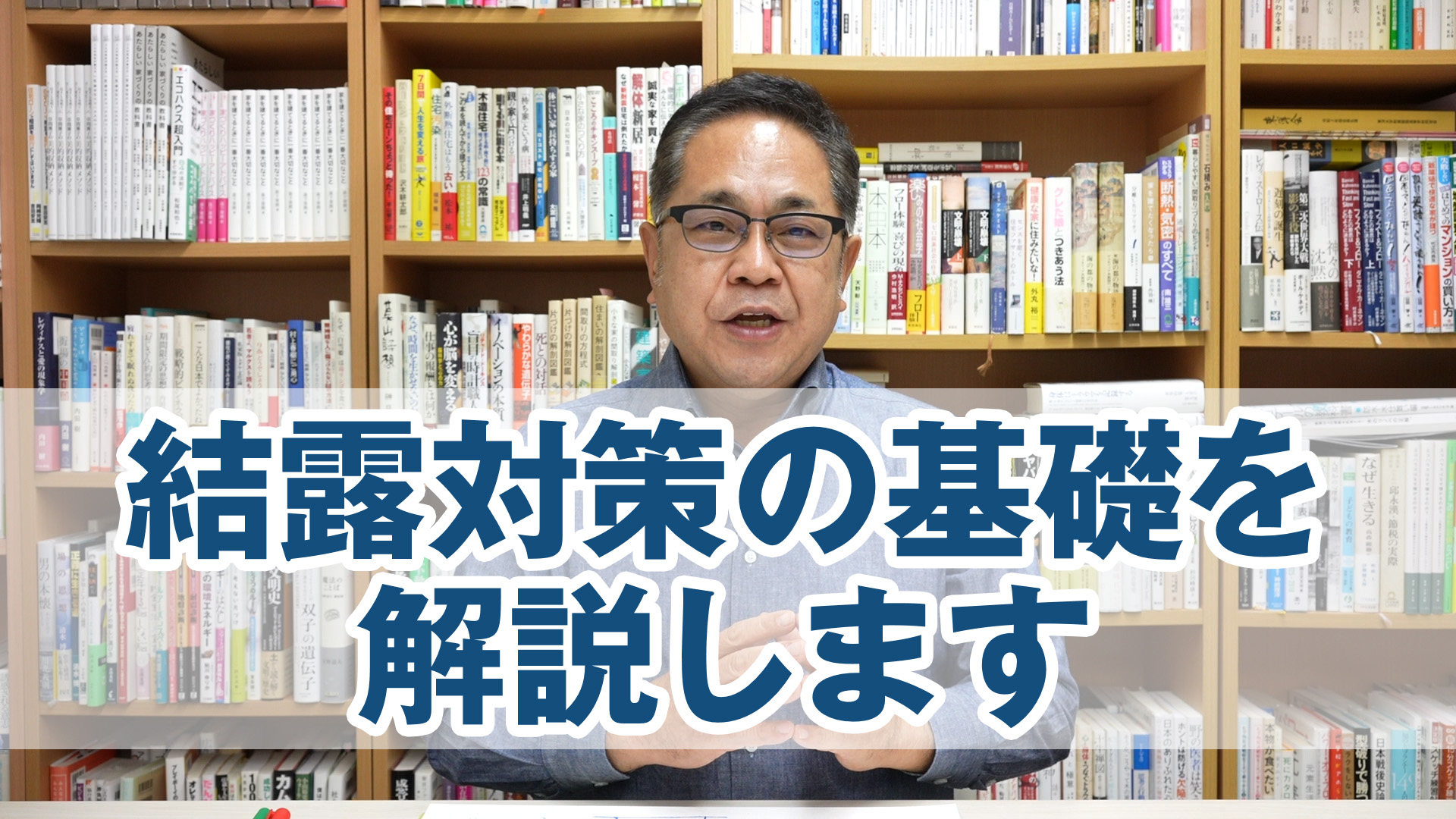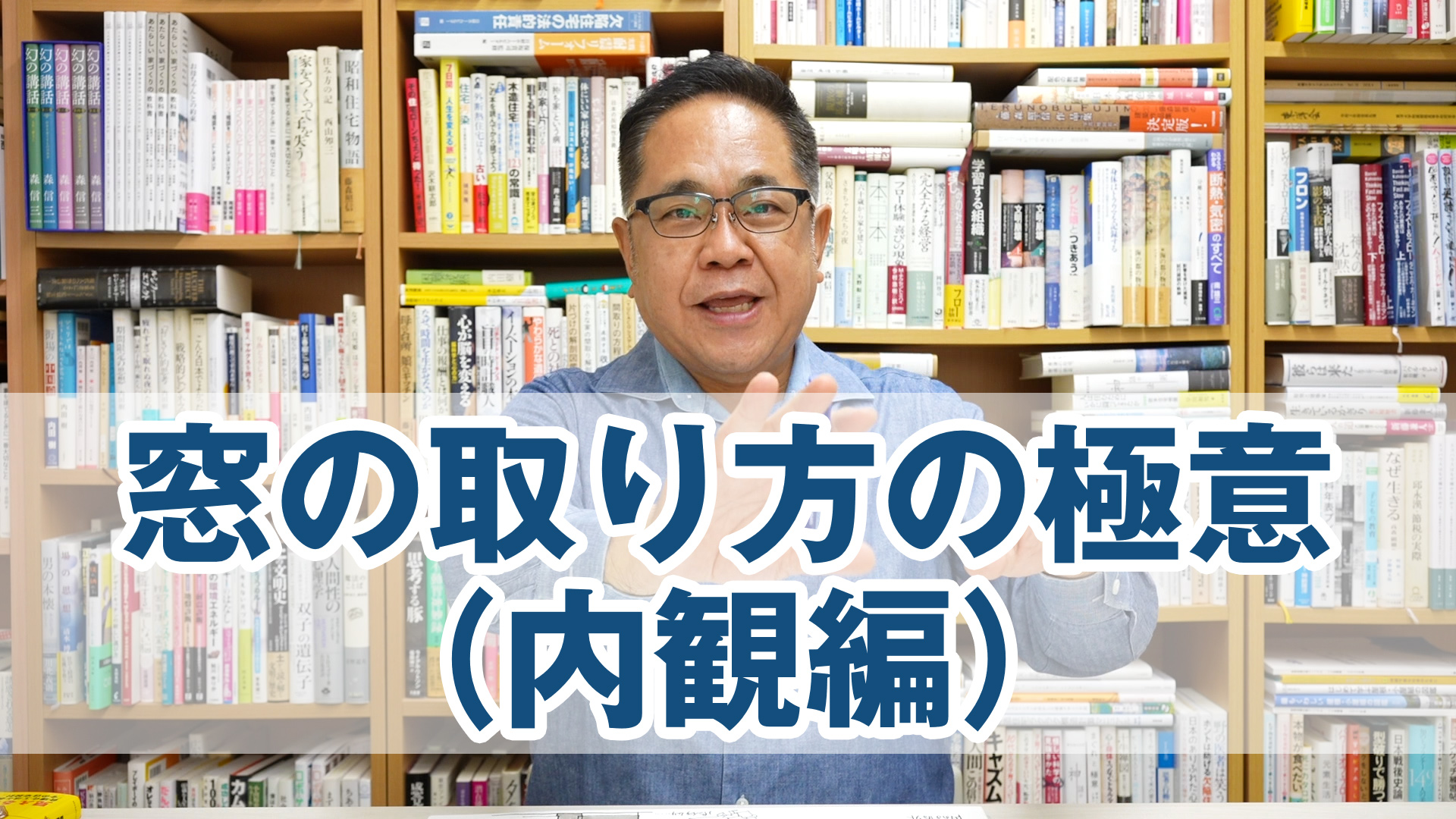住宅会社はなぜモデルハウスをつくるのか?
先日あるお客様から「森下さん、住宅会社っていっぱいあって、いろんなモデルハウスを建ててるじゃないですか。あれってなんで建てるんですか?」という、すごく素朴な質問をいただいたんです。
その問いに、僕なりに答えてもいいんですけど、最近AIにハマってまして、実はAIくんに聞いてみたんですね。「住宅会社はなぜモデルハウスを作るんですか?」って尋ねたら、ものすごい勢いで答えを出してくれました。その内容をまとめると、「住宅会社がモデルハウスを建てる主な目的は販売促進です」と。うんうん、AIが言いそうだなぁと思いながら聞いていたら、「顧客がその会社の住宅のイメージを具体的につかめて、購入しやすくするためにモデルハウスを建てています」と、これまたまっすぐな答えでした。
もう少し細かく言うと、「広告宣伝活動として、自社の住宅のコンセプトやデザイン、設備を実際に見てもらうことで、お客様にインパクトを与える」とも言っていました。ふんふん、確かにそうやなぁと聞いていましたし、「顧客の要望の明確化にも役立つ」と。どういうことかと言うと、お客様自身にも要望はあるんですけど、それが意外と曖昧だったりしますよね。当たり前です、プロじゃないですもん。なので、その要望を明確にする手助けになる、これは確かにそうやなと思いました。
もう一つは「住宅性能の体感ができる」という点です。例えば、暖かいとか涼しいといった快適さを実際に体験できるということ。もちろん、体感できるモデルハウスもありますが、大手ハウスメーカーさんの大きなモデルハウスだと空調設備がたくさんついていて、それをもって体感と言っていいのか…なんて、ちょっと意地悪な気持ちもありつつ。でも、体感できるというのも事実ですよね。
それと、「顧客の不安解消」にもつながります。図面やカタログだけではなかなかピンとこないものですが、モデルハウスを見て、しっかりしたイメージを持てることで不安が和らぎます。「こんな家になるんだな」とわかるのは、お客様にとっても、とても意味のあることだと思います。
それからAIがもうひとつ挙げていたのが、「総合住宅展示場への出店」という観点です。総合住宅展示場では、いろんな会社が出展しているので、より多くの顧客に自社の家を知ってもらえる。それにお客様側も、比較しながら購入を考えられるので、意欲が高まると。だから、住宅会社の立場でもお客様の立場でも、住宅購入の意欲を高めるためにモデルハウスを作るんだと、こういう話でした。
でも、実際にお客様にこのAIの回答をお伝えしても、たぶんあまりしっくりこなかったんじゃないかなと、話している中で感じました。そこで僕自身も改めて思ったのが、お客様が要望を明確にしたり、実際に体感したり、そういう曖昧なものがはっきりしてくるのは確かに重要なことやな、と。それと同時に、昔からよく言っていた話ですが、ちょっと揶揄っぽくなりますけど、総合住宅展示場に遊びに行くのはええけど、本気で家づくりを考えるなら、あそこに行ってもどうかな…という気持ちがずっとあるんです。
今回のご質問をいただいて、「じゃあ総合住宅展示場の最大の問題ってなんやろ?」と考えた時、僕は「方位がない」ということに気づいたんです。どの展示場も区画が分かれていて、もちろん方位自体はあるんですけど、家が方位をちゃんと意識して建てられていない場合が多いんですね。みなさんがこれから建てる土地は唯一無二の場所で、必ず方位があります。その方位に合わせて家をどう考えたらいいか、いろんな情報を集めるのが大事なんですが、住宅展示場では必ずしもそうなっていません。
例えば、展示場の敷地に駐車場があったら、一番カッコいい向きでモデルハウスが建てられている。でも、それがたとえば北向きだったりすることもあるんですね。実際の家は、周囲の環境や方位とどう調和するかが大事なのに、そこが抜け落ちている。だから、展示場で見て「カッコいい!」と感じても、自分たちの土地とは違う向きや環境で建てられているので、家の本当の意味や良さが変わってくる気がするんです。家は本来、周りの環境と一緒に考えるべきものやと思うので、展示場だけで判断するのは目くらましになるんちゃうかな、と。
もちろん、いろんなメーカーの家を見比べるには展示場もいいと思います。でも、気持ちが本気で家づくりに向いた時は、もっとリアルなもの、現実の暮らしに近いものを見た方がええんちゃうかなと、僕は思います。
今回、改めてAIの答えを見てしみじみ思ったのは、家ってもっと自然の中や街並みの中にあるものやから、そういった視点で家を見た方が、本当の意味でお施主さんのためになるんじゃないかな、ということでした。
ちょっと昔話になりますけど、2000年の話です。僕の地元に「パナホーム兵庫」さんという会社があって、ハウスメーカーさんの代理店というか協業会社さんなんですね。僕の経歴をご存知の方は笑われるかもしれませんが、大学卒業して初めて就職したのが、実は大手ハウスメーカーのパナホームさんだったんです。当時はナショナル住宅産業と言ってましたね。なので、僕にとってパナホームさんは、ちょっと郷愁があるというか、ふるさとみたいな感じもあって、今でもパナホームさんの家は気になって見てしまうんです。
このパナホーム兵庫さんの香山社長という方がいらっしゃって、同郷の方で、すごく立派な方だと聞いています。僕も尊敬する先輩のひとりなんですが、香山社長が2000年に「総展全面撤退」と発表されたんです。当時のハウスメーカーは、総合住宅展示場でお客さんを集めるのがメインだったので、「そこをやめるなんて気が触れたんかな?」と周りもびっくりしたみたいです。
香山さんはこうおっしゃってました。「総展に出して展示期間が終わったら解体せなあかん。それが忍びない。今は環境保全や資源の大切さが言われる時代に、効率のためとはいえ、短期間で壊す家を建てるってどうなんやろう。しかもモデルハウスはお金も手間もかかってるのに、やっぱりそれはやめたいんや」と。僕も聞いていて、本当に胆力ある社長やなと驚きました。
住宅って商業建築や博覧会の建物とは違います。敷地と建物の関係をちゃんと考えなあかんのやな、と改めて感じさせてもらいました。パナホーム兵庫さんは、普通の街角にモデルハウスを建てて、展示期間が終わったら気に入った方にお譲りする、だから解体しないんですね。僕の近所にもそういう展示場があって、今も個人の方が暮らしておられます。2000年から25年経った今でも、そのやり方で会社も順調にやってはる。本当に立派やなと思います。
このエピソードを通して、総合住宅展示場ってどうなんやろうと改めて思いましたし、果たして展示場から撤退して住宅会社がやっていけるのか…と、僕も社長の端くれとして考えたりもしました。でもやっぱり、家は土地の上に建つものやという、当たり前すぎることを改めて気づかせてもらいました。
それから僕は、家を押し売りするというよりも、お客様が本当に欲しいのは「家」そのものじゃなくて、「幸せな暮らし」なんじゃないか、という気持ちになっていったんですね。だから、僕自身のモデルハウスを建てる理由も、少しずつ変わっていったんです。最近よく言われる「リアルサイズ」というテーマもその一つです。身の丈にあった、実感できる本当の生活を体験できる家ですね。
例えば、80年代から2000年ぐらいまでは、ちょっと大きめの家、40坪とか45坪の家が欲しいという人が多かったです。でも2015年ぐらいからは、小さな家、だいたい100平米、30坪くらいの家がリアルサイズになってきました。45坪から30坪へと、15坪も違いますよね。そんな流れの中で、僕も10〜12年前くらいまでは、子育て世代のための家づくりをすごく考えていたんですが、途中からは、共働きで子どもがいないご夫婦の家づくり、家族の形の変化にも目が向くようになりました。
共働きの方は本当に忙しいので、家事がサクサクできることが大事だなと感じたり、ファミリータイプじゃない家も、長く住むなら大事だなと気づいたんです。そして、今63歳になって、僕も子育てを終えてしみじみ思うのは、家って「子育てのための家」というよりも、子育てが終わった後の暮らしの方がずっと長い、ということなんです。
僕も、子どもが小さい頃に家を建てた時は、仕事も忙しいし、奥さんも働いていたので、「家の周りは全部コンクリートで固めて、草が生えないようにしといて!」なんて言ってたんです。でも母親は、「緑もあった方がええで」「土の場所も残しておきや」と言って、コンクリートの上に大きな鉢を置いたり、花や木を植えてくれてました。長女が生まれた時はハナミズキを、次女の時はまた違う木を植えてくれたり、実のなる木もあったりして、当時は「せやなぁ」くらいだったんですけど、今になると「この木はお袋が長女の時に植えてくれたやつやなぁ、立派になったなぁ」としみじみ感じるんです。
また、娘が「おばあちゃん、この花なんていうの?」と聞いたら、母が花の名前や咲く時期を教えてくれていて、僕は全然知らなかったのに、娘が花のことをよく知っていたりして、庭っていいもんやなぁと感じるようになりました。こうした発見が、この歳になって本当に多くなってきたんです。この発見をお客様にも伝えたい、という思いもあって、このYouTubeのチャンネルで世間話をさせてもらっています。
最近、堀部先生がおっしゃっていたんですけど、「モデルハウスはテーマパークでなくていい」と。総合住宅展示場は、テーマパーク的な雰囲気がありますよね。現実の暮らしからちょっと離れた、夢のような場所というか。でも本来、モデルハウスを作るのはテーマパークを作りたいからじゃないと思うんです。
例えば、10区画20区画くらいの分譲地の一角に建つモデルハウスは、リアルサイズです。最終的には販売されるので、本当に現実的な家。ただ、それだけだとちょっと寂しい気もして、もう一つ「投企としての家」という考え方をお伝えしたいんです。少しアカデミックで難しい言葉かもしれませんが、「投企」というのは、ハイデガーという哲学者が使った言葉で、人間は世の中に投げ出された存在で、望まなくてもこの世界に放り出されてしまう。だからこそ、自分自身の存在を発見するために、現在から未来に向かって想像的に進むことが大事なんや、という考え方です。
平たく言うと、自分がやりたいことや世の中に問いたいことを投げかける、それが「投企」という意味です。僕ら設計者としても、せっかくお客様の家づくりに関わらせていただくなら、最近の発見や気づきを「企て」として家づくりに投げかける、そんなモデルハウスを作ってもいいんじゃないかなと思うんです。
例えば、松尾先生の家を見に行ったり、飯塚先生から「中間領域」の意味を教えてもらったりする中で、「家づくりの発見」がどんどん増えていくんですね。それを、うちのお客様やご縁のあった方に「こんな発見がありましたよ」と、やさしく問いかけてみる。それができたら素敵やなぁと思います。
そして、「この敷地にはどんな発見があるのか」という視点で家づくりができれば、土地探しも理想だけじゃなくて、ご縁があった土地の素晴らしさや長所を発見して、その上で家を建てられる。そうすると、その家は唯一無二の素晴らしいものになるんじゃないかなと思うんです。
こんなふうに、工務店さんや住宅会社が作るモデルハウスとうまく付き合っていくのも面白いかなと思いますので、今回の話も何かの参考になれば幸いです。