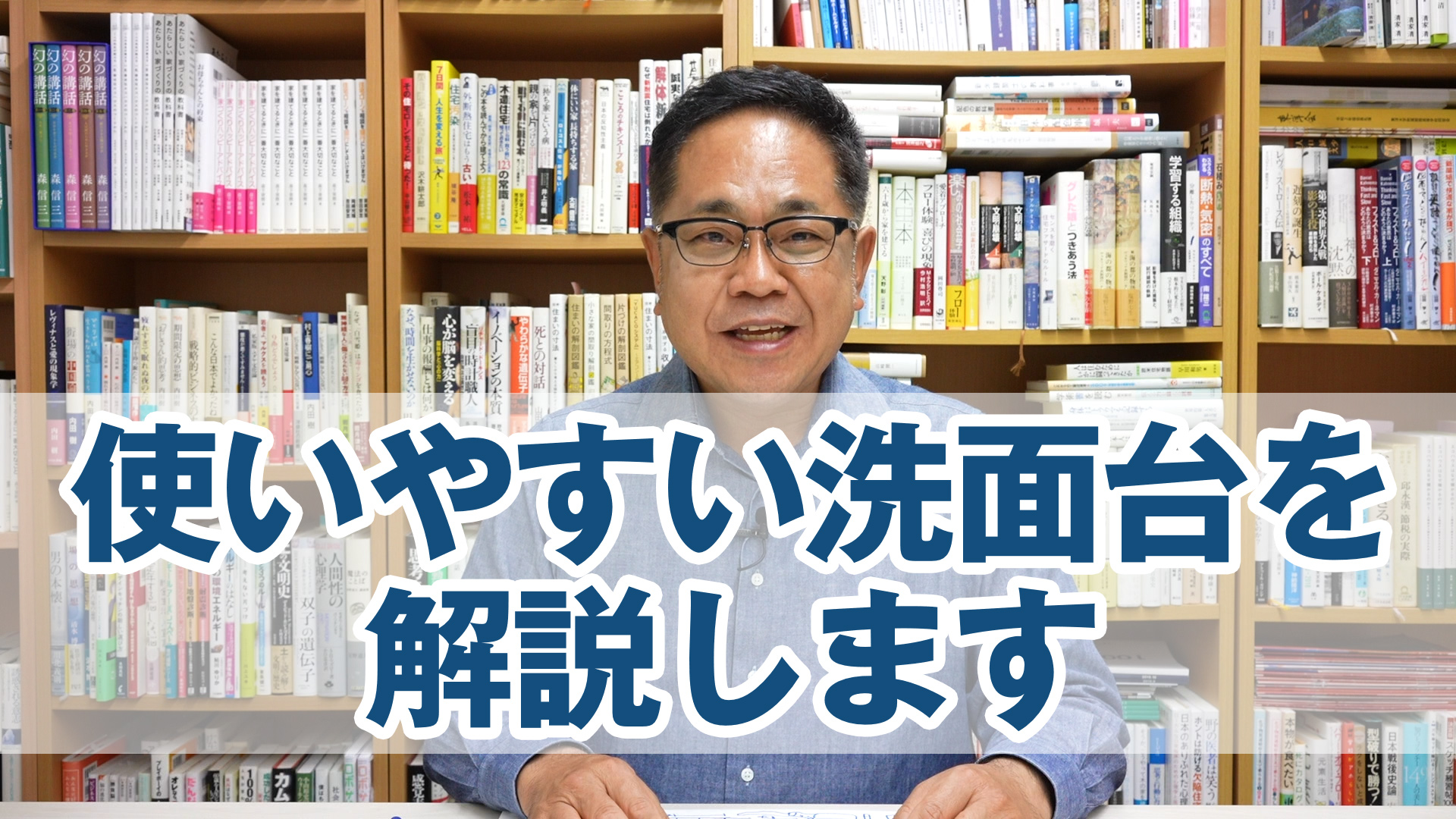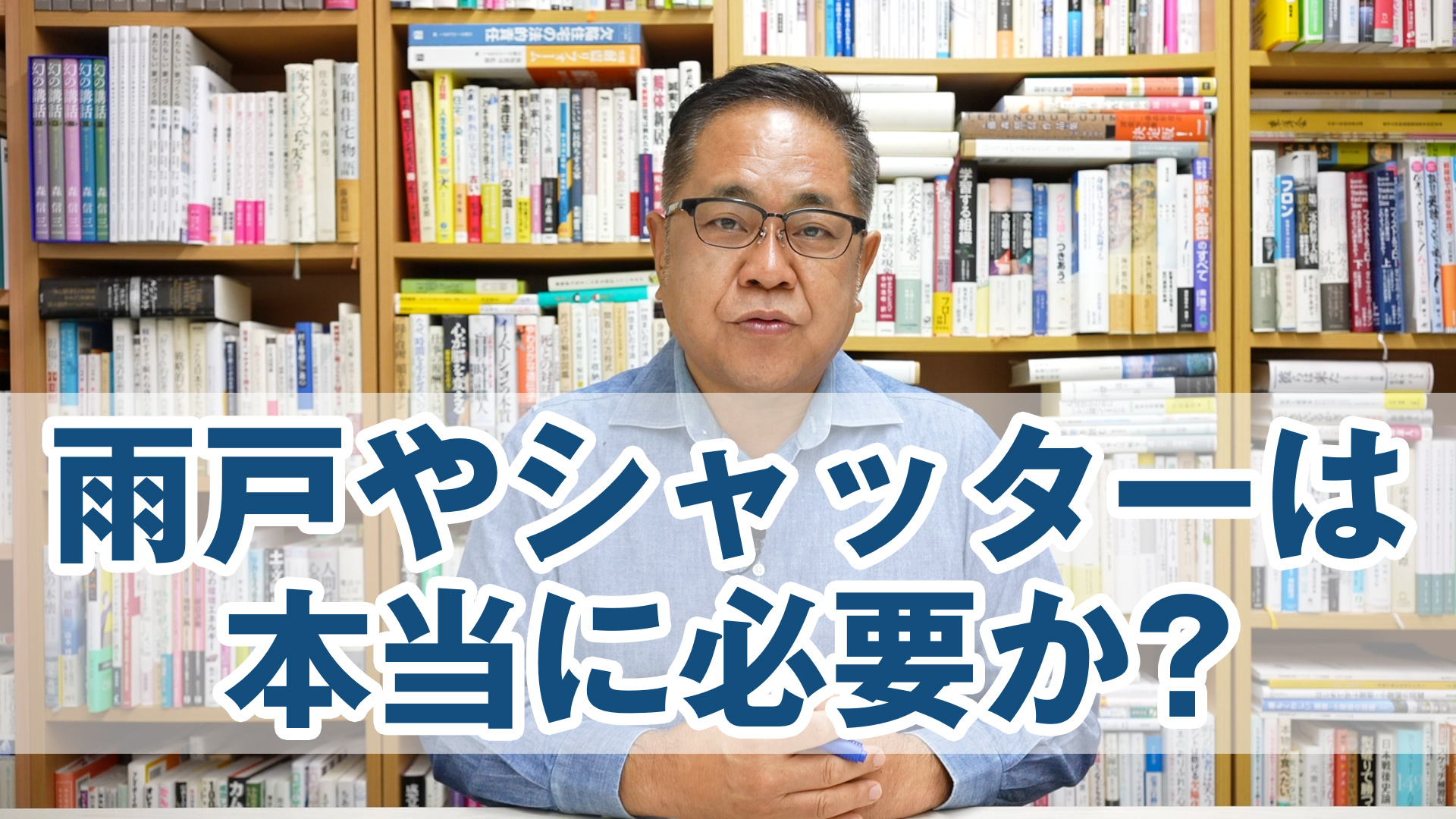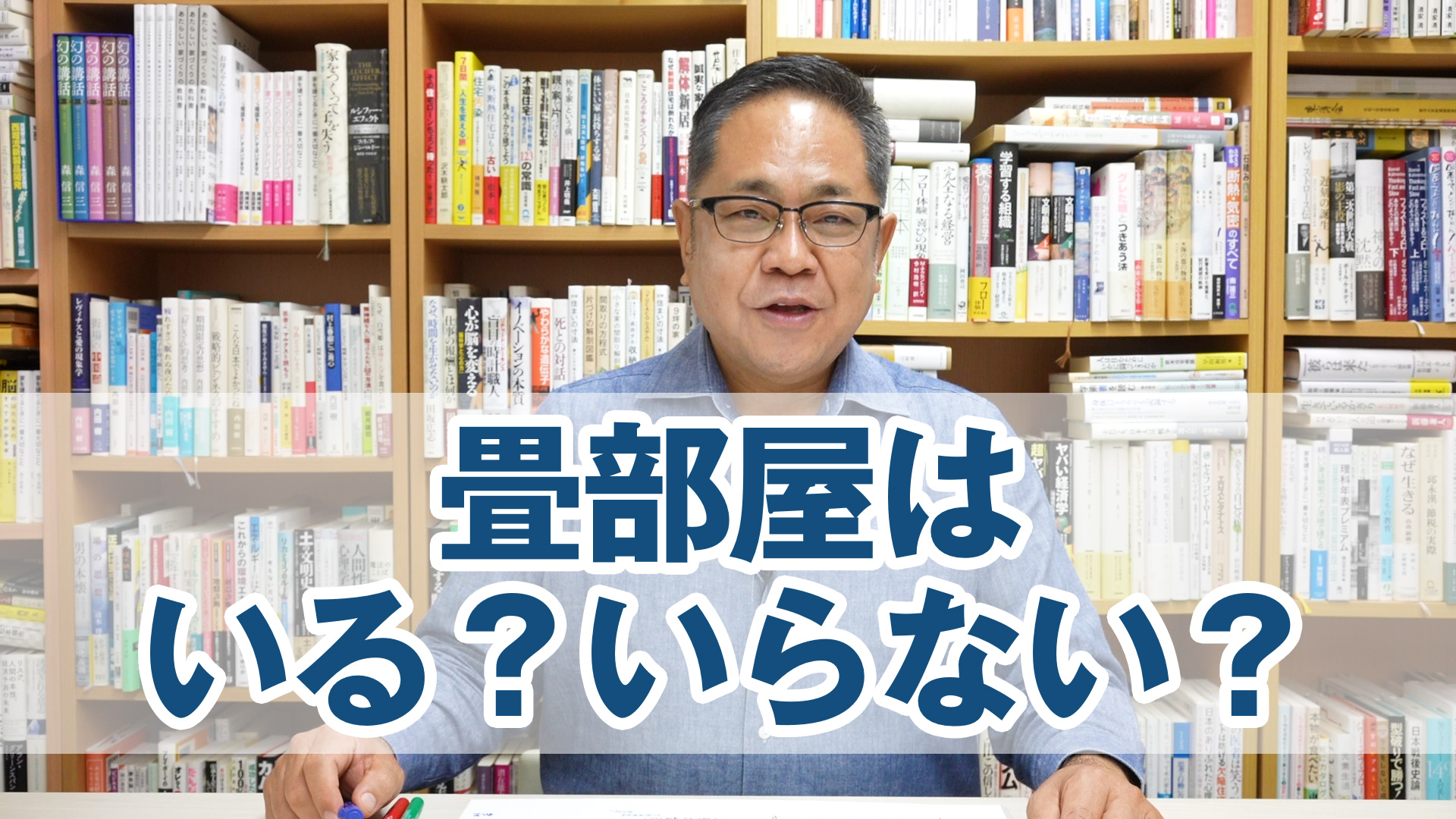人生フルーツ:老いながら生きてゆく家について
人間は誰しも歳を取り、老いとともに暮らしを続けます。今日はそのとき住まいをどう設えるか、板書をめくりながら少し長めにお話ししますので、時間のある方はコーヒー片手にお付き合いください。
題材は2016年に公開され、多くの方がご覧になったドキュメンタリー『人生フルーツ』――九年前にスクリーンに登場し、今もファンの心を温め続ける作品です。東大建築学科卒で日本住宅公団のニュータウン開発に尽力した建築家・津端修一さんと、名家に生まれた英子さんご夫婦が晩年を迎えながら畑を耕し、ケーキを焼き、友を招き、静かに互いを思いやる姿は、「老いながら豊かに生きるとは何か」を端的に示してくれます。修一さんはレーモンド、坂倉準三ら名匠の薫陶を受けた生粋のモダニストであり、一方の英子さんは結婚を機に「何もできないお嬢様」から家事と手仕事の達人へ変貌。二人の時間はお金では買えない果実となり、タイトルの“フルーツ”は人生を実らせる比喩なのだと上映当時感じ入りました。
では、その背景となるレーモンド事務所の話をもう少し。アントニン・レーモンドはフランク・ロイド・ライトの愛弟子で、日本にモダニズムを根づかせた立役者。彼の事務所は漫画界のトキワ荘のように俊英を輩出し、前川國男、吉村順三、ジョージ・ナカシマら錚々たる顔ぶれが羽ばたきました。麻布に建てられた自邸は、木造平屋の翼廊の間に藤棚で覆われた屋根のないパティオがあり、ここが夫婦の食堂兼リビング。南側は床から天井まで解放できるガラス戸、北側はハイサイドライトで安定した光を採り込み、障子が閉じれば断熱層、開けば柔らかい拡散光という、現代のインナーウインドウの先駆けです。若き修一さんはこの空間に出入りし、師の書斎で図面を広げながら「外でも内でもない曖昧な場」の価値を体感します。現在、高崎市美術館の一角にレプリカの井上邸が保存され、建築学生は必ずと言っていいほどこの写真を教材に中間領域を学ぶのです。
レーモンドは戦前の帝国ホテル別館や東京女子大学のレンガ講堂、軽井沢の聖パウロ教会など、日本各地に“風土とモダニズムの幸福な結婚”を実現した建築を遺しました。木梁を現しにしながらも垂木を絞り、深い庇で夏の日射を遮り、冬の低い光を室内奥まで導く手法は、戦後の住宅標準設計にも影響を与えています。津端邸の内障子+ハイサイドライトの断面構成は、そのDNAを忠実に継承したサンプルであり、図面を辿ると梁間寸法、建具の高さ、庇の出まで師弟で驚くほど似通っているのがわかります。
その遺伝子を色濃く受け継いだ津端邸は、名古屋近郊のニュータウンの傾斜地を切り拓き、雑木林三十坪、畑二百坪、キッチンガーデン、そして書庫や機織り小屋を抱いた一種の“里山マイクロコスモス”でした。七十二平米の平屋ワンルームを中心に、後年増築した子ども室やゲストルームが庭を取り囲みます。門をくぐると玄関はなく、テラスと庇で緩衝されたダイニングがいきなり迎え、回遊式の勝手口からも自由に出入りできる。「家は町の延長、敷地全体が玄関」という開放思想です。内部ではダイニングテーブルとL字書斎カウンター、並列のシングルベッド、丸テーブルとパーソナルチェアがシームレスに連続し、照明も家具も低く抑えて視線は庭へ抜けます。南面には深い庇と内障子、北面ハイサイドライトから高窓光、そしてリビング前の縁側的テラスが外へ引き出し、ここがレーモンド譲りの中間領域。浴室・洗面・物干しは一直線で、英子さんが多忙でも家事が数歩で回る“家事動線のコックピット”になっています。
外庭には四季を彩るゾーンがきめ細かく割り振られています。門の左は椎茸と筍の山林、奥に進むとイタリアンハーブとトマト・ズッキーニの畑、その隣はジャムやタルトに使うブルーベリーやクルミの“お菓子コーナー”。たい肥舎では落ち葉と台所残渣を発酵させ、無農薬畑の土を育て、燻製窯では自家製ベーコン、餅臼では年末に餅を搗く。庭そのものが季節のカレンダーであり、英子さんはそこで採れた恵みをケーキや惣菜に仕立てて来訪者へ振る舞い、「贈与こそ人間の営みの核」と微笑みます。『あしたも、こはるびより。』では「男の人は台所が家の中心だとわかっていないのよね」と冗談めかし、修一さんは「あとみよそわか――一度仕上げたら立ち止まり、更に一手加えて完成させよ」という幸田露伴由来の言葉を掲げて、図面も畑も丁寧にファイリング。夫婦にとって家事も設計も同列の“仕事”であり、時間は通帳に貯まる利子のように静かに膨らみます。
そして夫妻が繰り返し語るのは「お金より自由時間」。修一さんは若い頃ヨットを操り、海風を受けながら設計の着想を得る自由を何より大切にしました。英子さんはそんな夫を「無事帰ってきてくれればそれでいい」と笑顔で送り出し、自らは畑と台所の自由時間を満喫する。収穫物と手間をかけた料理を子や孫、隣人に分け与える行為は市場経済の外側にある“贈与”であり、その循環が二人の暮らしをさらに豊かにしました。贈る側も贈られる側も金銭では換算できない喜びを味わい、時間そのものが熟成した葡萄酒のように価値を帯びていく――ここにセカンドライフを超えた「老いながら生きる」温度があるのです。
ここで「あとみよそわか」の由来を補足します。明治の文豪・幸田露伴が娘の掃除を指導した際、「掃き終えたら立ち止まり、あとを見よ。隅に埃は残っていないか、もう一手添えよ。そうすれば“そわか”――物事は整い成就する」と説いた逸話に基づく言葉です。修一さんは若い所員にもこの精神を説き、図面の端に小さく“AMSW”と記しながら設計を磨きました。英子さんはそれを台所に応用し、ケーキの仕上げに粉砂糖をもうひと振り、煮物に柚子皮をそっと載せる。その気配りが贈与の品に宿り、受け取った人は「津端さんらしい味」と頬を緩めるのです。
夫妻の軌跡は書籍でも辿れます。第一作『あしたも、こはるびより。』は英子さん六十代の暮らしを、第二作『ときをためる暮らし』は七十代の畑仕事と保存食作りを、そして遺作『きのう。きょう。あした。』は八十九歳の“初めての一人暮らし”を記録。ページをめくると、季節ごとの作付け表やケーキレシピ、修一さんが残した設計資料のファイリング方法、庭木の剪定カレンダーまで写真と手書きで詳述され、まさに時間のアーカイブです。本に付いた紙の匂いさえ、二人が暮らしの中で熟成させた“時間の香り”に思えます。
映画はその密度の高い日常を追い、やがて九十歳の修一さんのもとに佐賀県伊万里市から一本の電話が入ります。街の医療と心を癒やす複合施設『まちさな メンタルヘルス ソリューションセンター』を設計してほしい──依頼主は映画を観て感銘を受けた医師です。修一さんは「報酬は要りません。最後のライフワークとしてお手伝いします」と即答し、「まっすぐな廊下では人が緊張するから曲線で囲み、植栽と回遊で患者さんが歩きたくなる病院を」と基本構想を描きます。それが彼の集大成となり、設計を終えたほどなくして旅立ちました。残された英子さんは大きな喪失感に打たれながらも、畑に立ち台所に立ち続け、『きのう。きょう。あした。89歳 はじめての一人暮らし』を出版。「死ぬまで家事を続けるのは幸せなこと」と語り、修一さんと同じ九十歳で穏やかにその生涯を閉じます。
ここで私自身の小さな懺悔を。二十八歳で父が急逝し、数年後に末弟の進学を機に母と同居しましたが、私は工務店の仕事と子育てで手一杯、妻も共働きだったため「キッチンは一つでいいだろう」と安易に考え、母のためのパントリーや折りたたみ椅子、目線が外へ抜ける窓辺の作業台を用意しませんでした。最初は張り切って洗濯や掃除を担ってくれた母も、階段の昇降がきついと言い出し、掃除機の重さを気にし始め、いつしか“してもらう側”へ回ってしまった。もし当時、津端邸のように洗濯機から物干しまでを半径三メートルにまとめ、陽だまりの椅子でアイロンを当て、孫と並んで味噌を仕込む小さなキッチンを設けていたら、母は「ありがとう」を 栄養に年を重ね、自分のペースで老いを受け入れられたはずです。家が人を介護するのではなく、人が家事という手仕事で家を介護し返す――その往復運動が人生を支える。バリアフリーは段差をなくすだけでなく、尊厳をなくさない設計思想だと、津端夫妻が教えてくれます。
最後に言葉のニュアンスについて触れておきます。近年「セカンドライフ」という語が軽快に使われますが、私はどこか“余暇消費”の響きを感じます。津端夫妻の暮らしはむしろ“ファーストライフの延長”。彼らは仕事も家事も趣味も切り分けず、朝起きた瞬間から畑に立ち、図面をめくり、夕刻にはパンを焼き、夜は読書と対話で一日を閉じる――子育てが終わっても、健康を損なっても、亡くなる直前まで同じリズムで時間を紡ぐ姿は、人生を二毛作でなく多毛作に変えるモデルです。だからこそ映画のラストで修一さんが新しい設計依頼に目を輝かせた瞬間、観客は「まだ終わらないのか!」と驚き、同時に心底勇気づけられるのです。老いは終わりではなく、熟成の始まりなのだと。
私たちが家を考えるとき、耐震等級や省エネ性能はもちろん大切ですが、年月と共に増幅する“使いこなす喜び”を図面に折り込むことも同じくらい重要です。障子を毎朝開ける所作、湯気の立つ土間で干し野菜を作るルーティン、雨の日にパティオの雨音に耳を澄ます余裕――それらが歳月とともに身体に染み込み、記憶という漆で家族を連結させます。津端邸の素材や寸法が示すのは、プラン以前に“動作と季節が重なる舞台”を作るという設計哲学。これを都市の小さな敷地でも、マンションの一室でも、アイデア次第で翻訳できるはずです。
ですから、新築でもリフォームでも、バリアフリーや趣味室より先に「年を取った自分がまだ台所に立ち、書斎で調べ物をし、庭で草を摘み、隣人にジャムを届ける光景」を設計図に描いてください。玄関は一か所でなくてもいい、畳ベンチと引き戸で外と内をつなぐ中間領域を一つでも作り、洗濯機から物干しまで数歩、鍋から畑まで数歩の回遊動線を組んでおく。そこに“あとみよそわか”――仕上げのもう一手が施されれば、家は歳月とともに熟成し、人生はフルーツのように瑞々しく甘く実ります。今日の長い話が、皆さんの家づくりや将来の住み替えのヒントになればうれしいです。